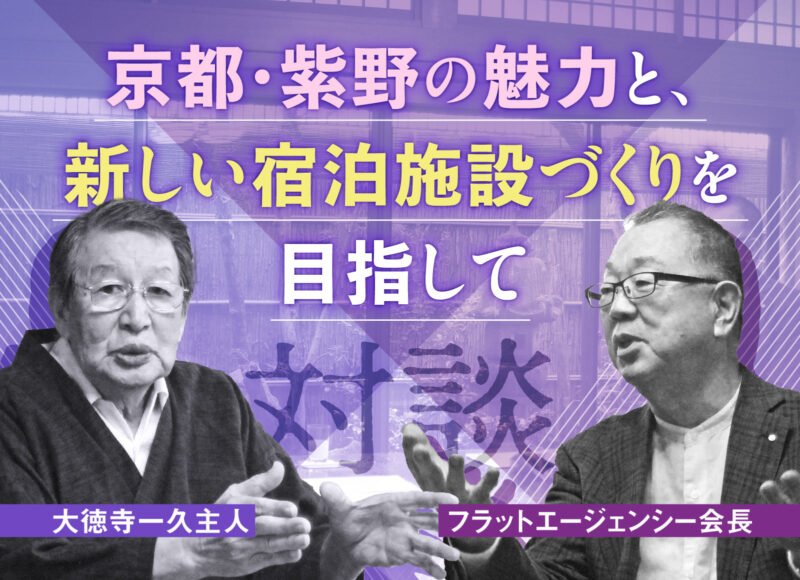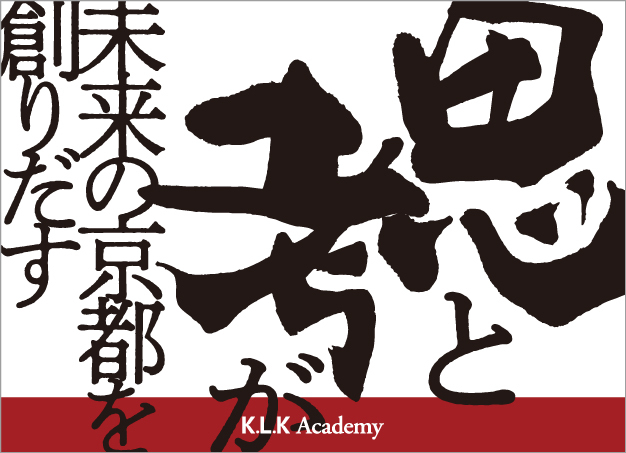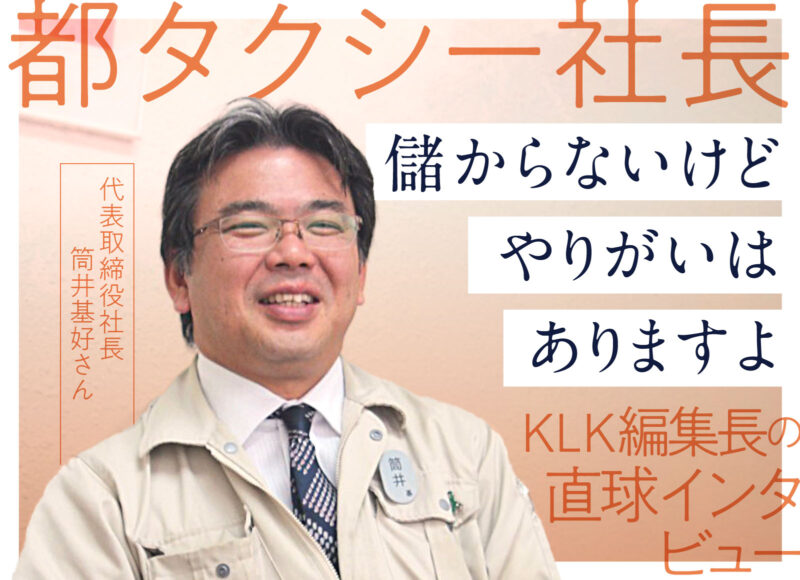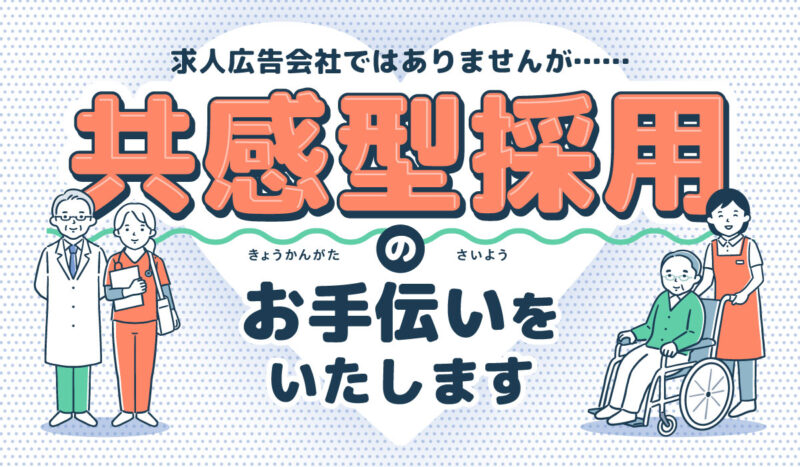発刊告知をご覧になった方から『禁断の京都カースト』(改訂タイトルは『京都カーストは本当に存在するのか』)についてのご批判を多くいただいております。「禁断」×「京都」×「カースト」という組み合わせが、この街における差別を連想させた点、とりわけ「禁断」という言葉が「京都における差別問題」や「同和問題」をカジュアルにコンテンツとして扱っているのではないか?という懸念を与えてしまいました。このことについて編集部を代表して心からお詫びを申し上げます。申し訳ございませんでした。
本編集部は各地域の成り立ちや差異は認めながらも、偏見はなくすべきとの立場にあります。その上で「地域間に格差・差異が存在することを認め、それについて当事者が問題意識を持って語る」事を意図する書籍という趣旨であったにも関わらず、「①序列をつけてしまうようなミスリーディングな編集をしてしまった点」「②告知段階において「カースト」という差別問題・身分問題と密接に関係した用語を用いた事で「京都における差別問題」「部落差別」等を想起させてしまった点」において深くお詫び申し上げます。なお、書題の決定や「序文」「京都カースト基礎知識」など、各区ライターによる直筆エッセイ以外の編集については、各区ライターは関与しておりません。また、疑似キャラクターのイラストについても、イラスレーターは、編集部の指示により制作しました。これらの責は編集部にございますことをご理解ください。
また告知LP(ホームページ)にて行政区を色分けするかのようなピラミッドイメージ図については、丁寧な説明が不足していたことや、表現に工夫の余地があったこと、各区のキャラクター紹介のイラストについては、詳細な説明とともに記載すべきところ、その説明が不足していたことを反省しております。
本書の意義
一方で、「地域間に格差・差異が存在することを認め、それについて当事者が問題意識を持って語る」という点については意義があると考えております。近年でも、大都市における「沿線格差」をめぐるネット記事や、地価などに基づいて地域性を語る書籍等が散見されるのは周知の通りです。そもそも、都市とは人口密集地帯であるため必然的に「中心」と「周縁」が構築されるものです。特に、歴史都市京都においては天皇・政権の所在地を中心として都市発展があったため、都市周縁に「被差別」の歴史があったことも周知の通りです。そのため、古代~近代にかけてのコスモロジー(世界観)が現代にも残っていると考えられます。これらは顕在化していない面もありますが、「現在でも確実に存在し、肌感覚として確実に中心-周縁をめぐる偏見は、残念ながら今日なお残っている」のではないでしょうか。
今回の企画は、当事者各自が肌感覚として感じている「今そこにある京都における地域格差」について物申し、未来においてこれら格差を縮小するために発信する事を念頭においたものです。そのため、当然いわゆるdeep案内のような「都市の周縁やそこに暮らす人々やその文化を単なる面白コンテンツとして提供する」事を意図するものではありません。その点において、本書のタイトルが不適切であった点については、重ねてお詫び申し上げます。
都市は、被差別の歴史の上に成り立っています。しかし、それらは再開発やクリアランスの過程の中で「語られなく」なってきているのも事実です。歴史修正主義者が横行する現代にあって、「今ここにある当事者から見た意識」を記録する事には、「地域格差是正」を目指す上で一定の意義があるものと考えております。
書題の変更と「京都カースト」と記した理由
次に、書題を当初の『禁断の京都カースト』から『京都カーストは本当に存在するのか』に変更したこと、また変更後もなお「京都カースト」という言葉を用いた理由についてご説明を差し上げます。「禁断」という言葉が文脈的に係かるのは、副題「京都人があんまり言いたくないヒミツの話」でしたが、「京都における禁断≒タブー」が差別を連想されるという点において「禁断」という言葉でミスリードを起こしてしまいましたことについてもお詫びを申し上げます。
その上で副題とともに禁断という言葉を削除いたしましたが、それでもなお「京都カースト」という言葉を使うのはこの言葉をもって、京都の地域間差異を語りたいという編集部の強い思いがございます。その趣旨にもっとも適う書題として『京都カーストは本当に存在するのか』に改訂いたしました。
カーストという語は、インド亜大陸における身分制度を示す語彙であり、階層構造・差別構造に直結する語です。また、日本国内においては、例えば「スクールカースト」や「地域カースト」などと階層やヒエラルキーを示す意味でカジュアルに用いられているケースが多く見受けられます。そして、本件において使用した「京都カースト」という語は、X(当時はTwitter)上では2009年から見られた語彙です。「洛中」を中心として周辺部に拡がっていった京都市の歴史において、地域格差や差異が存在することを前提としてその是非を表舞台で問うためには、「京都カースト」というネット社会で闊歩してきたこの言葉をもってして問いかけるべきであると考えました。
「京都カースト」に限らず「○○カースト」という言語が流布しているのは事実です。その良し悪しは別として、またその濃淡は別としても多くの人間の内面には他者との比較による階級意識が存在していると思います。カーストに類する意識を「持ってしまうこと」は、内面的に生じるものであり、それは人間の性ともいえ、止めようもないものだと考えます。しかし、特定の人物や地域にむかって「あの人(地域)は○○だ」と差別することは、あってはならないことです。世の中には様ざまな差別の概念があり、またそれを意味する言葉があります。その言葉を軽々しく使うべきではないですが、その概念について真剣に考え論じようとするにあたっては、言語化せざるを得ませんでした。人間は言葉なしには考えることができないからです。そうである以上、対象物である「京都カースト」を言語化せずに論ずることはできませんでした。
差別する思想の是非と、差別用語自体の存在の是非は別ものです。その言語を使わなければ、その言語が意味する概念や思想自体も無くなるのでしょうか?そうではないでしょう。両者を同一視することは、それこそ「差別をなくす」という正義に対してミスリードを誘引するのではないかと考えました。「言語として発信しなければ良し」とすることでは、差別的な態度や行動の抑制には寄与しない。この概念と向きあうには、その言葉と向きあう必要がある。婉曲な表現は、かえって事の本質を見誤るのではないかと考え、ストレートに「京都カースト」と記しました。そうすることで一人でも多くの方にこの問題と向きあってもらえることと信じております。
本書はその「京都カースト」の是非を問う上で、11行政区や地域に生まれ、住み、ゆかりのある11人の肌感覚による視点を通してそれぞれの地域の差異をお伝えすることによりその格差たるものが本当に意味のあるものなのか、逆にそれは本当にいけないものなのかどうかを考えていただくことを念頭においております。弊社の「京都カースト」問題への取り組みは本書の刊行で終了するものではございません。また、問題提起ともいえる本書を発行した責任があります。その責を果たすためにも、今回の教訓を生かし、この取り組みをよりよい京都づくりに繋げるという初志を貫徹すべく、この問題と向きあってまいりたいと思いますので、温かくお見守りいただければと思います。
令和7年7月7日
サンケイデザイン株式会社 代表取締役
Kyoto Love Kyoto 編集長
吉川忠男