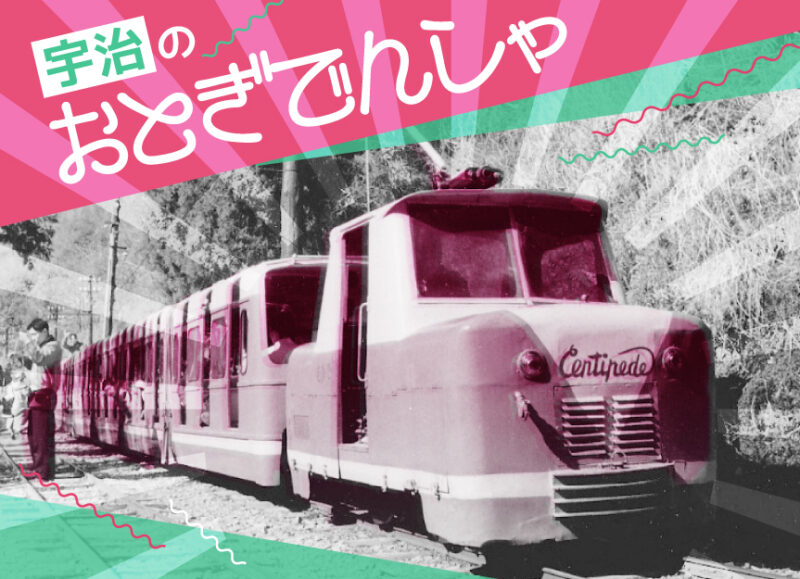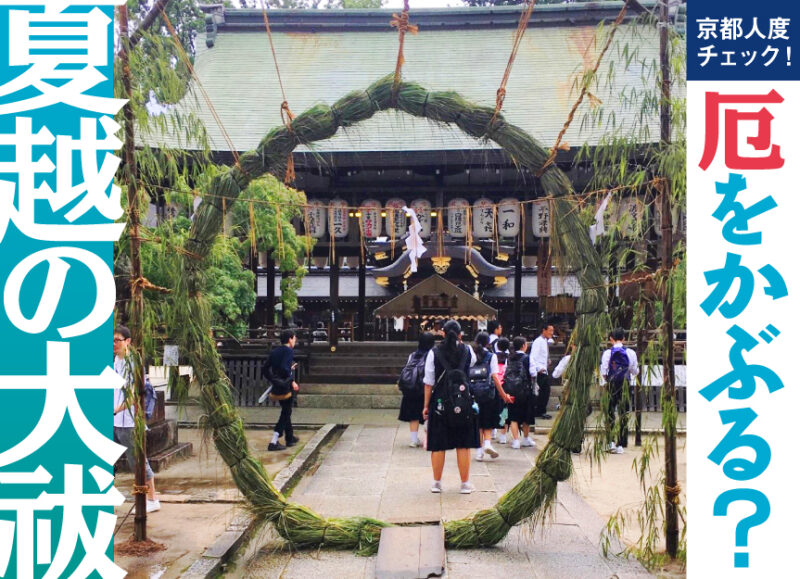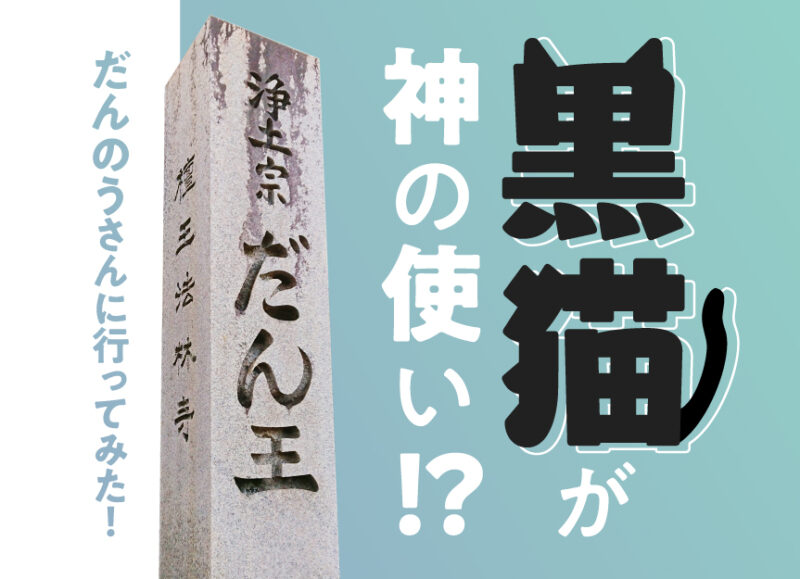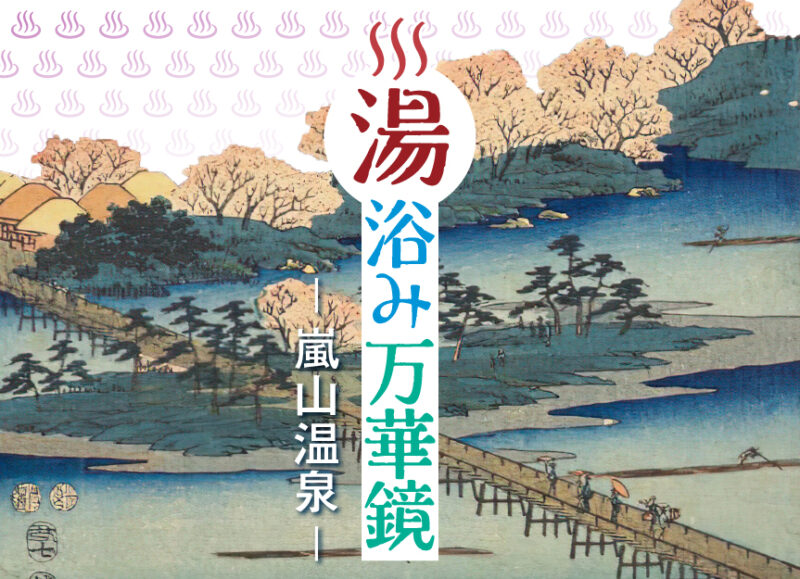昭和50年代、若者はこの店からディスコに繰り出した。
「軽く飯喰うてから、踊りに行こうや」。そんな会話がこの頃の若者たちのお決まり文句だった。週末の繁華街といえばディスコ全盛時分、祇園はまだマハラジャが台頭する前の時代で、「カルチェラタン」や少し大人びた「愛来日庵騎士(アラビアンナイト)」が甘く危険な香りを漂わせていた。そう、ディスコは遊び慣れた若者たちにとって、公然のナンパスポットでもあった。そんな若者たちの夜の導火線はご飯食べ、「かっぱ」かこの「山口西店」がデートコースに選ばれた。中でも「山口西店」は、祇園の真っ只中にあって、当時では珍しい明朗会計なめし処、若者たちにとって絶好の前哨戦店だった。

京都市東山区切通末吉町通を東に向いてすぐの「切通大西ビル」の路地奥にあった時の町家の佇まい。町家使いは先駆的だった。2階のテーブル席は20人ほどの貸し切りも出来、打ってつけの合コン会場にもなり、また晩年は京都会館(現ロームシアター京都)でコンサートを行った後の、アーティストたちの打ち上げ会場でもあった。
祇園で乾坤一擲とばかり「旨い!安い!お気軽」なめし処開業!
一般的に祇園の印象といえば、花街を象徴するように大人の社交場である。辺りには老舗の料理屋や会員制クラブ、小粋なバーが立ち並び、そういった店々の顔であることが馴染のステータスでもあり、ハイソの証しでもあった。そんな高級イメージの祇園で「山口大亭東店」というめし処が創業したのは昭和40年代後半と聞き及ぶ。一本気な男、初代山口春男さんが協力者の支援を受けながらも「旨い、安い、お気軽」を信条に、乾坤一擲、いわゆる居酒屋を開業したのが始まりである。祇園の真っ只中で、誰もが気楽にお茶漬けやごはんが食べられる店があったなら、その閃きは見事に的中し、店は開店するなり大繁盛した。勢いづいた春男さんが2号店「山口西店」の出店に乗り出したのが昭和50年(1975)のこと。長男の徹男さんを引き連れ目星を付けた店は、先見の明ともいえる築100年の町家物件だった。階段箪笥や民芸調度品を設えた店は、路地奥ながらもたちまちに脚光を浴びた。刺身におでん、肉じゃがやいわしの煮付け、いなり焼きといった品書きが所狭しと短冊に書き吊るされ、その価格の安さに客は頬を緩ませた。本家「山口大亭東店」が掲げた「めし処」という肩書の大衆居酒屋、そのあるべき姿を西店も真正面から呈した。

「とろろなっと鉄火めし」は最終680円だった。ちなみに「かやくめし」は450円、「鉄火めし」「とろろめし」は各650円だった。後ろに控えしは「いなりやき」は500円だった。
「山口西店」がようやく軌道に乗り出した2年後、春男さんが惜しくも肝硬変で他界、店の経営と板場は徹男さんの手腕に掛かった。いや、手腕を振るったのは相方、ますみさんの方かもしれない。ますみさんが女将として店を切り回せば、なんともいい間合いで客を取り持った。そして、この伴侶の呼吸のよさが「山口西店」の屋台骨を築いていくこととなる。
常連客のわがままから偶然生まれた最上級「鉄火めし」
時は一億総中流時代から泡沫景気に向かおうとする時代、「山口西店」の店内は、巷のサラリーマンと今どきを謳歌する若者たちが、肩を並べて杯を上げる姿が印象に残る。そんなある日のこと、常連客の一人が人気の「とろろ鉄火めし」に納豆を加えた注文を付ける。別段面倒でもないので、まずは試しにと徹男さんが作り、客に出す前に板場でひと口食べると、これが思いのほか旨いではないか。その徹男さんの反応を見逃がさなかった女将が、次の日早速品書きに書き加えた。「とろろなっと鉄火めし」、何とも長い品書きになったが客席からは注文が殺到した。腹を空かした学生たちには夜遊びの原動力となり、サラリーマンたちのシメには、ちょうどいい酔い覚ましとなった。あれよあれよとこの店のめしものランキングの上位に躍り出た。開業時から48年間ほぼほぼ変わらなかった価格も手伝ってのことだろう、「とろろなっと鉄火めし」はお茶漬けやかやくめしを抜いて「山口西店」の大名物となった。

青春の「とろろなっと鉄火めし」の味よ今甦れ!
小生も青春の真っ只中でむさぼり喰った「とろろなっと鉄火めし」を今ここでじっくりと思い返す。まずはきざみ海苔とワサビの脇役たちに感謝、滋養溢れるとろろと生卵の相性に感心しながらゆっくりとどんぶりの具を箸で掻き混ぜる。おもむろに口に運ぼうとも食欲が勝りついがっつくと、とろろと卵がズルッと音を立てるやいなや、喉ごしよく体に流れ込む。そこへ旨味を増した漬けマグロが、主役は俺だと存在感たっぷりに口中に攻め入ってくる。そして歯応えも優しい納豆の風味が後味のよさを演出する。やや堅めのご飯はどの具にもそれぞれに調和を見せ、「鉄火めし」でも「とろろめし」でもなしえない、「とろろなっと鉄火めし」唯一無二の世界観を味わうことができた。

※2023年11月4日付けの「閉店のお知らせ」がいきなり入り口の扉に貼られた。
「突然のお知らせとなり、申し訳ありません」の言葉に呆然と立ち尽くし、涙した。
本店の「山口大亭東店」はいまだ健在、青春の灯は消えていない