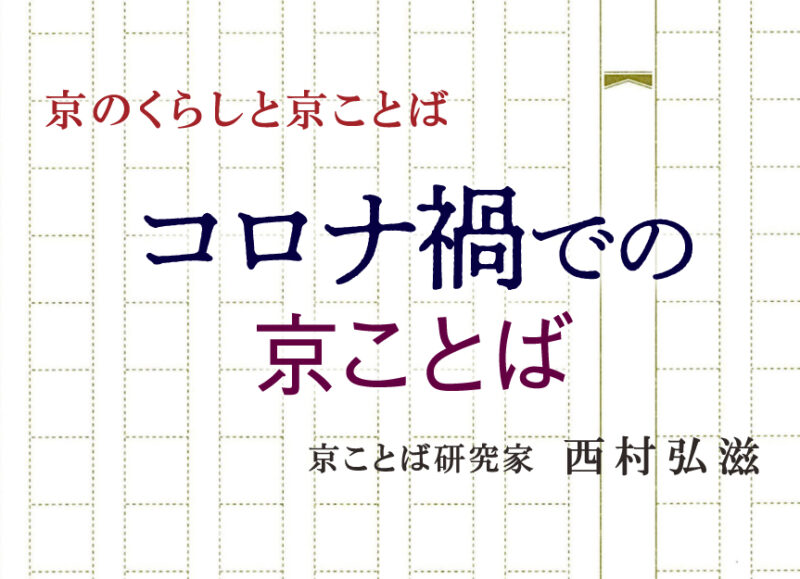京の四季から選ぶ時候の挨拶
刷り上がったばかりの月刊誌や単行本を、取材先や著者、お世話になった方に送る。もう三十数年やってきた定例の営みである。書店に並ぶ前にできるだけ早く届けることを命題にしつつ、一筆箋かハガキを選び、丁寧に手書きの短信を添える。
先様のお顔を思い浮かべながら、時候のご挨拶をしたためる。京都にあまたある美しい景観と歴史ある年中行事。それらが織りなす京都の四季は、実に多彩である。そこから相手の方に合う旬のものを選び出すのは、楽しいひとときだ。

桜もそろそろ終わりなら「円山の枝垂れが、篝火の下で妖艶に舞い散る頃」とか、7月初めなら「祇園祭の二階囃子があちこちから風に乗り、聞こえてくる季節となりました」とか。
長く月刊誌を編集してきたから知り得た、情景ひとつ一つを思い出し、暦や二十四節気も意識して「ことのは」に落とし込んでいく。

こうしたアウトプット作業を繰り返すと、表現力が高まるだけでなく、記憶力も定着するようになる。
また、手書きするという行動で、脳が活発に働き、積極的に注意を向けているものへの集中力が高まり、より記憶力も強化される。
手書きの効用がどんどん解明されているのに、私はというと、ネタ帳にメモ書きする程度で、ほとんどキーボードに頼りっぱなし。だからこそ短信の手書きはずっと続けようと思う。
愛用のペンを手に入れる
どんなペンで書くのか。それも重要な要素だ。私は、家や職場では短信に細字の筆ペンを使う。もう三十数年もこのスタイルである。
いつか墨を磨って愛用の筆で書きたいなどと考えてはいるのだが、いささかハードルが高い。
しかし私には、とっておきがある。名入りの携帯筆ペンだ。
縞更紗柄のペンケースに入っていて、朱の漆塗り。懐からさっと出せば、一見、茶杓袋のような、洒落た佇まいがいい。京友禅のテキスタイルで知られる老舗、岡重の漆職人さんが一本一本丁寧に仕上げたものである。
カバンに入れ、一筆箋やハガキとともに持ち歩いているので、出先でちょっと便りを出すのに、すごく重宝する。

もうひとつ、忘れてはいけないのが、金魚模様のボールペンとシャープペンシル。還暦のお祝いとして友人たちからいただいたもので、これも名入り。
取材など、ネタ帳のメモ書きにはこれを使っている。
愛着あるペンをもつことも、手書きの機会を増やす近道になる。

手書きの方が想いが伝わる?
ところで、手書きは先様への想いをしっかり伝えると聞くが、本当だろうか。このデジタル時代に筆記のコミュニケーション上のユニークな価値を、心理科学・脳科学的アプローチで検証を試みたところがある。応用脳科学コンソーシアム 「アナログ価値研究会」だ。
「手書きの方が、印刷されたタイプ文章に比べ、書き手の想いが相手に伝わる」という
「手書きの価値の実証実験」(※)を行った結果、「手書きによるコミュニケーションは、タイピングされた文字よりも『思いが込められている』というポジティブな印象を読み手に与えうる」ことがわかった。また、人となりの理解につながるという示唆が得られたという。
ただし、「心が込められている」と判断されるためには、時間をかけて丁寧に書く必要があるそうだ。
文字には人となりがしっかり表われるのである。柔らかい字は優しい印象、雑な字は大雑把な印象。慌てず、丁寧に味のある便りをしたためたい。
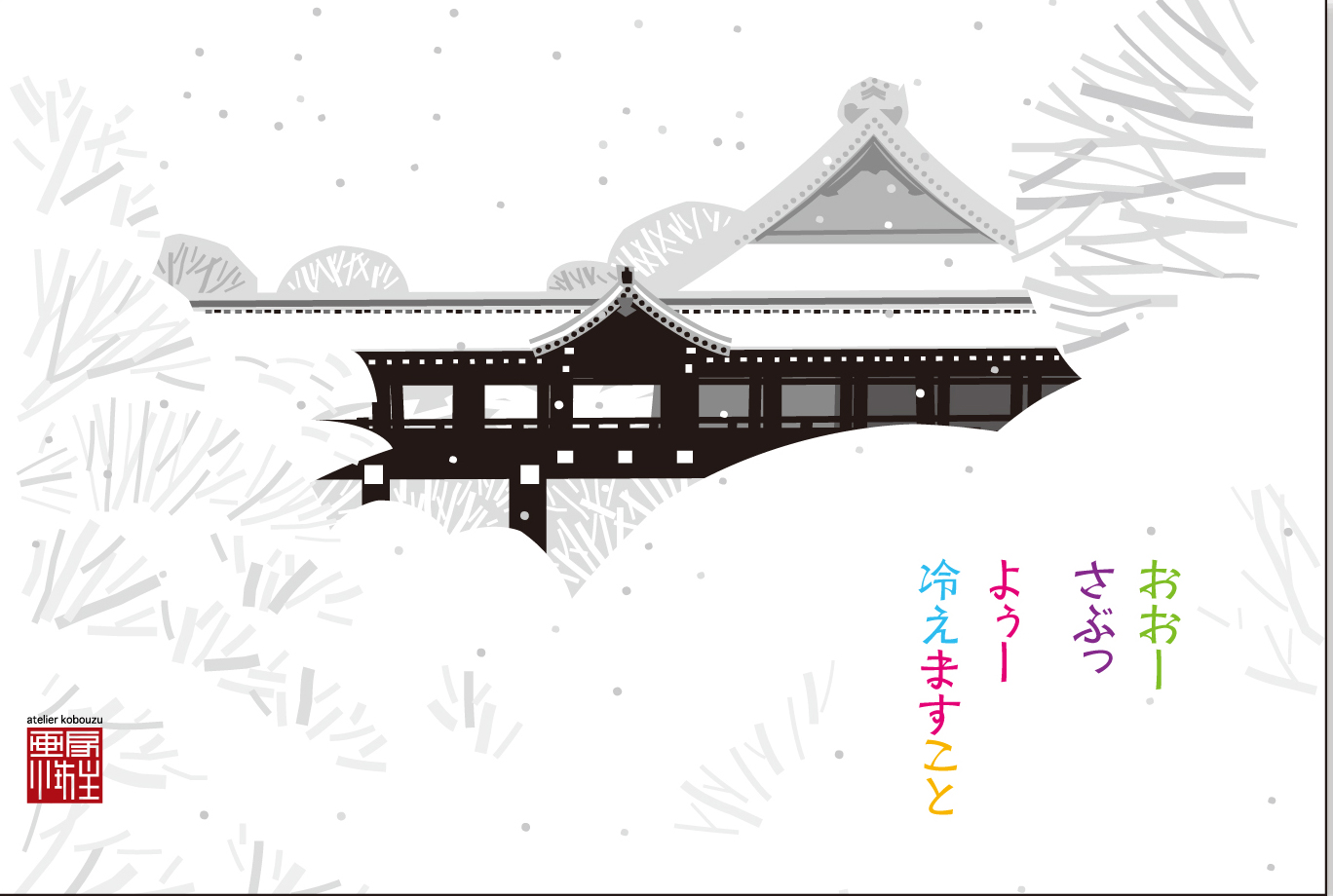
「アナログ価値研究会」は、NTTデータ経営研究所が千葉工業大学知能メディア工学科山崎研究室、東京大学大学院総合文化研究科酒井研究室、王子製紙、ゼブラ、DIC、日本能率協会マネジメントセンターと共同で2015年に組成した研究会。
デジタル化が進む時代において見落とされがちな「アナログ価値」を科学的に示し、その価値を再認識するとともにアナログとデジタルを融合した製品やサービスの開発につなげることを目的としている。
実証実験の概要は、身近な友人への誕生日メッセージカードを、書き手が手書きで丁寧に書いたものと速記したもの、タイプしたものを、読み手がそれぞれの封筒から取り出し、読了後に評価した。
コロナ禍の今、心に響く便り
この春からは、新型コロナウイルスが猛威をふるうようになった。会いたい人にもなかなか会えない。
そんななか、先日、贈った本へのお礼状をいただいた。
封書と便箋はお揃いの「紙司撰」で、夏らしい朝顔の切手が貼られている。作家らしい書き慣れた文字。おそらく愛用の万年筆を使っておられるのだろう。ペンを用意し紙を選ぶところから、相手のことを深く考える時間を取られているのがわかる。
ことば選びに気を配りながら、「ふとした時に思い出し、そうか、その相手はもういないんだ、と気づくことを繰り返している」と、ご家族を亡くされた苦しい心のうちを綴られている。このような状況が収まれば一度ゆっくり会ってお話しさせていただきたい、とも。こちらも心からそう願う。
結びは、あまり心配かけまいとしておられるのだろう、明るいニュースが。気遣いがひしひしと感じられる丁寧なお便りだ。
言外の意味や行間のニュアンスなどが読み取れ、幾度か読み返している。

京ことばで綴る新しいコミュニケーション
京都は、人と人とのかかわり合いがとても密接なところである。
私は、かねてから、日常のちょっとしたことばの掛け合いが、先様への思い入れをじょうずに伝え、互いの心を通じ合わせる機会となっていることに魅力を感じている。
例えば、「どこいかはるのん?」「ちょっとそこまで」など。行先を聞きたいわけではない。
ちょっと留守しゃはるから、気をつけといてあげなあかんな、との気働きも伝えるわけだ。
やんわりとしたコミュニケーション。素敵ではないか。
町のなかで繰り広げられるこうした日常会話を便りに添えてみたい。そうした思いは、人と密になれない今、いっそう強くなっている。
もちろん、書きことばは、ボディーランゲージつきの話しことば以上に深いものを伝え合うことはできない。
しかし、京都の日常会話のなかの、そのやわらかな含み、微妙でいて奥深い言い回しなどを思い出しながら、かな文字にして綴ってみると、気持ちがほぐれてなんだかほっとする。
また、ひらがなの効果なのだろうか、五感が働いて、発想力が豊かになるような気がするのだ。

短信を出す折は、手書きはもちろんのこと、京ことばを添えて。それが話の糸口や、人と人との潤滑油になってくれれば、楽しい。
例えば、時候の挨拶あとの書き出しには「」つきでこう書いてみるとか。
「先日は、おそぉーまで、寄せてもうて、えらいおやかまっさんどした」。
新しいコミュニケーションの形、となれば面白い。