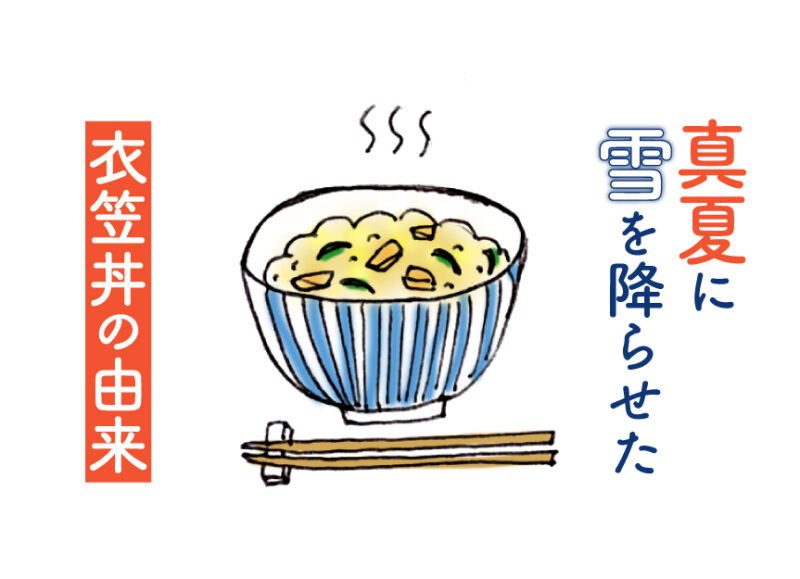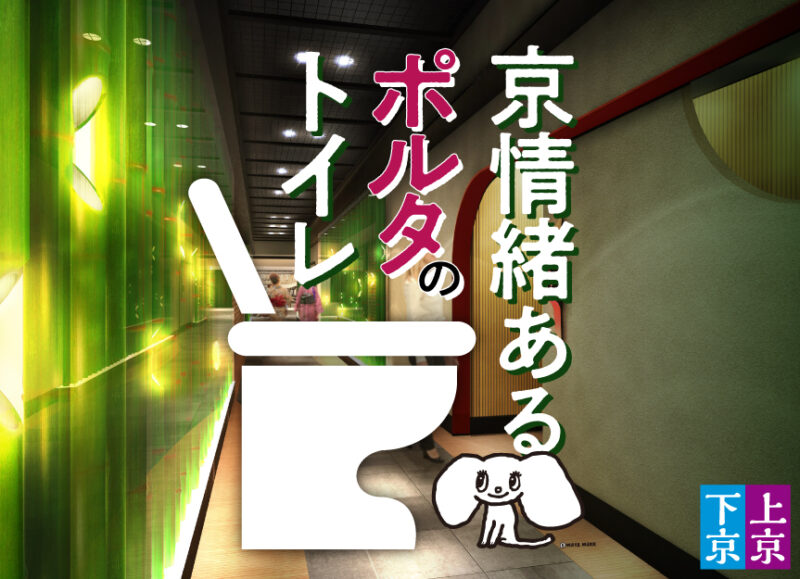「小劇場」を見に行かれたことは、ありますか?
昨年11月、京都の南座が恒例の顔見世興行によって新開場したことが全国的に大きな話題になりました。
歌舞伎発祥の起源が「出雲の阿国」によって上演されたかぶき踊りとされていることは広く知られています。当時から実に400年以上にわたって歌舞伎を上演し続けている南座はまさに日本最古の歴史と伝統を持つ国内では他に類を見ない劇場です。
そしてここ京都は、古くから歌舞伎のみならず様々な芸能、芸術が絶えず生まれてきた文化芸術のまちであり、文字通り「世界遺産」としての価値を確固たるものにしています。
その京都が実は「小劇場文化」を牽引してきたまちでもあることは一般的にはあまり知られていないかもしれません。
小劇場文化とは
例えば「演劇」の場合、ミュージカルのように比較的大きな劇場で上演される演目から、普段は「カフェ」として 営業している場所で行われるものまで実に多種多様です。
その中でも客席数が50席前後のものから多くても200席までの規模の劇場、あるいはそうしたところを発表の場としている舞台芸術公演や劇団そのものを指して「小劇場」と言われています。
京都にはこれまで、歴史的にも多くの「小劇場」があり、そこから国内外で活躍する多くのアーティストや舞台芸樹史に残る優れた作品を生み出してきました。その大きな要因は、京都が長年「大学のまち」であったことが挙げられます。実際「住民の10%が学生」と言われていますが、これは全国2位の東京のおよそ倍の割合です。
「歴史と伝統」だけではなく、世界中から多くの人々が訪れるまち中で刺激を受け、そこから新しい価値観や可能性を生み出す若い世代が常に存在するということは、京都という都市にとって、大切なもう一つの価値ではないかと思います。
ところがここ数年、京都では「小劇場の危機」という事態が起こっています。
いったい京都で何が起こっているのでしょう。