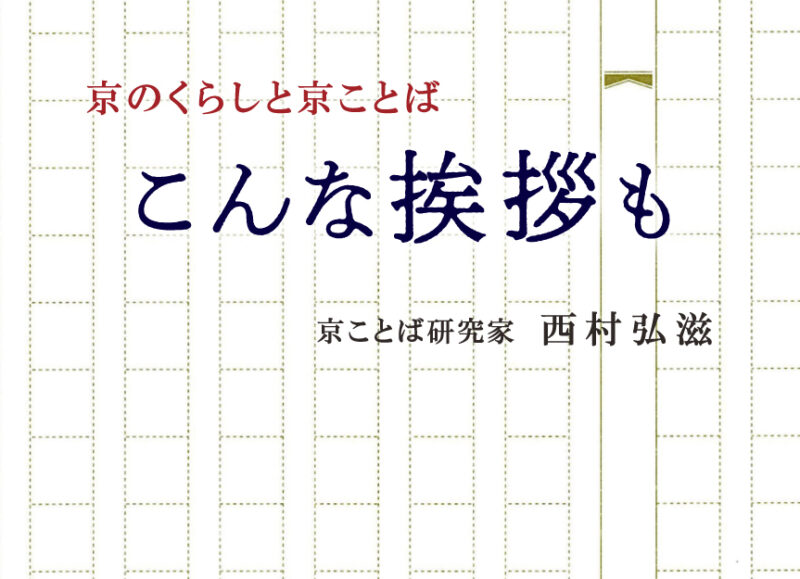思えば、京都の暮らしは習慣に満ちている。
毎月朔日には、月詣りに神社へ通う。帰るころには菓子屋が赤飯を持ってくる。月命日にはお坊さんが来てお経をあげて、十五日が来れば神棚を磨き上げ…とそんなことをしているうちに、もうひと月経っている。
私たちは、ひと月だけではなく、一年を通して習慣を繰り返している。
正月からしめ縄を飾れば、すぐに節分が来る。お雛様を片付ける間もなく菖蒲の節句がやってきて、軒先の地面を菖蒲でぺんぺんとたたいて笑っていると思えば、水無月をほおばった瞬間に、もう祇園祭がはじまる。


毎月毎年、何かを繰り返している。こんなことして何の意味があるんだ、と思っていた若かりし頃もあったが、立派な三十路になった今はぐっとその意味をかみしめることが多くなった。
今月も、菓子屋がほかほかの赤飯を持ってきた。家族で食べる前に、おくどさんと神棚、そして仏壇に供える。
くらしへの御礼と抱負を述べて拝んだあとに、家族みんなでいただく。
小さかった頃は、この赤飯がなによりも嬉しかった。秋になるころには栗もはいっていて、栗ばかりをねだったものだ。
両親と祖父母、叔父、そして私。六人の家族が食卓を囲み、昼食をとっていたが、あっという間に赤飯はなくなってしまう。赤飯とお漬物だけの質素なものだったが、それほどまでに、赤飯という食べ物は大ごちそうだった。
社会人になってすぐ、わたしは九州に赴任した。本社が大阪だったこともあり、出張帰りに京都の実家に寄ることがあった。
さて、ビールでも飲もう、と開けた冷蔵庫の隅に、カチカチに固まった赤飯のかたまりがあった。
老いた両親と、それよりもさらに老いた祖母には、もう赤飯を食べきることができなくなっているのだ。目に見えない月日の重なりが、カチカチの赤飯にうつし出されていて、なんとも言えない、せつない気持ちになった。
そうこうしているうちに、私は結婚をして実家に戻ってきた。毎月一度の赤飯を楽しみにするわが子は、おぼつかない箸づかいで、小さな口に赤飯を詰め込むようにして食べる。
そんな光景をみるたびに、家族六人で食卓を囲んだむかしを思い出す。
習慣を通して、かつての記憶がよみがえる。かつてここにあった、家族の思い出をおもいおこすことができる。
世代を超えて、変わらない習慣があるのは、いいものだ。
写真撮影:Toshi Kano 福永雅文