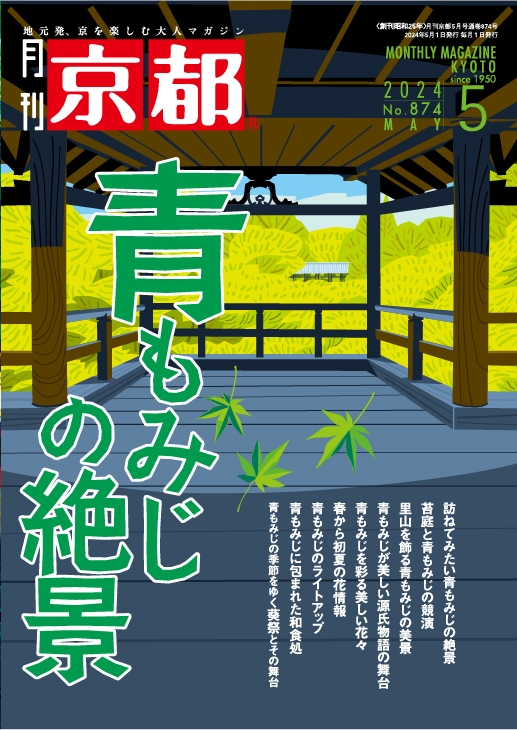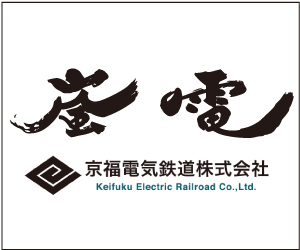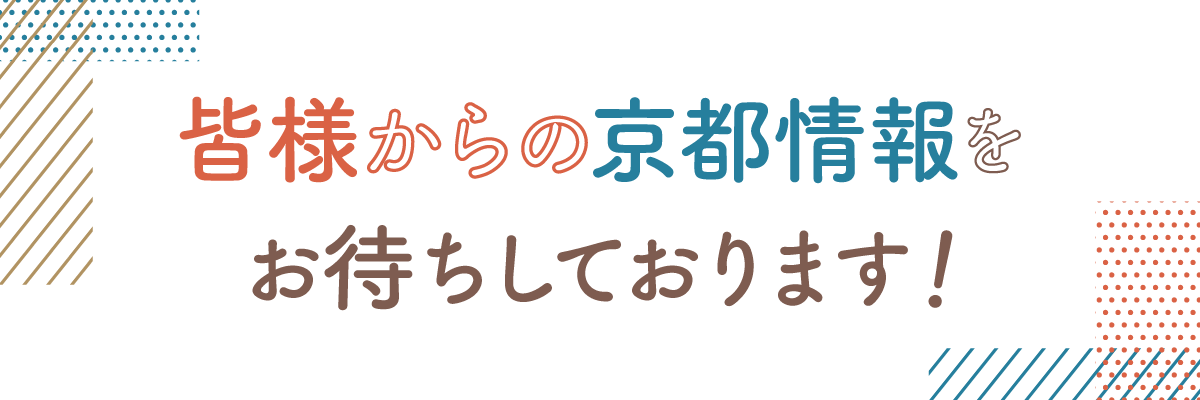茶道とは。何モノか。 その5「大坂 堺 織田信長と茶の湯政道。」
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます
▶︎由緒正しき京菓子店▶︎お盆に始まる行事の数々
▶︎神輿をかつぐ人だけのお弁当
▶︎漱石も惑わされた「おおきに」の意味
▶︎京都の春の味といえば竹の子
▶︎京野菜で作る昔ながらのお雑煮
(いろは歌 :平安中期以後の作)
「色はにほへど 散りぬるを」
いろはにほへと ちりぬるを
「我が世たれぞ 常ならむ」
わかよたれそ つねならむ
「有為の奥山 今日越えて」
うゐのおくやま けふこえて
「浅き夢見じ 酔ひもせず」
あさきゆめみし ゑひもせす
涅槃経 (ねはんぎょう) の偈 (げ) 「諸行無常、是生滅法 (ぜしょうめっぽう) 、生滅滅已 (しょうめつめつい) 、寂滅為楽 (じゃくめついらく) 」の意を訳したもので、この世の全ての現象の理を表しているのである。現象=(有為法 有為と無為)「有為」は仏教用語で、因縁(ネットワークと相互作用)によって起きる一切の事物。有為の奥山とは、無常の現世を、どこまでも続く深山に喩えたもので、平家物語、敦盛と同じくいろは唄も、善・悪 好・悪 有・無の二極以外。常に変化流動するの第三極「空」を歌った、2世紀に生まれたインド仏教の僧 龍樹(ナーガールジュナ)が「有為の中論」で記した理論である。
人間五十年、
「人の世の50年、下天の一日なのである。」
化天のうちを比ぶれば、
「化天の一昼夜は800年」夢幻の如くなり。
「夢幻 一瞬だ。」
一度生を享け、
滅せぬもののあるべきか
「一度 生を受け、
死なぬ者などあるものか。」
これを菩提の種と
思ひ定めざらんは、
口惜しかりき次第ぞ。
「これが仏の定めとも、
悔しい事 限りなし。」
桶狭間の戦いで今川義元軍の尾張侵攻を聞き、清洲城の織田信長は、人間五十年、化天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり一度生を享け、滅せぬもののあるべきかこれを菩提の種と思ひ定めざらんは、口惜しかりき次第ぞ。「敦盛」のこの一節を謡い舞い、陣貝を吹かせた上で具足(甲冑や鎧・兜)を着け、立ったまま 湯漬を食したあと、甲冑を着けて出陣した。
織田信長は母・土田御前が信秀の正室であったため2歳にして那古野城主となる。しかし、身分にこだわらず、民と同じように町の若者とも戯れ、幼少から青年時にかけて奇妙な行動が多く、周囲から尾張の大うつけと称されていた。今川氏へ人質として護送される途中で松平氏家中の戸田康光の裏切りにより織田氏に護送されてきた8歳年下の松平竹千代、後の徳川家康と幼少期を共に過ごし、後に、両者は固い盟約関係(清洲同盟)を結ぶ事にななった。
尾張の大うつけと呼ばれた信長は生母と弟の謀反に遭い弟を殺害している。
桶狭間の戦いでは、幼少の頃から竹馬の友である徳川家康が敵方の先鋒として率いる2万人とも4万人とも云われる今川氏の軍勢に対して織田軍は総兵力5千人で勝利した。
ルイスフロイス
宣教師ルイス・フロイスの記録には、彼(信長)は中くらいの背丈で、華奢な体躯であり、ヒゲは少なく、はなはだ声は快調で、極度に戦を好み、軍事的修練にいそしみ、名誉心に富み、人情味と慈愛を示し正義において厳格であった。彼の睡眠時間は短く早朝に起床した。貪欲でなく、はなはだ決断を秘め、戦術に極めて老練で、非常に性急であり、激昂はするが、平素はそうでもなかった。彼はわずかしか、また ほとんど全く家臣の忠言に従わず、一同からきわめて畏敬されていた。酒を飲まず、食を節し、人の扱いにはきわめて率直で、自らの見解に尊大であった。彼は日本のすべての王侯を軽蔑し、下僚に対するように肩の上から彼らに話をした。
彼は善き理性と明晰な判断力を有し、神および仏の一切の礼拝、尊崇、並びにあらゆる異教的占卜や迷信的慣習の軽蔑者であった。形だけは当初法華宗に属しているような態度を示したが、顕位に就いて後は尊大に全ての偶像を見下げ、若干の点、禅宗の見解に従い、霊魂の不滅、来世の賞罰などはないと見なした。
彼は自邸においてきわめて清潔であり、自己のあらゆることをすこぶる丹念に仕上げ、対談の際、遷延することや、だらだらした前置きを嫌い、ごく卑賎の家来とも親しく話をした。彼が格別愛好したのは著名な茶の湯の器、良馬、刀剣、鷹狩り。
彼は少しく憂鬱な面影を有し、困難な企てに着手するに当たっては甚だ大胆不敵で、万事において人々は彼の言葉に服従した。趣味は舞と小唄。敦盛一番 の外はお舞にならず“人間五十年、下天の内をくらぶれば夢幻のごとくなり”の節を歌い慣れた口つきで舞われます。
つまり、織田信長の人生観は、「是非に及ばず。」良いも、悪いもない。自分の成したい「天下布武」に真っ直ぐ走るだけだ。結果などどうでもいい。いつ死んでも構わない。人生とは生死を賭けた遊びという事なのである。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます
▶︎由緒正しき京菓子店▶︎お盆に始まる行事の数々
▶︎神輿をかつぐ人だけのお弁当
▶︎漱石も惑わされた「おおきに」の意味
▶︎京都の春の味といえば竹の子
▶︎京野菜で作る昔ながらのお雑煮


関連する記事
 松尾 大地
松尾 大地
昭和44年(1969年) 京都 三条油小路宗林町に生まれる。
伏見桃山在住
松尾株式会社 代表取締役
松尾大地建築事務所 主催 建築家
東洋思想と禅、茶道を学ぶ。
|禅者 茶人 建築家|茶道/茶の湯/侘び寂び/織田信長/村田珠光
アクセスランキング
人気のある記事ランキング