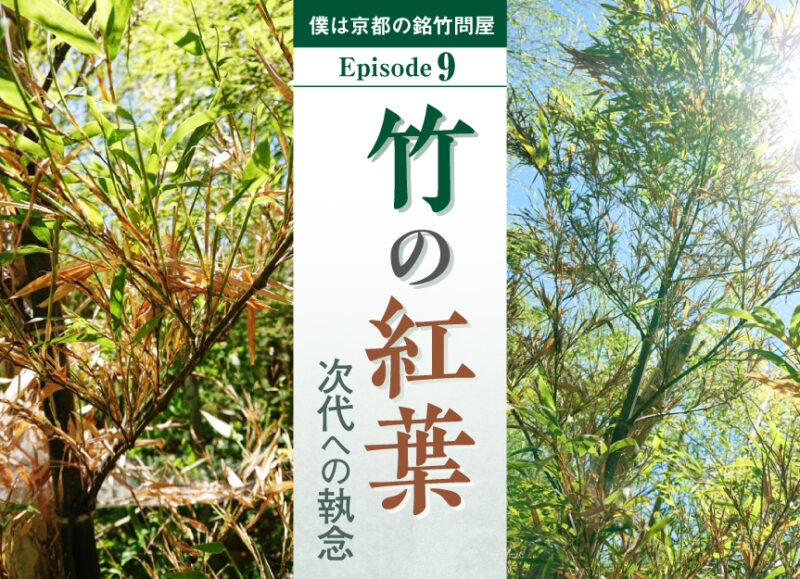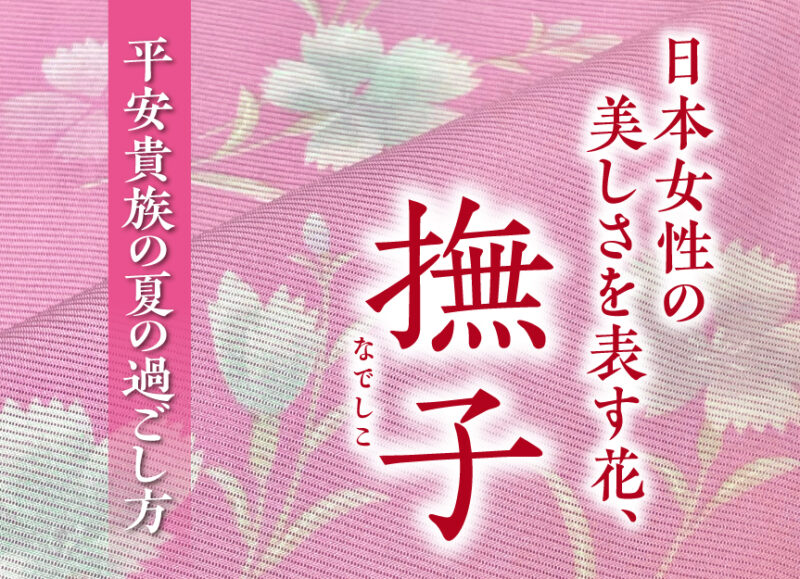五山の送り火でお精霊さまをお見送りすると、急に季節が進む京都。昼間は夏を思わせるような暑さでも、日の暮れは日に日に早くなり、蝉の声から虫の音に変わってくると、すぐに秋の気配を感じます。
そろそろ春夏に使っていたうつわも、秋らしいものと入れ替える時期かなと。(そんな大げさな作業ではなく、食器棚の奥に入っている秋冬うつわと入れ替えするだけですけどね)
うつわのメンテナンス
皆さんのお家にある、お気に入りのうつわ(私たちの名前「おきにのうつわ」の語源です)を長く使ってもらえるように今回はうつわのメンテナンスについてのお話。
まず、うつわの部位のお話から。
うつわにもその部分ごとに名前が付いています。産地や工房、お店によって名称に若干の違いはあると思いますが、その名前からまるで人の姿のように思えます。

①口縁 うつわの上の縁の部分
②首 徳利・花瓶など袋もの(★)細い部分を指します
③肩 袋ものの細い部分から徐々に太くなるあたりを呼びます
④胴 口から下の部分、同じ太さの部分を指します
⑤腰 胴から下のカーブを描く部分
⑥高台 うつわの最下部、テーブルに接着する部分。ほとんど円形ですが、多角形や高台のないデザインのうつわもあります
⑦見込み 鉢や皿を上から見た部分を言います
⑧耳 花瓶や壺など首から肩の部分に付いた突起の部分
⑨手 急須や土瓶などには手(取っ手)もあります
⑩印 作者の雅号、窯銘が入っています。ハンコでギュッと押して凹ませたり、染付で書かれたタイプ、上絵付けで書かれたものなどがあります。
(★)袋もの…徳利・花瓶・壺など胴より口が細くなったものの総称

買ってすぐに高台の点検
うつわを買ってすぐ点検していただきたいのが、高台。特に土ものは触ってざらざらしていないかチェックしてください。気になるときは紙やすりで磨くと、テーブルにキズをつけるのが防げます。

陶器はしっかり乾燥させて
食事の後、料理の油やこびりつきが強い時、水にしばらく浸けたりしますが、この時も材質の違いに注意。
磁器はそれほどではありませんが、陶器は顕微鏡で見ると生地の目が粗くすき間が多くあります。吸水性が高いのであまり長時間に渡り水に浸けずに洗ってください。その後タオルなどで拭いてしっかりと乾燥させることが長く楽しむコツです。食器棚にすぐに片付けないでしばらく乾燥させるとなお安心。だからって面倒と汚れを放置しておくのは絶対NG。
料理を盛りつける前にさっと水にくぐらして拭いてから使うと、強い汚れをさけるとも言われています。
また、土ものは焼き上がった後「キン、キン♪」という金属音を奏でます。これは温度が下がっていく際に生地と釉薬の収縮度合いの違いから、うつわの表面に「貫入(かんにゅう)」というヒビのような模様が入り、その時に出す音なのですが、陶磁器卸業の夫のところに納品されてからも時々奏でています。
この貫入からはどうしても食事の調味料などの色が染み入ってきます。新品のころは気にならなかった貫入が、しばらくすると目立ってくることも。汚れてしまったと感じられるかも知れませんが、皮革製品が日焼けして良い味を出すように、それを「うつわを育てる」と言って先人は楽しんできました。

食器棚への収納
食器の収納について。これまでにも紹介してきましたが、大まかに言うと陶器は磁器と比べてやわらかく仕上がっています。ですので、やわらかい陶器の上に堅いものを重ねるのはタブー。石ものの高台で、土ものの表面を削ることになります。どうしてもこのように重ねて収納したいときは、キッチンペーパーや布を敷くと下のうつわにキズが付きにくくなります。

うつわとの突然の別れ…でも
気に入っているうつわに限って割ってしまった…なんてことありますよね。
私も一瞬の油断で割ったり、欠けさせてしまって、1日中ブルーな気分で過ごしたこと、何度もあります。
そんなときに頼りたいのがうるしの職人さん。「陶磁器なのにうるし!?」と思われますが「金継ぎ」という修理方法があります。
①陶片の鋭利な部分を紙やすりやハンドグラインダーなどで削ってなめらかにし、マスキングテープを使って仮止めし、原型を再現。
②小麦粉とうるしを混ぜた「麦うるし」などで陶片を接着。さらに砥の粉とうるしを混ぜた「錆漆(さびうるし)」で目地を埋めます。
③十分にうるしが固まったら、はみ出たうるしを磨いて表面を平らにし、ヒビの部分に再度うるしを塗って、真綿で金粉を付けていきます。
大きさにもよりますが、1ヶ月程かけて修理されます。
決して元通りとはなりませんが、金の装飾でまた新しい印象が生まれます。せっかくのお気に入りのうつわ、こうして大事に使ってあげたいものですね。

(手ほどきを受けて夫が金継ぎしたものです)
秋を感じるうつわとは
さて、京都のやきもの、陶器と磁器の違いがわかったところで、我が家の食器棚の奥から衣がえをした、秋のうつわってどんなものでしょう。
そろそろ収穫時期の、お芋さんやかぼちゃ、きのこ、新米などの食材が楽しめます。日夜涼しくなってくると、あたたかいお料理が恋しくなってきますね。そんな秋の恵みを盛るのは素朴でかつ保温性のある〈ぽってり〉としたフォルムの陶器がオススメ。

ほんの一例ですが、写真のような刷毛でさっとうつわに模様が描かれた「刷毛目」、カラメルのような色の「飴釉(あめゆう)」、淡いグレーベージュに白い斑点が特徴の「御本手」など、暖色系の色の“土もの”のうつわが合います。
もちろんこれ以外に磁器でも秋のお花が描かれたお皿や、白っぽい厚手の生地のうつわや、寒色の青でも色調を下げたものでしたら秋らしい印象を与えてくれます。
お箸置きも季節を感じさせる重要なアイテム。紅葉や菊の花、柿など季節のモチーフがあるだけでぐっと季節感が引き立ちます。

こんなにも豊富な技法、デザインのうつわがある京都。食空間コーディネーターの私としてもカジュアルなシーンから、格式高い場面、スタイリッシュな空間、はたまたナチュラルな表現など多岐にわたるご提案が可能で、こんなに面白い環境はないと思っています。
皆さまも、食器棚を見渡してみると、そういやこんなうつわもあったな…なんてこともあるかも。ぜひうつわで季節感を感じてみてください。
「おきにのうつわ」は祖父の代から京焼・清水焼の卸売をしている夫と、食空間コーディネーターの私との夫婦ユニット。当初は2人が深く関わる京焼・清水焼にまつわることをSNSに発信したり、イベントやセミナーなどにお招きいただき、お話させてもらってきました。近年は、やきもの以外の工芸品のPRや展示会プロデュースなどを手がけることも増え、〈作り手〉と〈買い手〉をつなぐ〈つなぎ手〉として活動しています。
今回は京都のやきものの紹介になりましたが、食卓にはやきもの以外にも漆器や木製品、金属製のアイテムもあります。また、床の間や棚にしつらえる飾り、身につけるものなども伝統的な技術を使って、今の時代に合うように作られたおしゃれで素敵な工芸品がたくさんあります。
我が家でスタートさせた、京都の伝統的なものを愛でたり使ったりして日々を楽しむ活動、略して「伝活」を今後も文章にしたためて紹介していきたいと思います。