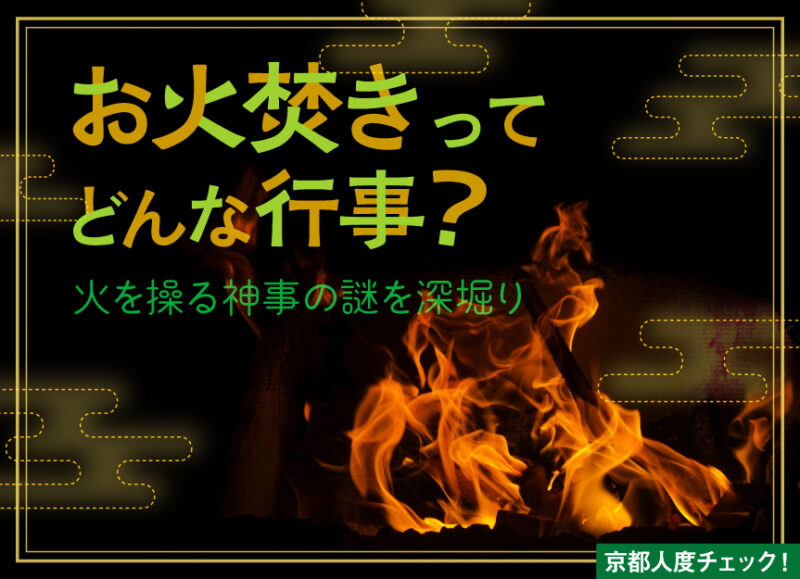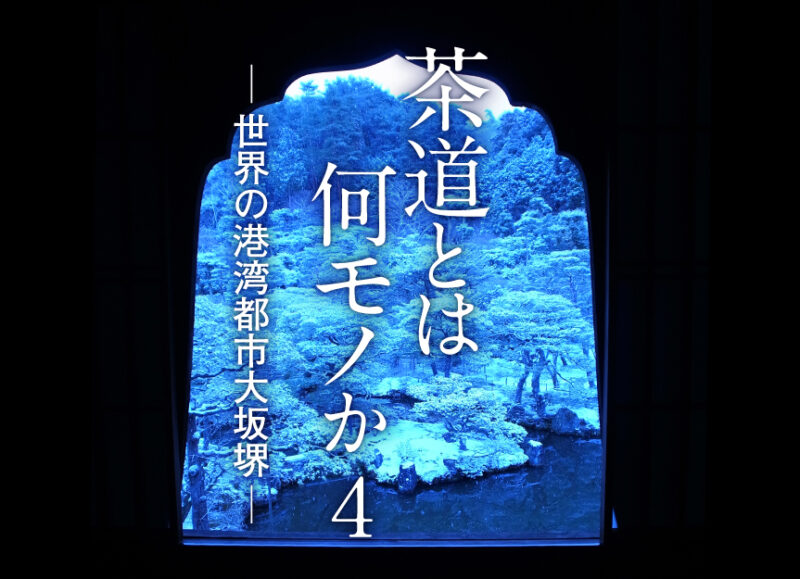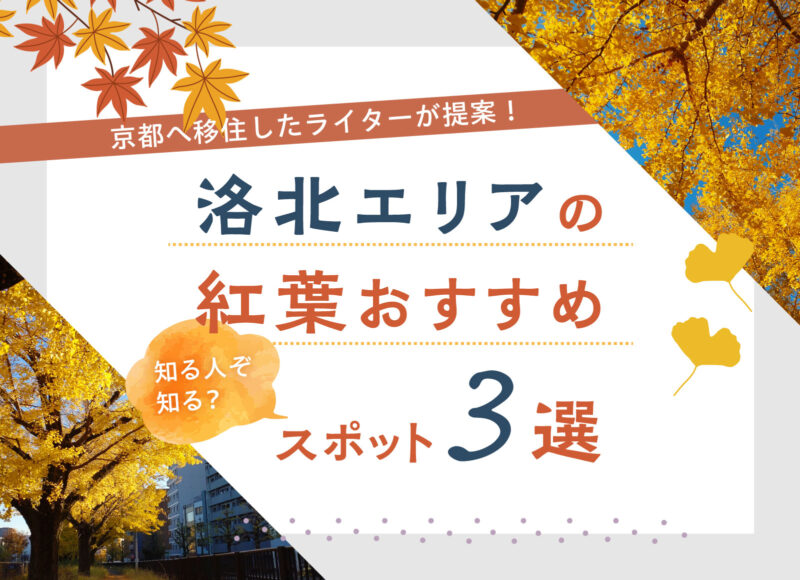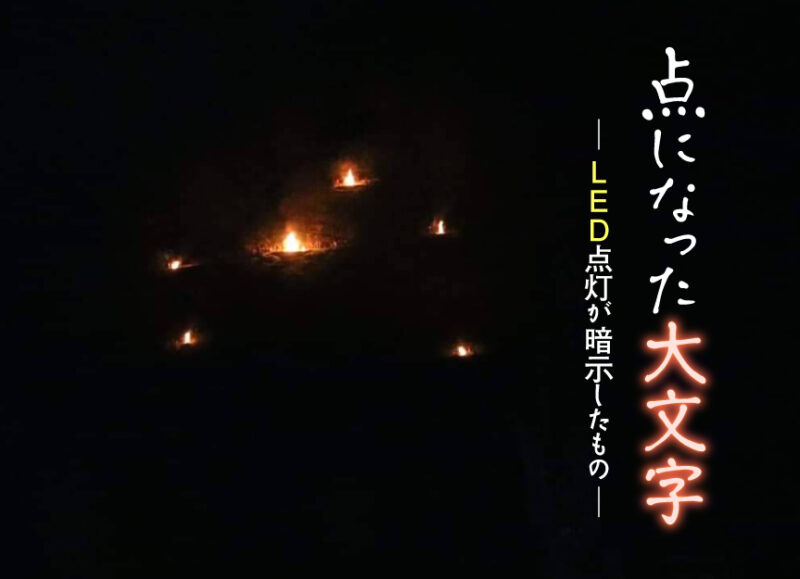3月3日は上巳の節句、お雛祭りです。古来より雛道具として貝覆い(貝合わせ)や貝桶はお雛様と共に飾られてきました。貝合わせ、というと多くの人が真っ先に『源氏絵(源氏物語絵)』を思い浮かべると思います。実は、とも藤では源氏絵の貝合わせを制作しておりません。現代では源氏絵を楽しめる人が少なくなっていますので、源氏絵でなく宝尽くし文様が描かれた貝覆いをご提案しております。あえてお造りしていませんが、蛤貝に描かれた艶やかな源氏絵はやはり魅力的なものです。源氏絵は日本の美術工芸の題材として数多く製作されていますので、主要な場面を知っておくことで美術鑑賞がもっと楽しくなります。今回は、源氏絵の魅力と楽しみ方を貝合わせとともにご紹介します。
『源氏絵』といえば、土佐派の絵師たち
『源氏物語』は平安時代中期に紫式部によって書かれた物語です。平安時代末期ごろから『源氏物語絵巻』として絵画化されるようになりました。平安・鎌倉時代の源氏絵はほとんど失われており、室町時代から、桃山、江戸時代のものが残されています。源氏絵を知る上で、覚えておきたい人物は桃山時代の土佐光吉(みつよし)とその子(または弟子)で、江戸時代初期に活躍した土佐光則(みつのり)です。
まずは土佐光吉を是非知ってください。現代も愛され続ける『源氏絵』の様式を生み出した方です。光吉は土佐家の後継が戦没したので土佐派を継承しました。土佐家代々に伝わる絵手本を有職故実を踏まえて整え、新しい構想も加え、絵図の様式を生み出しました。蛤貝に描かれる源氏絵の多くは土佐派のスタイルと思って良いでしょう。貝覆いの煌びやかさは桃山時代の華麗な雰囲気なんですね。
次に土佐光則です。父の光吉の絵もとても細かいのですが、息子の光則の画風は驚くほどの精密さと緻密さで知られています。源氏絵には寝殿などの建物や衣裳、調度類が欠かせませんが光則が描く源氏絵はまさに細密画。当時は室内を豪華に彩る狩野派の障壁画など大きな絵がもてはやされていましたが、この親子の細かい絵は目を凝らしてじっと見るうちに物語の世界へと引き込む、物語絵にぴったりの画風で、この後の多くの絵師が描く源氏絵にも大きな影響を与えました。源氏絵は次第に場面選択、構図やポーズなどが定型化してゆきます。

特徴的な「吹抜屋台」
それでは源氏絵を楽しむポイントをご紹介します。まず注目すべきは建物です。斜め上からの視点から、俯瞰して見下ろす大和絵の手法で「吹抜屋台(ふきぬきやたい)」と言います。屋根、天井、鴨居などは必要に応じて、あったりなかったりします。屋内を覗き込むような構図は情景を説明的に描くのに適しています。また建物と庭が描かれている場合、草花は季節を知るための重要な手がかりになります。
蛤貝にも吹抜屋台で描かれていますが、実は制作するのには蛤貝ならではの工夫があります。そもそも生き物ですから貝の大きさを全てぴったりと揃えることは出来ません、貝の内側は1個1個それぞれにカーブの具合も違います。貝によっては面自体が波打っていたり小さな突起が出ているものもありますので、直線的な建物を描くのには適さず、どうしても歪んで見えてしまいます。蛤貝に描かれる源氏絵には絵の上下に金雲が描かれていますが、これは蛤貝という菱形で複雑な曲面に定型化された源氏絵を描くための必要な手法だと思います。金雲があることで、ばらつきのある蛤貝がまとまったセットになるのです。


服装で読み解く
次に人物の見分けについてです。源氏絵にはさまざまな人物が描かれていますが、主要な人物は、公達(貴人)、従者、侍童(貴人のそばに仕える少年)姫君、僧などです。人物については男性に注目して見ることが絵を読み解く近道になります。

男性の中で貴人と従者は服装で大体見分けることができます。貴人は冠直衣、従者は烏帽子に狩衣です。直衣(のうし)と狩衣(かりぎぬ)は肩の部分に特徴的な違いがあります。狩衣はその名の通り、もともと狩りの時に着る服装ですから、動きやすい作りで、肩が空いています。貴人の服装は烏帽子に直衣姿の時もありますし、青い色の夏の直衣を着ていることもあります。

小道具も絵解きのヒントになります。籠を持つ女性(28巻 野分)、篝火(27巻篝火)、火焔太鼓(7巻 紅葉賀)などがあれば、どの場面かがすぐにわかります。

さて、ここで一見わかりやすい囲碁の場面について少し詳しく見ていきましょう。源氏物語では囲碁を打つ場面がいくつかあります。ですので囲碁だけではすぐにあの場面とはわかりません。中でも囲碁をする女性を男性が垣間見する場面は定型化され2種類あります。
「3巻 空蝉」では
空蝉と軒端の萩、立ち合い役の小君、垣間見しているのは光源氏、
「44巻 竹河」では
玉鬘の娘たちと立ち合い役の玉鬘の三男、垣間見しているのは蔵人の少将です。
どちらも女性二人が囲碁をしていて、立ち合いが男性、垣間見しているのが男性という構図です。
囲碁が登場する場面は他にもありますが、特にこの垣間見をしている構図は絵を読み解く面白さを楽しむことができます。立ち合い役が、小君なのか玉鬘の三男なのか、垣間見をしているのが光源氏なのか蔵人の少将なのかを推理します。この貝合わせには庭の前栽が描かれていませんから絵から季節がわかりませんので服装で見分けます。「空蝉」の季節は晩夏で「竹河」は春の出来事です。立ち合い役が侍童であること、垣間見ている公達の服装が夏の直衣であることから「空蝉」であることがわかります。源氏絵が描かれた蛤貝で貝覆いの遊びをするには、源氏物語のストーリーを記憶しておいて、さらに源氏絵を読み解く必要があります。貝覆い遊びで自分がとった蛤貝の源氏絵の場面をすぐに言い当てられたらかなりの源氏物語通と言えますね。
ポーズで読み解く
源氏絵には定型化された仕草があります。代表的なものの中から、2種類見てゆきましょう。「5巻 若紫」はわかりやすく知名度ナンバーワンの人気の場面です。逃げた雀を追って縁先に出ている紫の上を垣間見る光源氏、転がる籠、満開の桜と飛び去る雀は定型化され多くの絵師によって描かれてきました。

次に「4巻 夕顔」です。夕顔の花を載せた扇を差し出す童女とそれを受け取る随身、夕顔らしき女性、夕顔の咲く垣、光源氏の乗る車が描かれています。
私は小学生の頃、この二つの場面が大好きでした。いつか誰かが自分を見出してくれる、そんな男性に出会えるだろうかと思ったものです。現代では恋愛や婚活は女性も積極的に自分をアピールするのが普通ですが、平安時代の女性たちは家の中の深いところに居て、誰かの垣間見や突然の訪問でしか恋が叶わなかったのです。そう思うと、これらのシーンの特別感、ドラマティックな奇跡のような場面であることがわかってきます。

源氏絵が伝える平安時代の暮らし
源氏物語には平安時代の貴族の暮らしぶりが描かれているため日本の歴史文化を知る上で重要な資料だと言われています。源氏絵「22巻 玉鬘」より「衣配り(きぬくばり)」では光源氏と紫の上が六条院に暮らす夫人たちや姫君たちに新年の衣装を選びます。春の御方と呼ばれた紫の上には紫草の根を多く使った葡萄(えび)染めに紅梅の文様、夏の御殿に住む花散里には涼しげな浅縹(はなだ)色に洲浜の文様など年齢や容貌、性格に相応しい衣装が選ばれています。このように姫君ごとに細やかな設定が書かれており、紫式部は文学だけでなく、衣装にも高い知識と美的感覚を持っていたことがわかります。そして絵画に関しても高い知識を持っていました。「絵合」では、宮廷で対立する二つの勢力の対決の場面で梅壺女御方は古い伝統的な「竹取物語絵巻」を、一方の弘徽殿女御方は「いまめかし(当世風)」で目新しい「宇津保物語絵巻」を選んでいます。両者の絵画観の違いがよくわかるチョイスでこの場面の緊張感が伝わってきます。今ほど情報化社会でない平安時代に絵の流行りや鑑賞法を正確に把握していた紫式部の審美眼は素晴らしいものです。

貝合わせは源氏物語には出てこない
「絵合」は「物合わせ」という遊びで、「物合わせ」は平安時代にとても流行しました。参加者が左方右方に分かれて趣向を凝らし、持ち寄ったものを飾り立て、造り物や和歌の出来栄えを競います。「絵合」ではこのイベントのために当時の人気画家が描いた絵巻に人気書家が書をしたためた絵巻が用意されました。「貝合わせ」も物合わせの一種であり、左方右方のそれぞれが珍しい貝殻を集め、海の風景をジオラマのように造りそこに貝殻を散らし、その情景を歌に詠み、それぞれの出来栄えを競いました。蛤の貝殻のみを使う遊びではなく、さまざまな貝殻が集められ飾られました。源氏物語では当時流行の遊びとして「物合わせ」の遊びの一つである「絵合」の場面が描かれていますが「貝合わせ」は登場しません。蛤の貝殻の内側に源氏絵が描かれるようになったのは、貝覆いと貝桶が武家の婚礼道具となった室町時代以降とも言われています。王朝文化である源氏物語の世界が同じ王朝文化である貝覆いの遊びに使われる蛤の内側に描かれることで格式のある王朝風の道具類となり婚礼の威儀を整える役目を果たしたのでしょう。そして、江戸時代には大奥で働く女性たちや商家の令嬢が源氏絵の描かれた貝覆いのセットで遊び、王朝風の雰囲気を楽しんだのです。
紫式部が書いた『源氏物語』は現代も人々を魅了し続けます。物語の中で女性たちは自分らしさを見出し、幸せとは何かを追い求めています。何度読み返しても新しい発見がある源氏物語の世界がこれからも蛤とともに残っていくことを願っています。
『すぐわかる源氏物語の絵画』 田口榮一 監修 東京美術
『江戸の遊戯』貝合わせ・かるた・すごろく 並木誠士 青幻舎
『絵巻物の鑑賞基礎知識』編者 若杉準治 至文堂
『源氏物語絵巻 新版 徳川美術館蔵品抄2』徳川美術館 発行
『特別展 土佐派と住吉派 其のニ やまと絵の展開と流派の個性』
和泉市久保惣記記念美術館
『源氏物語画帖』鷲尾遍隆 監修 中野幸一 編集 勉誠出版
『土佐派源氏絵研究』和泉市久保惣記記念美術館