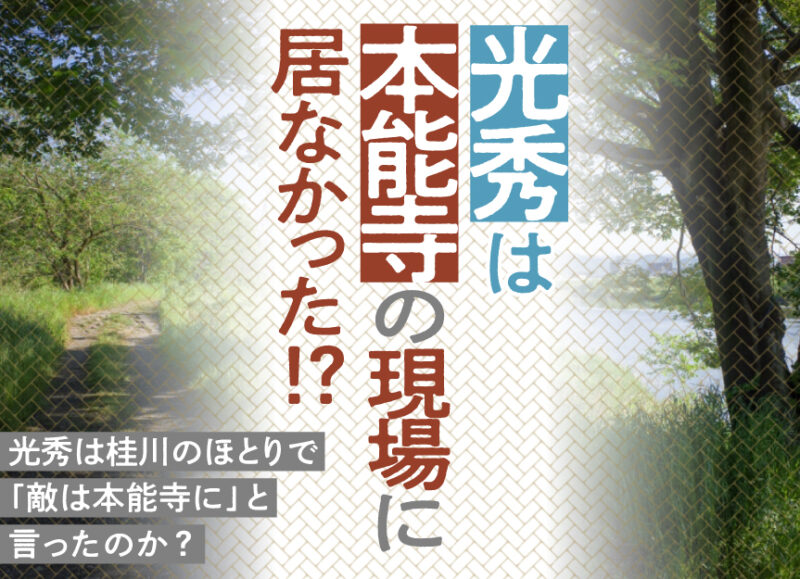後鳥羽院が見た霞

印象派の絵画のよう、とまで言ったら言い過ぎかもしれないのですが、筆者の心象風景だと思って許していただきたい…。隠岐島には今、対岸の島を隠すようにして霞(かすみ)が立っています。
遠島御百首 春の歌 一番
霞みゆく高嶺(たかね)を出(い)づる 朝日かげ
さすがに春の いろをみるかな
春。霞がかかっている高い山の頂きから昇ってくる朝日の光よ。
都を遠く離れた、
この隠岐の島にも、やはり、春が来たのだなあ。
後鳥羽院遠島百首の春の歌の一番目がこの歌なのですが、この歌にも霞が詠まれています。
和歌のことばで「霞」とは春の景物です。春になると、遠くのものがぼんやりかすんで見えることがよくありますよね。「霞」とは一体、どんなものかというと、『歌ことば歌枕大辞典』によれば、「春、大気中に浮遊した細かい水滴や塵のために、遠くのものがぼんやりと見える現象。」とあります。
万葉集の時代は、春にも秋にも、「かすみ(霞)」ともいいましたが、古今和歌集の時代になると、春に立つのを霞、秋に立つものが霧と呼ばれるようになりました。
『散歩が楽しくなる 空の手帳』によれば、「雪解けや植物の蒸散が活発になることで、空気中に水分量が増え、それが冷えて見えるようになるので景色がぼやけるのだ。」と説明されています。また、霞と呼ばれているものには、実は「黄砂」である場合も多かったようです。紫式部のあらわした『源氏物語』でも「朧月夜」が描かれていますが、このぼんやりとした美しい月夜も、黄砂が飛来して、夜空を曇らせていた可能性が高いようです。
黄砂の飛来は、3月から5月の間が特に多いそうです。
「あなじ」の風
平安時代、鎌倉時代にもすでに日本に飛来していた黄砂。一体、どこからやってくるのでしょうか?
実は、日本から遠く、遠く西へ離れたところにある、中国の内陸部にあるタクラマカン砂漠やゴビ砂漠から飛来しているのだそうです。筆者は恥ずかしながら知らなかったのですが、タクラマカン砂漠やゴビ砂漠では冬になると雪が降り、春になって雪解けがすすむと、上昇気流が強まり、低気圧が発達するため強い風が吹きやすくなって大量の砂が巻き上がり、偏西風にのって、日本まで飛来してくるのだそうです。
ゴビ砂漠で発生した黄砂は2、3日、タクラマカン砂漠だと5、6日で日本に到達するそうです。意外と、速いですよね。
隠岐島で後鳥羽院が、(ああ、霞だ、春だなあ。京の都と変わらないなあ)と感じている時、隠岐よりも大陸から遠い、京都の皆さんのところへは、まだ春が到達していない可能性がありますね。そう考えると、隠岐で空を見上げている後鳥羽院の方が、春を先取りしているかもしれません。
3月は、冬の間お休みしていた超高速船が隠岐航路に復帰し、本格的な観光シーズンに向かう季節で、冬の間静かだったこの島にも、本土から渡ってくる人が増えるようになります。そもそも隠岐航路がどうして冬は船の通う便が減るのかというと、冬の日本海がとても荒れるからです。
冬の間、12月、1月、2月は日本海上では古くから「あなじ」と呼ばれる西北の風の吹く季節です。「あなじ」は「あなし」ともいい、俳句の季語にもなっています。この間、海の荒れる日が多く、降りつけて視界が利かず小型の船が遭難することがあります。後鳥羽院の和歌にもこの風のことが詠まれています。
遠島御百首 雑の歌 九十三番
ことづてむ みやこまでもし さそはれば
あなしのかぜに まがふむらくも
西北の風(あなしのかぜ)に吹き乱されるむら雲が、もし都の方まで誘われて行くならば、
その雲に我が思いを都人にことづてたいものだ。
都を目指した渤海使
さて、この季節風に乗って、12月から2月の冬のもっとも海が時化る時期に、都を目指して海を渡ってきた人々がいます。それが、「渤海使(ぼっかいし)」です。
奈良から平安時代にかけて度々やってきた渤海使は、真冬の激しい季節風が吹く時期に、風を利用して百人以上の大型船でやってきたそうです。真冬の海を越える、高い航海技術を持っていたことになりますね。
「渤海(ぼっかい)」は、8~10世紀、中国東北地方を中心に、沿海州から朝鮮半島北部にわたり栄えた国。698年、ツングース系靺鞨 (まっかつ) 族の首長大祚栄が建国しました。唐の制度・文物を摂取し、仏教を保護していました。渤海から日本への使節の派遣は神亀4年(727)にはじまり、30数回来朝しています。926年に契丹に滅ぼされるまでの間、日本との国交がつづきました。
「こまうど」と光源氏
『源氏物語』桐壺巻に
光る君といふ名は、こまうどのめで聞こえて、つけ奉りける、
とぞ言ひ伝えたる、となむ。
源氏の君が、初めて「光る君」と名づけられた場面です。
源氏の君が、海外からの客人をもてなすために作られた「鴻臚館(こうろかん)」を訪れ、
そこで、「こまうど」の人相見に会うのですが、この「こまうど」にあたるのが、渤海使ではないかと考えられています。
「鴻臚館(こうろかん)」の「鴻臚」は、「おおきな雁が鳴く」という意味で、決まった季節に海を越えて自由に日本と異国を行き来する人々と雁のイメージが重なるからなのでしょうね。
「鴻臚館(こうろかん)」は、何年に一度やってくる渤海使をもてなすため、普段利用することのない施設だったために維持管理することが、財政的に大変な負担であったと思われており、最初は京都に東と西の2つの鴻臚館があったのですが承和(じょうわ)六年(839)には東鴻臚館は廃止され、それ以後西鴻臚館だけになったそうです。
『源氏物語』の物語の中では、源氏の君が訪れた鴻臚館でしたが、源氏物語の執筆された平安時代中期には、藤原道長(ふじわらみちなが)が法成寺(ほうじょうじ)の造営
に際し鴻臚館の礎石を一部抜き取ったと記録にあるとのことで、(『小右記』しょうゆうき)。
紫式部や藤原道長の活躍した時代にはかなり荒廃した状態だったようです。
「平家物語』に登場する鴻臚館
渤海の使節の帰国を餞別するため、鴻臚館で催された宴での詩があります。このときに詠まれた詩は、現在でも『和漢朗詠集』に収録されたものを読むことができます。
渤海使と、それをもてなす日本の詩人たちとの間の深い心の交流をうかがわせます。
『和漢朗詠集』は、平安時代中期に藤原公任がまとめた漢詩のアンソロジーで、のちの時代の平安貴族たちにも愛誦されました。
『和漢朗詠集・餞別』
於鴻臚館餞北客序 江相公
前途程遠
馳思於鴈山之暮雲
後會期遥
霑纓於鴻臚之曉涙
前途 程 遠し。 思ひを 鴈山の暮(ゆふべ)の雲に 馳す。
後會 期 遥かなり。 纓を 鴻臚の曉の涙に 霑す。
(渤海使であるわたしは)これから帰路につく長旅と、はるか北方にある故郷に思いを馳せる。
再会は遠い先であろう、それを思えば鴻臚館での別れの朝、涙がわが纓(冠のひも)を濡らす。
この詩は、延喜8年(908年)5月に、来朝していた渤海使一行が帰国するに当たって鴻臚館でもよおされた送別の宴で大江朝綱(江相公)の詠んだ詩です。
『平家物語』の「忠度の都落ち」で、都から落ちのびてゆく平忠度(たいらのただのり)も、この詩の一節を口ずさんでいます。。
平忠度(たいらのただのり)は、平清盛の弟で、文武両道に秀でた人でした。都から落ちのびていく途中いったん引き返し、自分の和歌の師である藤原俊成のもとを訪れました。鎧の隙間に忍ばせていた和歌を俊成に託し、「世の中が治まって、あなたが勅撰和歌集をえらぶ時が来たら、わたしの歌を入れてください」と言いました。
俊成は、平忠度に「かならず」と約束すると、忠度は、安心し、「これでもう、西海に沈んでもいい」と言い残し、再び都を落ちのびていったのでした。
のちに、俊成は勅撰和歌集『千載和歌集』をえらびますが、そこには約束どおり忠度の和歌がありました。ただ、平家一門が西海に沈み、源氏の世になっていたために作者の忠度の名は出せず、「詠み人しらず」として、忠度の和歌は後世まで残されたのでした。
『平家物語』平忠度/『千載和歌集』詠み人しらず
ささなみや志賀の都は荒れにしを昔ながらの山桜かな
志賀の都は荒れてしまったけれど、長等山の山桜だけは昔ながらに美しく咲いているなあ…。
故郷へ帰っていく渤海使とちがい、平忠度の都落ちは、西海に向かう死出の旅路でした。
ただ、渤海使の人々にも、平忠度にも、京の都でのかけがえのないあたたかい思い出があったことでしょう。
なお、渤海使の人々は日本海を航行中、隠岐にも風波を受けて寄港したり、嵐のために漂流してたどり着いたりしていたそうです。隠岐の人々が当時、異国の使節団を見てどんな感想を持ったのか、興味深いですね。
短歌(有泉 作):
はるばると浪路を越えてまた来てね浜の真砂を数えて待つよ
渤海使節を迎えた平安皇権
―『源氏物語』の一風景―
小山利彦
※ほかにもいろいろと参考文献があるので追加させていただきます。
参考文献追加分
『歌ことば歌枕大辞典』久保田 淳 馬場あき子 角川書店
『散歩が楽しくなる 空の手帳』 森田正光 東京書籍
『渤海使のもたらしたもの―古代の日本海交流(奈良平安篇)』小林道憲
(小林道憲〈生命の哲学〉コレクション9 ミネルヴァ書房 2017年 所収 『古代日本海文明交流圏』第七章)※kindleで購入できます
『渤海国の謎 知られざる東アジアの古代王国』上田 雄 講談社現代新書
『光源氏が愛した王朝ブランド品』河添 房江 角川選書
リーフレット京都 No.67(1994 年 8 月)「鴻臚館」
(財)京都市埋蔵文化財研究所・京都市考古資料館
『平家物語』池澤夏樹個人編集 日本文学全集09 古川日出男 河出書房新社