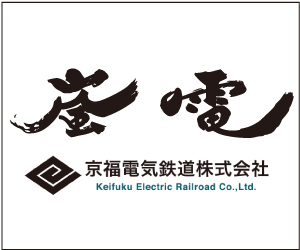お茶と竹の静かな空間 ~茶室の中の竹~(後編)僕は京都の銘竹問屋 Episode-20
矢竹
女竹と似ていますが、堅さや光沢もある竹。弓矢の矢の為に栽培された竹。
寒竹
ササの仲間の竹で、細く、節間の短い上品な竹。
黒竹(別名:紫竹)
国宝の茶室【如庵】の窓には、紫竹を詰め打ちした「有楽窓」が残されています。
錆竹(別名:胡麻竹)
立ち枯れにより、細かな粒が表面に出た竹。
亀甲竹
天然で亀の甲羅のような特殊な形状の竹。
しぼ竹
マダケの変種で、皺のある竹。稀にですが、壁止めに使われることもあります。
しみ竹
マダケの中で、120年の開花周期の中の一時期だけに茶色の斑(模様)が現れた竹。その模様の味わいが茶道具で好まれます。
茶室の醍醐味
茶室は、茶の湯を執り行うことに特化した特殊な建築物です。その醍醐味は“狭さ”と“暗さ”にあります。と講義で教わりました。
“暗さ”によって見えづらいからこそ研ぎ澄まされる感性が、“狭さ”によって空間の感覚が狂うことに拠り、茶室が無限の宇宙のように思えてくる錯覚の心地よさを経験した時に、醍醐味の意味が何となくわかったような気分になりました。
“狭い”場所が、住宅のような天井高になると、どこか細長い見た目になってしまいます。そこで、縦横のバランスを取る為に、天井高が全体に低くされているのが茶室の特徴の一つなのです。
天井を低くしたがための工夫として、掛込天井の形式にして勾配を付ける事で、さりげなく高さを稼ぐ等、独自の様式が創造されてきました。そして天井からの圧迫感を避ける為に、良い意味での脱力感が感じられる材料として、竹やヨシが用いられたのでしょう。
ギターを弾くのには手の脱力感が重要、と同じこと、かな?


関連する記事
 利田 淳司
利田 淳司
1967年京都市生まれ。
関西学院大学法学部卒。
1915年創業の銘竹問屋・(有)竹平商店4代目、代表取締役。
NHK「BEGIN JAPANOLOGY」「美の壺」などのメディアへの出演や「第8回世界竹会議」の開催組織委員・「日本人の忘れ物知恵会議」のパネラー等を務め、日本の銘竹の美を海外・国内に向け発信する活動を行っている。
|銘竹問屋四代目・ギタリスト|竹/明智藪/嵐山/祇園祭/ギター
アクセスランキング
人気のある記事ランキング