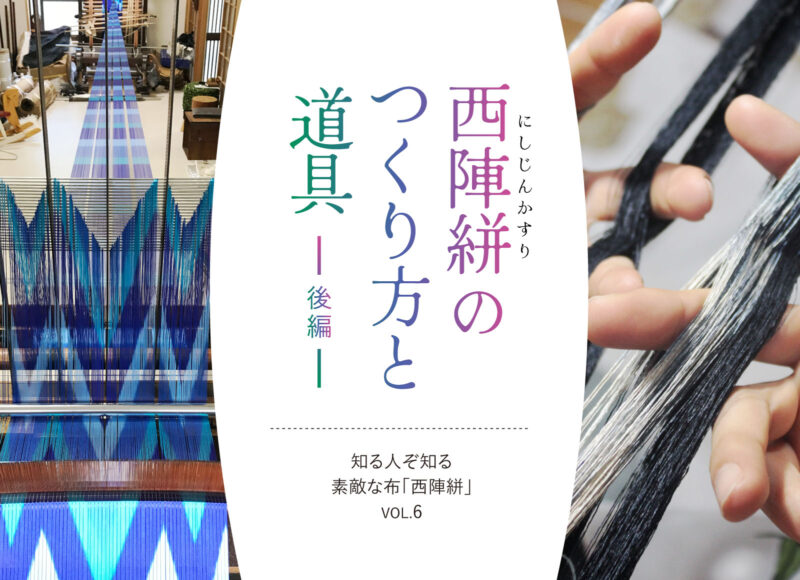夏の着物の定番柄「ナデシコ」
夏の着物の定番柄といえば秋の七草の一つ「撫子(ナデシコ)」です。着物や帯だけでなく、夏の帯揚げの柄をよく見ると撫子が散りばめられていたりします。撫子は華やかさの中にも優しげで、たおやか、という言葉がぴったりの花です。
大和撫子はカワラナデシコの別名で、花弁が細かく裂け、ふちが垂れ下がるように咲く、頼りなげで可憐な花です。日本種は大和撫子、外来種を唐撫子と呼びます。外来種といっても平安時代に渡来し、江戸時代に栽培が流行しました。着物や浴衣でよく見かける撫子は唐撫子のことが多いようです。唐撫子とは「石竹(セキチク)」のことで、セキチクはナデシコ科の多年草で中国原産、五弁花をつけます。花の色は、鮮やかな赤、淡い赤、赤紫、白など。四季咲きのセキチクは「常夏」と呼ばれます。
源氏物語26帖「常夏」では玉鬘への想いを諦めきれない光源氏の気持ちが書かれており、玉鬘のことを撫子となぞらえて愛しみました。
撫子は小さく可愛い、撫でたくなるような子というのが和名の由来とされており、漢名では瞿麦(くばく)、古くから日本でも薬草とされ、種子を瞿麦子と言い、漢方では利尿剤となります。歌に詠まれる際に撫子は「石竹」「瞿麦」と漢名で表記されています。

国立国会図書館デジタルコレクション(参照2023-07-31)
六条院の夏の町
源氏物語の六条院は、紫式部が作り出した寝殿造の大邸宅です。光源氏はこの邸宅に妻たちを一堂に集め、住まわせました。六条院の敷地は広く、春夏秋冬のそれぞれの季節をテーマにした町があり、季節にちなんだ木々や草花が植えられました。六条院の東北に位置する夏の町には花散里が住みましたが、玉鬘が物語に登場の後、玉鬘は夏の町の西の対に入ります。夏の町は山里の風情になっており呉竹や卯の花、薔薇などが植えられ、池の辺りには菖蒲が繁ります。撫子は2種類、唐撫子と大和撫子が植えられています。枕草子では「草の花は撫子、唐のはさらなり、大和もいとめでたし」とあります。唐撫子と大和撫子、私もこの二つの撫子を並べて、色とりどりに寄せ植えをして鑑賞してみたいです。さらに六条院の夏の町では、ただ並べて植えているだけでなく「撫子の花の周りを低く作った垣に添って植え」と書かれています。着物や帯の柄、日本画などの絵画では垣と花が描かれていることがありますが、垣と撫子が描かれていたら、源氏物語の「常夏」を思い浮かべてください。

盛夏の光源氏
それにしても暑い京都の夏、毎年、夏が来るたびに「平安時代の人々はどう過ごしていたんだろう」と思います。源氏物語の「常夏」では、池に張り出すように作られた釣殿で涼む光源氏の様子が書かれています。釣殿は風通しがよく、納涼のほか、月を眺めたり、釣りを楽しんだり、船遊びの際の船着場になったりする場所です。プールサイドのガゼボ(西洋風の東屋)のような感じでしょうか。鮎などの魚を目の前で調理させ、酒を飲み、氷水、水飯を食べます。源氏物語絵では画面に壺が描かれている絵が「常夏」ですから是非覚えていただければと思います。この壺には氷室の氷が入っています。現代でいうところの氷保管容器、アイスペールです。平安時代の人々も水辺で風にあたりながら冷たいもので喉を潤し納涼の宴を楽しんでいたのです。
光源氏を筆頭にさまざまな男性に好意を寄せられた、撫子のような姫君、玉鬘。彼女について少しご紹介しましょう。
玉鬘は源氏物語4帖に登場する夕顔の娘で母の死後は筑紫国(福岡県)で成長しました。夕顔はかつて光源氏の恋人でした。玉鬘は長谷寺参詣の旅の途中で、光源氏につながる女房と偶然に再会し、光源氏の娘として六条院に迎えられますが、実際には夕顔が光源氏と出会う前に関係があった頭中将との間の娘で、のちに本当の父親である頭中将と対面します。光源氏にとって、夕顔の面影を残す玉鬘は養女であり恋の対象でもありました。
玉鬘は源氏物語30帖「藤袴」で光源氏の息子の夕霧にも好意を持たれ、恋心を告白されます。夕霧は振られますので、とても切ない場面です。私が顧問を務めています「平安装束胡蝶の会」では夕霧が玉鬘に気持ちを伝えるこの場面を奉納劇として企画制作し、10月の藤袴祭にてご覧いただきます。

平安時代の「なでしこ合わせ」
さて平安時代の遊びといえば蹴鞠や碁、双六などが知られていますが、左方右方に分かれて和歌を読み合う「歌合わせ」、さらには何か、物をテーマに造形物を作り、その造ったものに和歌をつけその優劣を競う「物合わせ」は宮廷文化ならではの文芸的な遊びです。実は、貝合わせも元は「物合わせ」の一種で、左方右方に分かれて互いに珍しい貝を持ち寄り和歌をつけて、その出来栄えを競う遊びです。源氏物語17帖「絵合」も「物合わせ」の遊びの一種で、光源氏と頭中将が絵を持ち寄り競います。物は「洲浜」という台に置くのですが、単に置くだけでなく、洲浜台に歌のイメージに沿ったジオラマのような風景を造り、テーマとなる物を置き、その日の衣装もテーマに合わせたものを準備します。絵や貝の他にも歌、香、根、鶏、虫、草花、前栽などさまざまな物が題材となり盛大に行われました。
寛和2年(986年)に藤原道長の姉、藤原詮子主催で執り行われた「なでしこ合わせ」の際に作られた洲浜台の造形は細部に撫子鑑賞への並々ならぬ意気込みを感じます。
洲浜は左右2基ずつ、左第1の洲浜には小さな垣根に撫子2株を植え、鶴が立っている盆景で歌を3つつけたもの。左第2の洲浜には、瑠璃の壷に撫子の花を指し、虫かごが置いてあって歌をこちらも3つ添えています。洲浜の撫子は金銀などで製作された造り花。歌の内容は七夕、織姫牽牛や撫子の美しさを歌ったもの。
いずれも大変豪華な造り物を用意しての華やかな歌合です。撫子の美しさをたっぷり楽しむために趣向を凝らしていたのがよくわかります。歌が七夕の内容であるのはこの「なでしこ合わせ」が七夕の時期に開催されたためです。当時は今と違って撫子の季節が七夕の季節に重なっていました。一般的に七夕の日とされている7月7日は、2023年の新暦でいうと8月22日にあたります。

大和撫子は日本女性の美しさを表す
幼い頃は、夏の花といえば朝顔が好きでした。夏の浴衣の花柄といえば朝顔が良く、もしくはすっきりとした桔梗か、艶やかなものなら菊も外せません。私の家は呉服を商いにしていましたので、幼い頃より実際の花を見るより先に、着物の柄で花を知ることが多いのですが、撫子のことも実際の花をよく見る以前に着物の柄として見て知り、そして私の中では長い間、印象の薄い、選ばない花でした。花の魅力に気づくのには人それぞれのタイミングがあると思いますが、私の場合は歳を重ねるにつれ、夏の着物の撫子を毎年夏にみているうちに、奥ゆかしい雰囲気に心が惹かれるようになりました。唐撫子は着物の柄で見ると幼なげな印象に見えていたのですが、今では、ほっそりとした茎と葉に描かれている撫子が、凛として、現代の大人の女性にちょうど良い花柄だと思います。
撫子だけでなく秋の七草は夏の着物の柄でよく見かけますが、落ち着いたコーディネートを楽しむことのできる柄です。和花の良さは現代人には分かりにくいかもしれませんが、実はカーネーションはナデシコ科の花ですからなんとなく似ており撫子にも同じような華やかさがあります。
撫子は万葉集でも数多くの歌に詠まれ、恋の相手になぞらえられました。京都府の草花として制定されており、日本の女性の美しさを表す花とされていますから、夏に着物を着ることでその魅力を知ることが出来て本当によかったです。
図説
花と樹の事典 木村陽二郎監修 植物文化研究会編 柏書房
京都国立博物館所蔵 源氏物語画帖 土佐光吉画 解説 今西祐一郎編 勉誠社
合せもの (ものと人間の文化史) 増川 宏一著 法政大学出版局
源氏物語の花 青木登 けやき出版
すぐわかる源氏物語の絵画 田口榮一監修 東京美術
平安大事典 図解でわかる「源氏物語」の世界 倉田実編 朝日新聞出版
源氏物語解剖図鑑 佐藤晃子文 株式会社エクスナレッジ
絵で読む古典シリーズ源氏物語 学研
歌合集 日本古典文学大系 岩波書店
画像