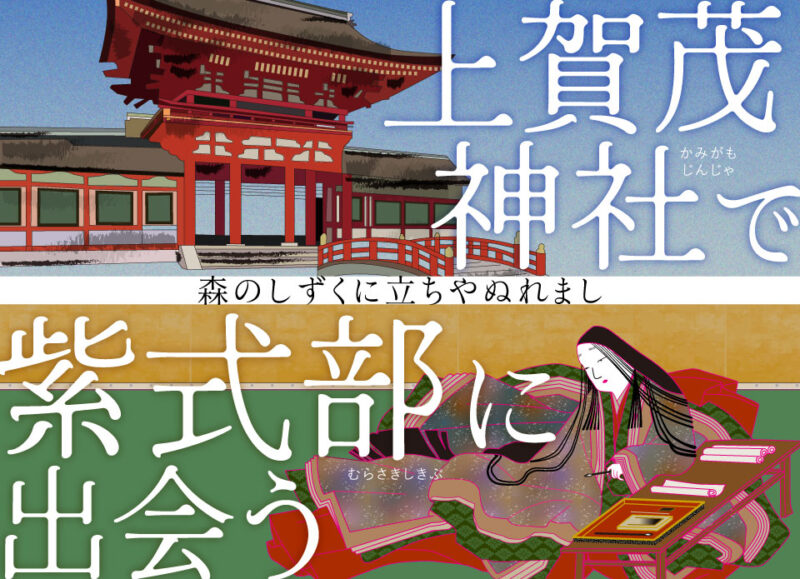「ペリーはある日突然やってきた」のではなかった!
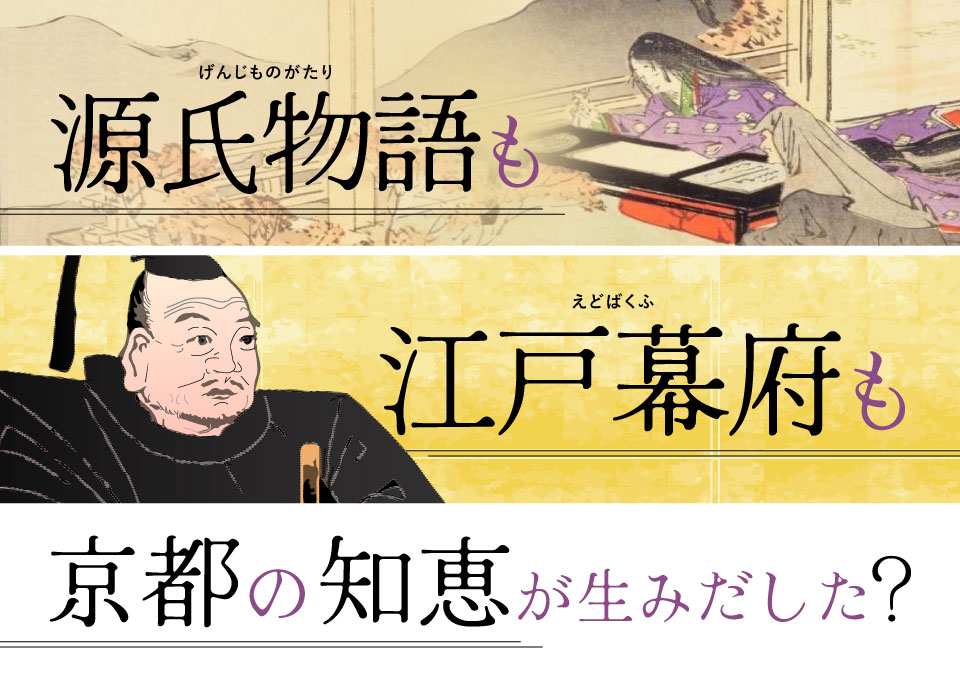
泰平の眠りを覚ます上喜撰 たった四杯で夜も寝られず
1853(嘉永6)年、ペリー提督率いる艦隊が浦賀に現れたときの、日本の混乱ぶりを表した狂歌です。私の記憶では小学校の教科書にも載っていたと思うので、多くの人がこの歌をご存じかと思います。日本の歴史は、ここから一気に近代化の扉をあけることになります。
さて、この「黒船現る!」の報は、市民レベルでは突然の出来事であったかもしれませんが、少なくとも時の政府、つまり江戸幕府的には十分に予測できたことであったはずです。なぜならペリー来航よりも、ずっとずっと前から日本の沿岸には外国船が通商を求めて姿を見せはじめていたからです。古くは1792(寛政4)年にロシアのラクスマンが根室に入港したことを皮切りに、ロシアやイギリス、アメリカの船が次々と日本の近海に現れ、通商を求めるようになります。
しかし、幕府の対応はことごとく「NO!」でした。この時代は「NOと言える日本」だったのですね。しかも、ただの「NO」ではなく、とんでもない「おもてなし」で追い返すのです。たとえば、日本人の漂流民をわざわざ連れてきてくれたアメリカの商船・モリソン号に、幕府は問答無用で大砲をぶっ放ちます。また、とてもジェントルな姿勢で開国を求めて来航したアメリカのビッドル提督は、通訳の手違いがあったとはいえ、なんと護衛の武士から鉄拳パンチを喰らうのです。外国の大使をぶん殴ったのですから、戦争になってもおかしくないのですが、なんとしても日本と通商したかった紳士・ビッドルは我慢してくれたのです。しかし、とうとう堪忍袋の緒が切れたアメリカは「日本とは普通に交渉してもダメだ」と悟り、力づくで開国させるべくイケイケのペリー提督の登場となったわけです。

[18–] 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2542901 (参照 2024-06-13)
思考停止が招いた倒幕
では、なぜ日本はここまで頑なに「NO」だったのか?いうまでもなく、江戸時代の日本は鎖国体制を敷いていたからです。外国の要求に対して「わが国の祖法により、異国との交渉はまかりならん!」の1点張りでした。ここでいう「祖法」とは徳川家康が定めた法律を意味します(※)。家康公は日光東照宮に祀られている「神」であり、その神様がお決めになったことを、みだりに変えるなどもってのほか。これが、当時の幕府の考え方でした。
※実際に鎖国を定めたのは3代将軍の徳川家光です。しかし、後の世になると「すべての法は大神君である家康公が定めた」という認識になっていたようです。
しかし、家康が幕府を開いてから200年以上の時が流れ、世界の情勢は大きく変化していました。産業革命とともに、欧米諸国はその市場をアジアに求めるようになります。また、大量の商品・武器を積める蒸気船の発明が、その動きに拍車を掛けました。これらの変化について、幕府が知らなかったわけではありません。オランダ国王からは「鎖国は時代遅れであり、速やかに開国することが日本のためだ」と警告を受けたのをはじめ、国内でも開国の重要性を説く人々が現れていました。しかし、幕府は耳を傾けることなく、それどころか彼らを処罰してしまうのです。
徳川家は国を閉ざすことを目的に鎖国をしたわけではありません。日本国の安全、幕府の安泰を考えての策だったはずです。ところが、いつの頃からか、本来の目的が置き去りにされ、「鎖国を守ること」自体が目的となってしまったのです。よくいう「手段の目的化」です。結果「ダメなものはダメ!」状態となります。こういう姿勢を「思考停止」といい、「なぜ、そうなのか?」「本当にそれでいいのか?」「このままの状態が続くとどうなるのか?」を一切考えず、感情や前例にとらわれ、思いこみだけで判断することが思考停止といえます。
さて、その後の日本はどうなったか?ペリーの強硬な姿勢に屈した幕府は、各国と不平等な条約を結ばされ、日本は50年もの間、苦しむことになります。なにより、幕府の安泰を願って施行されたはずの鎖国へのこだわりが、結果的に幕府を滅ぼす一因となったのです。皮肉なものですね。
ここまで長々と述べてきたのは日本史のおさらいのためではありません。思考停止、つまり「考えないこと」の恐ろしさを知ることで、思考、つまり「考えること」の大切さをお伝えしたかったからです。その「考えることを考える」にあたって、京都の歴史は大きな意味を持つと、私は考えています。それが本稿のテーマ「京都の知恵」です。
知識と知恵のちがいって?
知恵といえば、多くの人が混同しているのが「知識と知恵の違い」です。広辞苑によると、知識とは「ある事項について知っていること、またその内容」とあり、知恵とは「物事の理の悟り、適切に処理する能力」とあります。ここでいう「理」とは、「ものごとの筋道、道理」を指します。
「ちょっと何言ってるのか、わからない」とまでは言いませんが、小難しい表現ではありますよね。そこで、私なりにかみ砕いて例をあげてみることにします。たとえば「漢字を知っている」ことは知識、「その漢字を適切な場面で使いわけられる」のは知恵といえます。また、「車の運転の方法」は知識、「実際に車を安全に運転できること」は知恵となります。また、「おばあちゃんの知恵」はよく聞きますが、「おばあちゃんの知識」は、あまり馴染みがありません。これらから言えることは「知識とは単なる情報」であり、「その知識を実社会で活かせるようにしたものが知恵」というのが私の解釈です。もっとシンプルにいえば「知恵 = 知識+思考+経験」となります。
ものすごい勢いでデジタル化が進む現代では、知識の価値がどんどん下がっています。わからないことがあっても、ググれば百科事典以上の超絶膨大な量の情報が出てきますからね。そんな社会にあって問われるのは、「その知識をどう活かすか」の知恵であり思考力です。パソコンでいえばハードディスクなどの記憶装置にあたるのが知識、CPUなど処理能力にあたるのが知恵や思考力といえます。世の中で求められているのは、知識よりも思考から生まれた知恵だということです。
朝廷と幕府はどっちが偉いの?
そこで京都です。千年の都であった京都は、長らく日本の政治・文化の中心として栄えました。その後、政治の中心は東京が担うようになりますが、文化や学問の中心は依然として京都にあることは、文化庁の移転や「人口あたりの学生数 全国1位」であることからもうかがえます。
京都ではその長い歴史の中で、多くの知恵が蓄積されてきました。なかでも秀逸だと思うのが、天皇家と時の権力者との関係です。平安時代までは、天皇家すなわち朝廷が政権を担っていました。しかし、天皇そのものが実権を握っていたのは、ほんの一時に過ぎません。
この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の 欠けたる ことも なしと思へば
藤原道長が詠んだこの歌は、藤原一族の栄華の象徴といえます。道長の息子である藤原頼通は宇治に豪華な平等院鳳凰堂を建てます。このころが藤原氏の絶頂期です。いっぽうで天皇家はどうだったか?大河ドラマでは華やかな宮中が描かれることが多いですが、実は朝廷は困窮にあえいでいました。この国のトップが貧乏なのに、その部下に過ぎない藤原氏にはお金があり余っているのです(そのカラクリの秘密は「荘園」にあるのですが、その話をするととんでもなく長くなるので割愛します)。ようするに、藤原氏の財力はあくまで個人としてのものであり、政府である朝廷にはお金がないということです。

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/13183820 (参照 2024-06-13)
しかし、藤原氏は摂政あるいは関白として天皇の部下であり続けました。これが意味するところは「権力と権威の分離」です。藤原氏にあったのは権力です。権力と財力はほぼイコールですから、莫大な資産をもとに優雅に暮らせました。でも、その権力の背景にあったものは天皇の権威です。摂政も関白もざっくりいえば「天皇の代理」です。つまり「天皇あってこその権力」がその実態でした。
いっぽうの天皇は、その権威をもって藤原氏に権力を与え、自らの地位を保全します。この微妙かつ絶妙なバランス関係は、のちに幕府と朝廷の関係に受け継がれます。圧倒的な武力をもつ源氏や足利氏、徳川氏が、その気になれば朝廷を滅ぼすことは簡単でした。しかし、「はじめに天皇ありき」と考える思想が根づく日本で天皇の地位を脅かすと、大きな反動を生みだすことになります。本能寺の変で、明智光秀が謀反を起こしたのは、「織田信長が朝廷を亡きものにしようとするのを阻止するため」説が唱えられるのが、その好例です。そう考えると、朝廷を滅ぼさず幕府と並立させたのは、日本人のメンタリティにぴったりでした。
この幕府と朝廷の関係があったからこそ、明治維新という一大革命が「ほぼ無血」で成されたわけです。外国でこれだけの革命があれば、まちがいなく大戦争となり、おびただしい血が流れていたはずです。このように明治維新までの日本の政治は、天皇家と権力者とのパワーバランスで成り立っていました。この権威と権力の分離こそ「京都人の知恵」であり、その知恵が、(戦国時代を除いて)日本が平和に過ごせてきた源泉といえます。
京都の歴史は知恵の歴史
唐突で恐縮ですが、私たち日本人が最初に覚える文字は99%ひらがなですよね。「日本語は難しい」とは、外国人からよく聞く声です。漢字があり、ひらがな、カタカナがある。しかも同じ漢字でも読み方も意味も様ざま。くわえて敬語という概念は外国では珍しいそうです。難しい言語を巧みに使いこなすことで、日本人の思考力が培われた。私はそう考えます。日本人の識字率は昔から世界トップレベルの高さを誇っていますが、それはひらがなの発明があったからこそだと思います。ひらがなの誕生によって、ごく一部の人しか読めなかった文字が、広く普及することになります。そうして生まれたのが世界初ともいわれる長編小説『源氏物語』であることは有名ですよね。

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1305607 (参照 2024-06-13)
では、ひらがなはいつ、どこで発明されたものか?確かな文献があるわけではないそうですが、平安時代の宮中で使われ始めたことはほぼ間違いありません。そう考えると、ひらがなは京都で生まれた可能性が高いといえます。日本語そのものの起源はともかく、現代に連なる日本語は、平安時代の京都で成立したといっても差し支えないと思います。
ここまで述べてまいりましたように、京都の歴史は「知恵の歴史」ともいえます。急速に進むAI化や、人口減少にともなう市場縮小と労働人口の不足など、現在の日本は歴史上もっとも知恵が問われている時代だと思います。「歴史は繰りかえす」の格言にならい、京都の知恵によって令和の日本がより良い方向へと歩むことを願ってやみません。