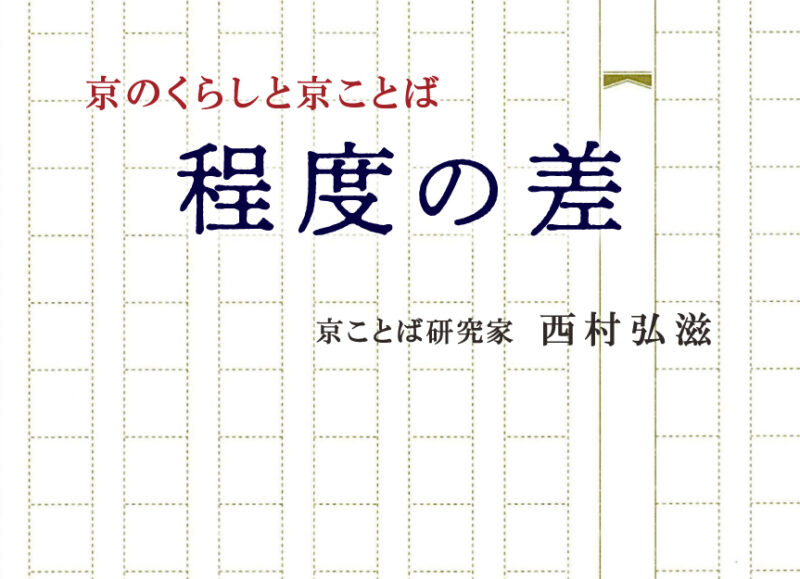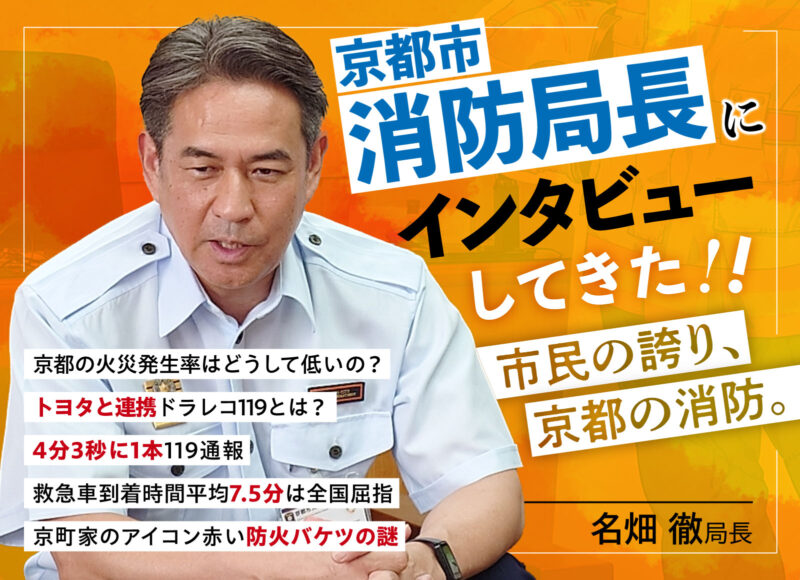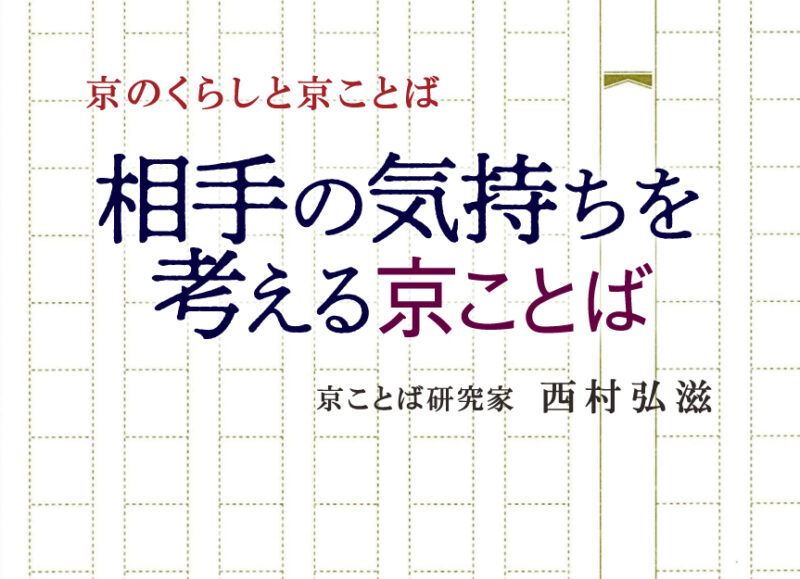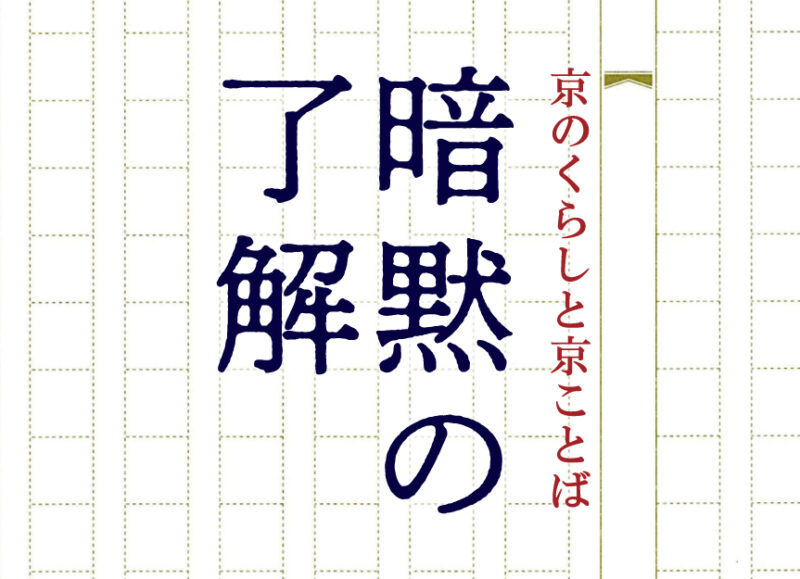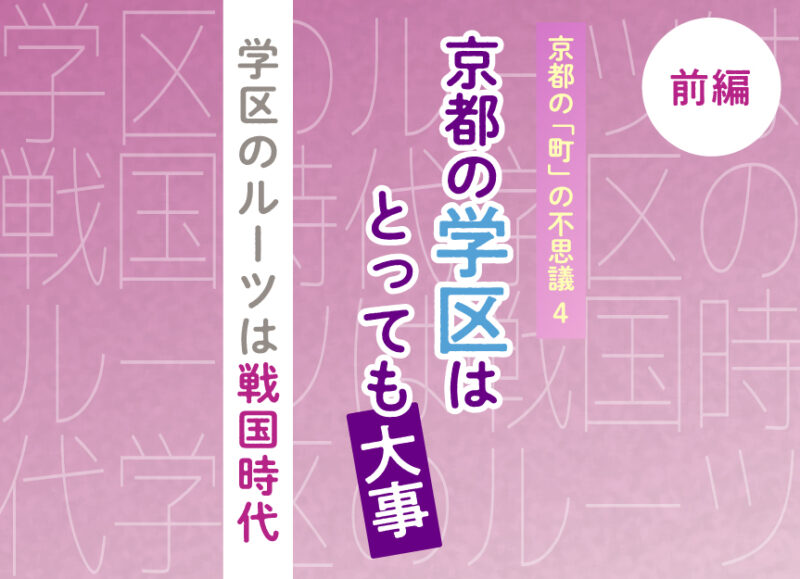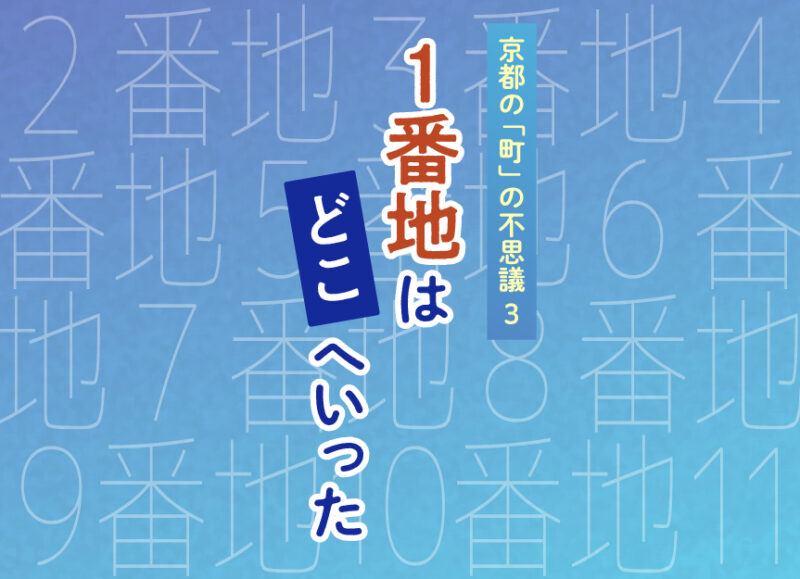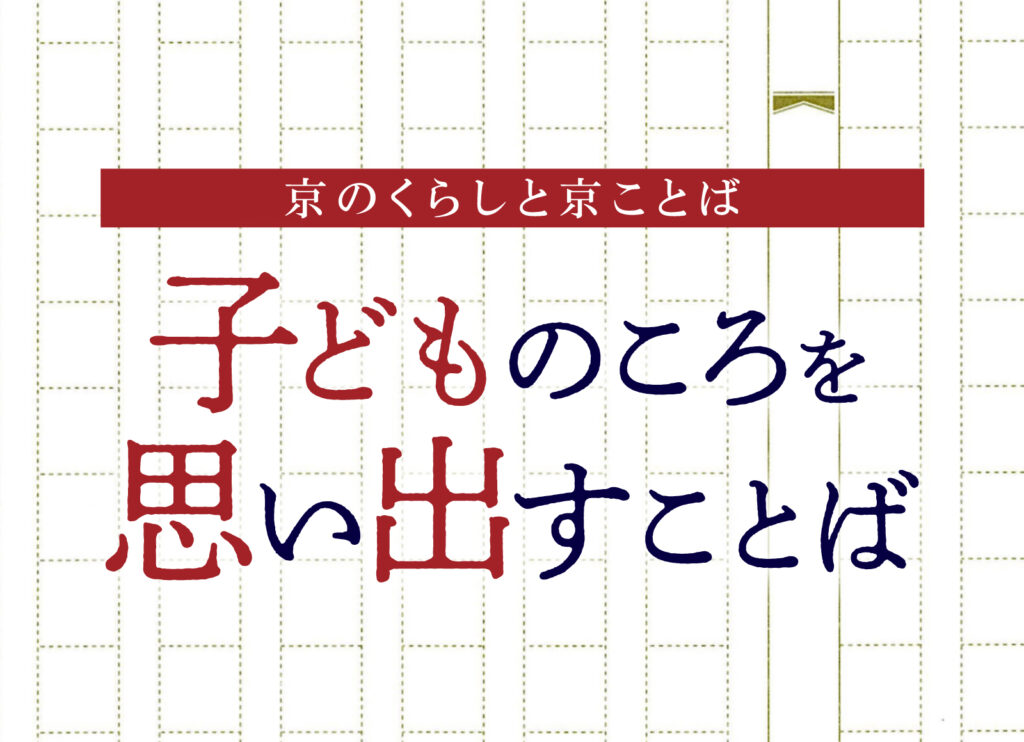
とんするえ から とんしとおみ
私は、西陣で生まれ育ったので、子どものころを思い出すのもやはり西陣での暮らしからである。以前、西陣の家のつくりを書いたことがあるが、「とおりにわ(通り庭)」といわれる家を貫く土間があり、台所の間の土間には「はしり」があった。「はしり」は、今で言う台所の流しである。仕事に追われる母親に代わって、「はしり」には祖母が立っていた。おばあちゃん子であった私は、よく祖母に甘えたが、ある日、台所の間から「はしり」に立つ祖母に、何を言ったかは忘れたが、駄々をこねる場面があった。いつも優しい祖母だが、その時は『「とんする」え』といって、私をたしなめた。「とんする」とは、台所の間の食事をするところから、「はしり」のある土間へすとんと落ちてけがをするということである。いわゆる子どもへの躾ことばである。事実だけを言ったのであるが、なかなかの迫力であった。それでも駄々が続くと、今度は「とんしとおみ」と一言。あとは知らん顔である。「とん」は、すとんと落ちる様子であり、「とんする」とは、「落ちてけがする」であり、「とんしとおみ」は「落ちてけがしたらどうなる……、痛いのがわかるやろ」という意味合いである。駄々をこねるのを怒るのではなく、そんなところで駄々をこねていたらけがをするよ、ということを「とん」という音を先に出して、事実を言うのである。感情は入れない。子どもにとって、これほど厳しいことばかけはないだろう。忙しい西陣の職人のことばである。
婆抜き それとも 婆つかみ
子どものころの遊びで、こんなことばも思い出す。トランプ遊びで、全部の札を配り、同じ数字のペアーになった手札を棄てる。そして、残りの手札を見ながら、順に隣の人の手札を1枚ずつ抜き、同じ数字がペアーになれば棄てる。その繰り返しで、最後までジョーカーを持っていた人を負けとするゲームである。ああ、あれかというと、そう婆抜きである。ジョーカーのことをどうして婆というかわからないが、小さいころ、「ばば(婆)つかみ」といっていたのを思い出した。婆抜きというと、ジョーカーを抜いたとき、ポーカーフェイスを装ったすまし顔をして、ジョーカーを取ったことを知らしめないように頑張り、他の人は、いわゆる相手の表情やしぐさなどちょっとした変化を見逃さぬようにしているのだ。しかし、「ばばつかみ」は、つかむということで、その行為には、幸運や金をつかむなどに現れるように、しっかりと握り持ったり、自分のものとするといったプラス的イメージが強く出て、ジョーカーなのにつかんだ喜びを隠せなくしてしまう。ゆえに、周りからは、見ていてジョーカーをつかんだ者を知ることとなる。この婆とてプラス思考にしてしまうのが、京都の持つ強みであるように思う。そこには、「ばばつかみ」をやっていて本当に楽しいというか、わいわいがやがやとして楽しんでいるという場面が浮かび上がってくる。一度婆抜きと言わず、「ばばつかみ」といってトランプ遊びをやってみてもらえればと思う。

子どもの頃の「すか」は
最近でも時々駄菓子屋を見つけることがある。今もそこは子どもがわいわいがやがやと集うところである。幼いころを思い出すが、その中に当てものがあった。いわゆる福引で、当たりくじに該当する景品をゲットするのである。子どもたちは、「あてもん」と言って、駄菓子屋では一番人気である。当然、当たりくじは少なく、多くは外れくじである。その外れくじを、京ことばでは「すか」と呼んだ。一等の景品を尻目に、「また『すか』やったわ」と残念がる子どもの声が駄菓子屋の門口まで響いている。大きくなっている息子もよく駄菓子屋に行っては「あてもん」をしていた。一等は大きなエビ、ゴム製の伊勢海老である。それが欲しくて、毎日偵察である。だんだんと景品がなくなってきて、まだ一等が残っている。今日当たるかななどと言いながら、出かける。息子の部屋にはその伊勢海老が残っている。小さなころを思い出す代物である。
大人になってからの「すか」は
さて、こんな子どもころの「すか」が大人になると、約束を守らずに、相手に失望をあたえてしまうことばとなる。約束をしておきながら、その場に、その時間に現れないことに対して、待つ側は、「すかくわされた」という。この「すかくわす」が京ことばである。他に「すか」の派生語として、「すかくう」は当てが外れるという意味で、「宝くじも当たらんと、『すかくう』たわ」などと使う。また、「すかたん」ということばは、「すか」に接尾語「たん」がついたことばで、「たん」は「ちゃん」と同じように「さん」から転じたもの、特に意味がないものともいえる。「すかたん」は、当て外れ、間違い、とんちんかんといった意味である。「すまんすまん、『すかたん』ばっかりして」、「おばあちゃん、このごろ『すかたん』ばっかり言わはるな」などと使う。また、「すかみたいな」は、頼りないという意味で、「お前の話、『すかみたいな』話やな」などと使う。
この「すか」は、前のいろいろな例からもわかるように、透かす、空かすからきたことばである。子ども頃はたわいもない意味合いだが、大人になると、人間関係を壊したり、その頼りなさのを表す意味合いとなる。