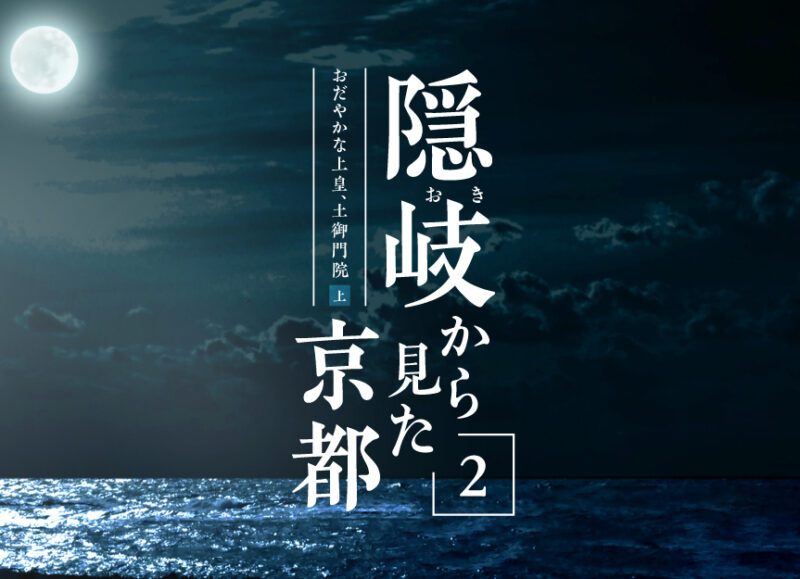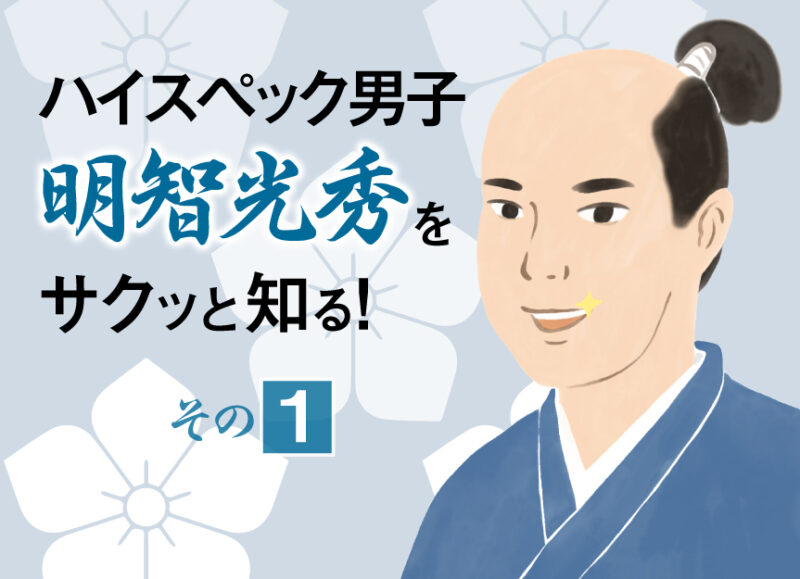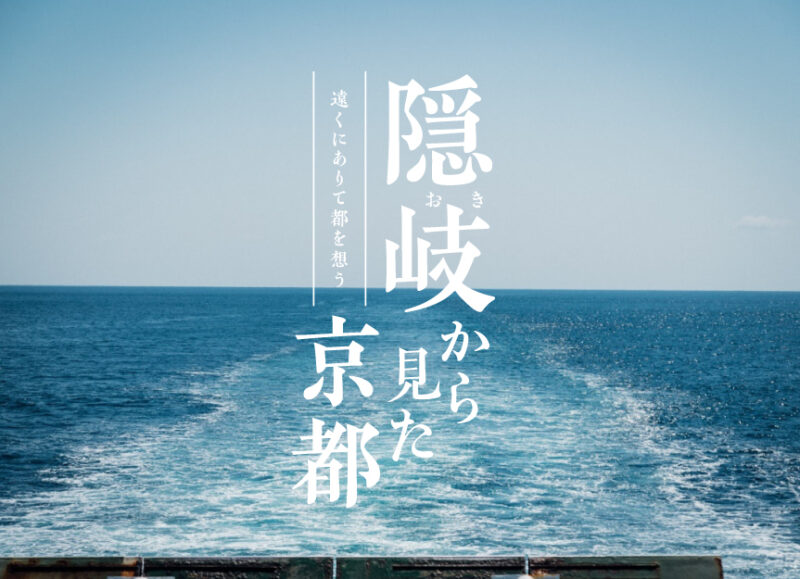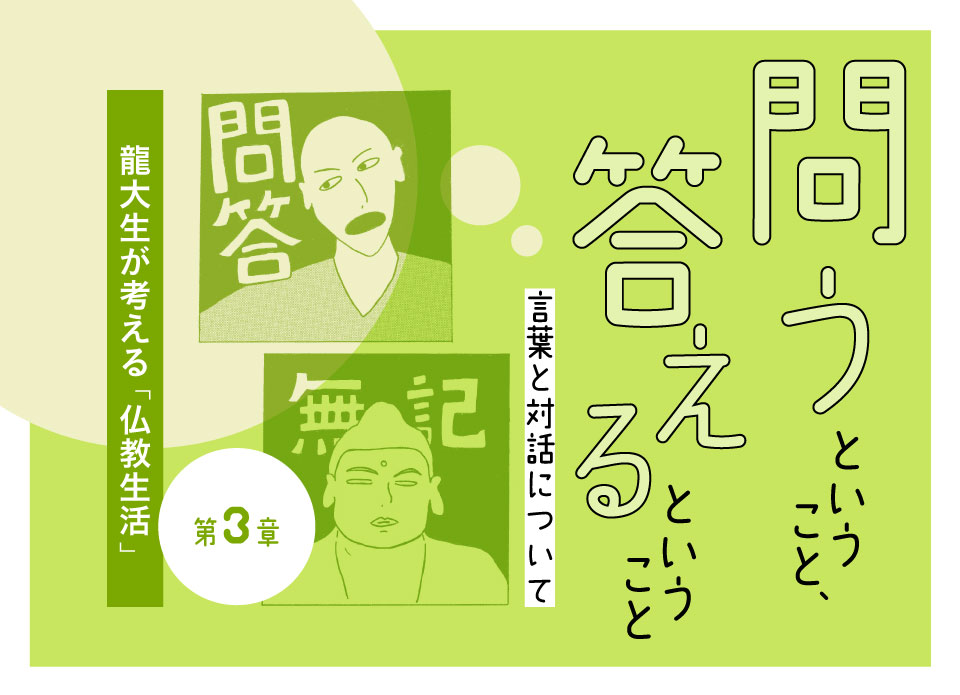
「対話」について
少し前にYahoo!ニュースで禅僧の南直哉(みなみじきさい)氏が取り上げられていました。そこで南氏は「言葉は対話の中のみで成り立つ」「SNSは対話にあらず」「言葉の強度を上げなければ実感がなくなっていく」といったことを述べておられました。私はなるほどと思い、改めて「対話」について考えるきっかけとなり、「言葉の強度」というフレーズに目を惹かれました。
また別の日、AIへの悩み相談がテレビで紹介されていました。もちろんAIは人の悩みに対して返答してくれるのですが、どこか違和感があります。私には、AIの回答は中身のないものに感じられました。
辞書で「対話」とひくと「直接向かい合って互いに話すこと」(日本国語大辞典)「向かい合ってさまざまな話題で話すこと」(角川類語新辞典)と出てきます。
これらに共通しているのは「向かい合うこと」です。
私は対話とは「人と人とがリアルで真正面から言葉を交わす熱のあるもの」なのだと考えています。
今回は「言葉と対話」を仏教から考えてみましょう。
取り上げるのは、「問答」と「無記(むき)」です。
「問答」または「禅問答」は、禅宗の中において行われるものです。師匠と弟子などが互いに質問を投げかけ、それに答えるといった形式です。同義語には「話頭(わとう)」「公案」があります。問答は『碧巌録(へきがんろく)』『伝灯録(でんとうろく)』『無門関(むもんかん)』などでさまざま記録されています。
そして「無記」は釈迦が弟子たちとの対話の中で出したひとつの答えです。ある質問に対して釈迦が「答えない」というエピソードがあり、私は「答えないという答え方」と理解しています。
では、この2つを挙げつつ、「言葉と対話」を考えていきます。
禅の「問答」にみる
「問答」のポイントは真の自分に気づくことです。師とのやり取りによってそれに気づく、つまり悟ることもあります。悟りを開く可能性があるせいか、問答というものは一般的な言葉のやり取りではありません。
一見すると「答えになっていない」「対話として成立しているのかな」と思ってしまうこともあります。中には言葉を使用せず、体で分からせるといった答え方もあります。例えば、師匠をいきなり張り倒す問答があります。
ここでは私が以前耳にしたときから印象に残っている問答をひとつ記させていただきます。私はこの問答を初めて知ったとき、「強い!」と思いました。
禅の立役者である達磨と梁武帝(りょうぶてい)との興味深い問答です。

梁武帝は502〜549年の間に在位していた仏教への信仰が篤い人物です。達磨が中国を訪れて2人が対面したとき、梁武帝は達磨に「私は仏教に親しみ信仰篤く過ごしてきた。寺もたくさん建てた。そんな私にはどのような徳があるだろうか」と尋ねました。それに対しての達磨の答えは「無功徳(むくどく)」というものでした。「功徳などない」と言っているのです。 これは何か見返りを求めて信仰しているうちは功徳などないという意味です。非常に秀逸で一刀両断、すっきりとした言葉ですね。
さらに武帝が達磨に「私の目の前にいるあなたは何なのだ」と問うと、達磨は「不識(知らない)」と答えました。この答えは「実体はない」という仏教の根本を説いています。つまり達磨はこの一連のやり取りの中で、強い言葉をもって仏法の正しさを提言しているのです。
けっきょく梁武帝は達磨の言うことを理解できず、達磨は武帝のもとを去りました。
その後、武帝は後悔したといいます。
外野から見る分には「そりゃそうだ」と思ってしまいますが、梁武帝の気持ちって共感しますよね。自分の行動に意味や目的を持ちたくなるのは当たり前のことです。
梁武帝はとても人間的なのです。そしてそれを正直な気持ちのまま正直な言葉にして達磨と対面したのです。
一方で、達磨には別に武帝の鼻をへし折ってやろうという意図はなかったでしょう。だって達磨ですから。ただ仏教としては武帝の思惑は計られるものではなかったわけです。それを強い言葉をもって達磨は武帝に知らせたと考えると、達磨のやさしさをうかがうことができます。武帝は知りたいことを正直に聞き、実にさばさばしていますが、達磨はしっかりと答えています。
あと、「直指人心(じきしにんしん)」という禅における重要な言葉を確認させてください。これは正面から人の心にアタックしてそれがどのようなものなのかを捉えるという意味です。
禅宗に僧籍を持つ教授いわく、直指人心は「お前は誰だと言っている」とのことです。誰に「お前は誰だ」と問われているのかと疑問を抱きましたが、禅は自分の外側に絶対的存在を置かないので、これは自分による自分への問答みたいなものですね。これは禅を志す者にとっては半永久的に問われていることでしょう。
「無記」、沈黙という答え
最後に少しになりますが、「無記」を考えます。
大昔、釈迦は説法をしました。その中で起こった「無記」というものがあります。先ほど述べたとおり、これは釈迦が特定の質問に対して「答えなかった」というものです。例えば、「世界の終末」「死後の世界」などについての質問にはこの無記を採用しています。
ネットで「無記」と検索をかけると「形而上学的な問いに答えなかった」と出てきます。

さて、私は今期に「仏教カウンセリング」という講義を受けています。以前、担当教授に「沈黙という対話は今もあり得るでしょうか」と質問しました。教授は「毒矢の例え」を示しながら、「あり得る」という答えを出しました。
「毒矢の例え」は釈迦の説法のひとつです。「誰かが毒の矢で射られていたらどうするか」と釈迦は問いました。そして「誰が矢を放ったのか・・・どんな弓だろう・・・どんな矢だろう・・・と考えるより前に苦しんでいる人の救済が先であろう」と言います。つまり、「目的とは異なるような議論は展開すべきでない」ということなのです。これが無記です。
後日、同講義で実際のカウンセリング中の映像を見ました。互いにまっとうに言葉を交わしています。しかし見ていると相談者もカウンセラーもどちらもしゃべらない数秒があるのです。おそらくその時間、カウンセラーは相談者の話を真剣に聞き、話すのを待っており、その間に余計なことは言わないのです。
私にはこの沈黙の空間は両者の対話を確かに構成しているように見えました。そして「目的とは関係ない余計な話はしない」という点で無記の特徴と重なるものを感じました。
つまり強い言葉を交えた対話の中において、沈黙には言葉を発さないゆえのそれ以上のパワーがあるのです。
問答には「言葉にする強さ」があります。もっとも問答においてのそれは常識にはおよそ通用せず、禅の世界で着地するものです。しかし、先ほど挙げた達磨と梁武帝の話のようにストレートな言葉が用いられる場合もあるのです。そして、無記には「言葉を超えた強さ」があります。
対話を構成するのは「言葉」です。芯のある言葉が対話を構成し、そこに「言葉にしない言葉」という情緒的な要素が含まれても対話は成り立つのです。
冒頭に挙げた南直哉氏の言葉をお借りすれば、「言葉の強度をあげること」が対話の要となるのではないでしょうか。
参照サイト
無理に夢や希望を持つ必要はない、正解なんて出なくていい―恐山の禅僧が語る、「人生の重荷」との向き合い方 8月17日配信(最終閲覧日11月13日)
https://news.yahoo.co.jp/articles/851d718af77f5107b09bad5d76a4ad5bf9e2eaa1