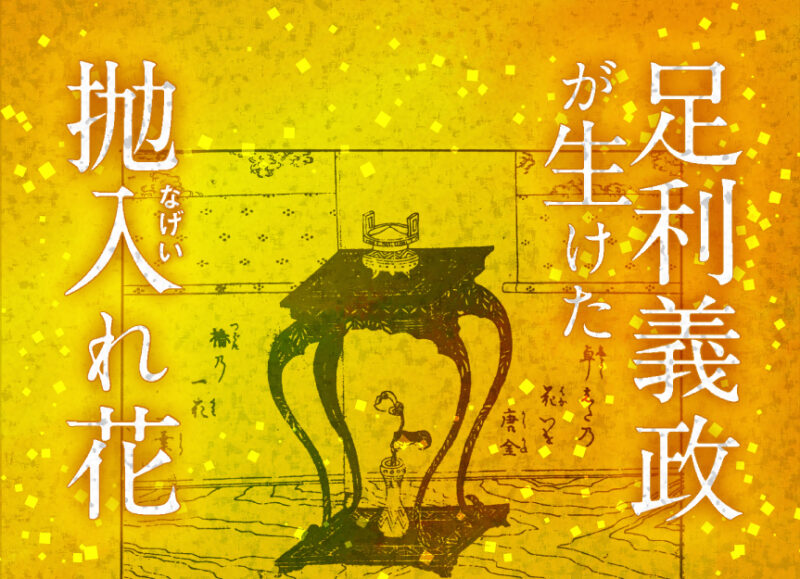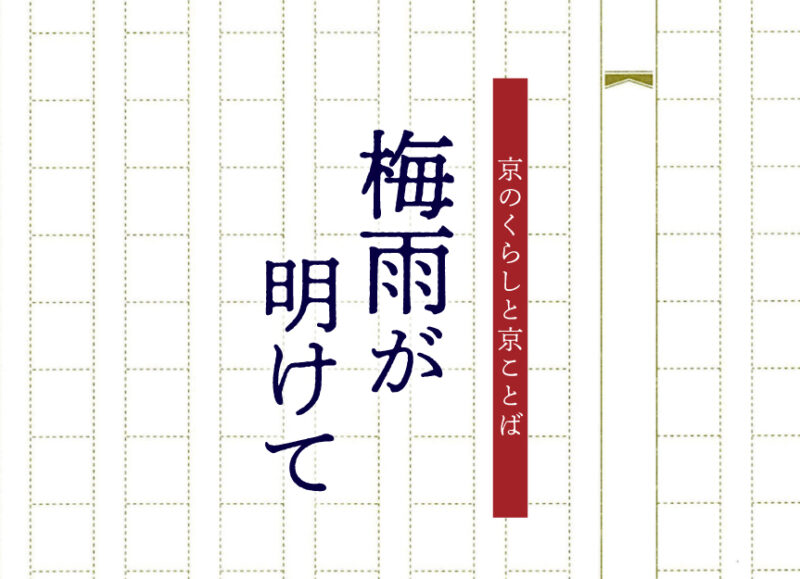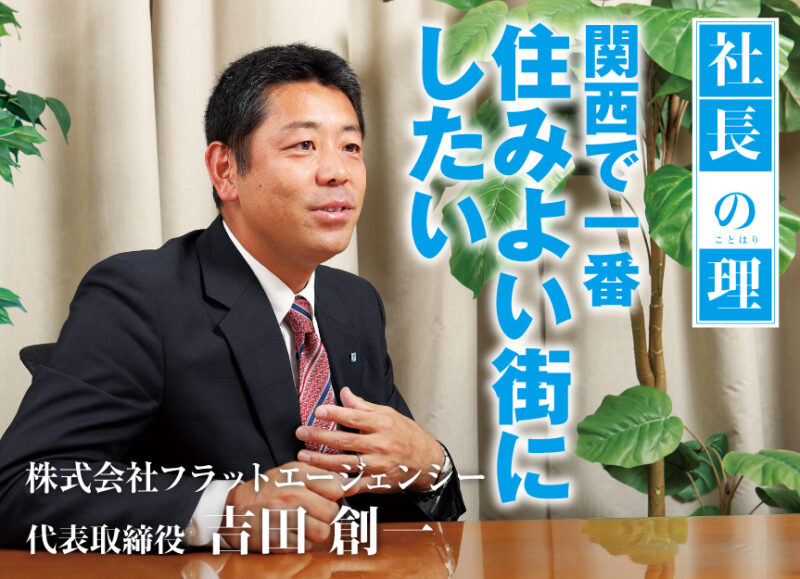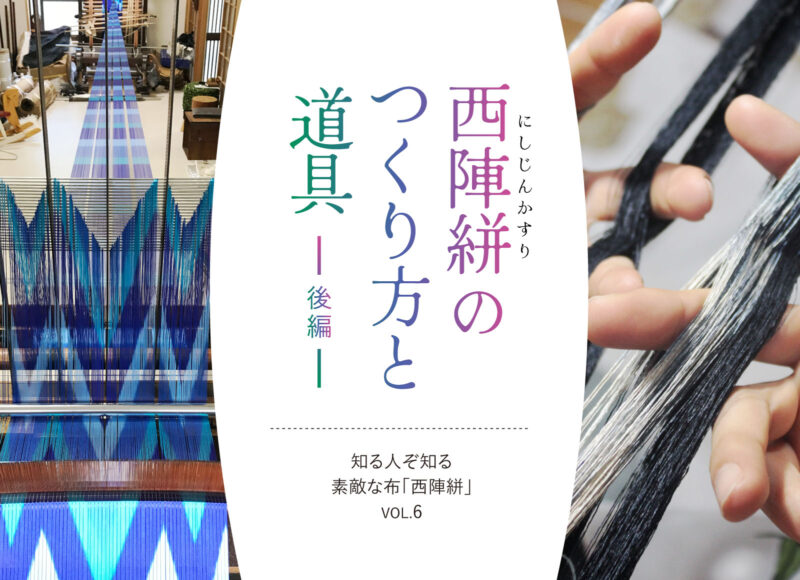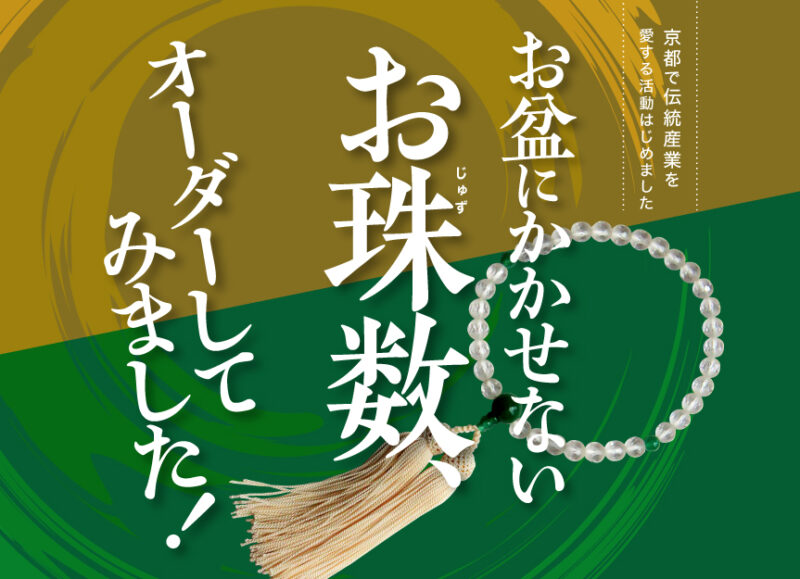京都府の中程に位置する南丹市園部町。戦国時代には明智光秀が丹波攻略後に統治しました。江戸期には小出家の治める園部藩が作られました。小さな藩であったが故に築城が許されず、築城許可が出たのは幕末。しかし、直後に起こった大政奉還により白紙となってしまいます。改めて明治政府に嘆願し、ようやく許され、園部城が完成したのが明治になってからというエピソードがあるまちです。(城の一部は京都府立園部高校内に残ります)
その園部の地に1995年に開校した学校があります。二本松学院 京都伝統工芸大学校Traditional Arts Super College of Kyoto、通称TASKと呼ばれています。(以下TASKと表記)
開校当時は京都伝統工芸専門校の名称で、それまで徒弟制度で受け継がれていた伝統的なものづくりを、カリキュラムを通じて伝統工芸品の制作を一から学べる学校として誕生しました。

(写真提供:京都伝統工芸大学校)
当初、総合と陶芸の2コースでしたが、30年を経て現在は、工芸コース、工芸クリエイターコース、文化財コースの3つのコース、陶芸、竹工芸、木工芸、木彫刻、仏像彫刻、金属工芸、漆工芸、蒔絵、和紙工芸、京手描友禅の10の専攻があります。
工芸品の職人やクリエイターを目指した学生が、日本全国からはもちろん、韓国、中国、タイやブータンなどのアジア圏や、さらにイギリスやフランスなどの欧州からも、世界中でも伝統的な工芸の技を学べるのは日本のこのTASKしかないと、留学して来ると伺いました。
また、学生の年齢もさまざま。高校卒業後、あるいは短大や大学卒業後に入学する学生はもちろん、社会人経験を積んでからや、会社を退職してからの60代、70代の学生もいらっしゃいます。
夫はTASK第1期の卒業生。それまで勤めていた古美術出版の会社をTASK開校のタイミングで退社し、家業の陶器商を継ぐにあたって、陶器の技術を学ぶために入学しました。
陶芸専攻 工藤良健教授にインタビュー
開校当初より講師を務められ、教務部長、校長を経て現在陶芸専攻教授である工藤良健教授。
30年間、学生を育み、羽ばたかせてこられました。そんな工藤教授のこれまでや、TASKの歴史や思い出を伺いました。教授は夫の恩師でもあります。

(於:京都伝統工芸大学校)
 三谷
三谷TASKの開校に至るまでのお話をお聞かせください。



伝産法(伝統的工芸品産業の振興に関する法律)が改訂され、後継者育成支援の法律ができました。財団法人京都伝統工芸産業支援センターが母体となり、全国で初めて伝統工芸の技術を専門に教育する、京都伝統工芸専門校(開校当時の名称)を開校することになりました。全国各地にも設立の検討がされましたが、開校まで至ったのはTASKだけでした。



開校当時は大変なご苦労があったのではないでしょうか?



1995年春の開校を目指し、準備も大詰めにさしかかった同年1月、阪神・淡路大震災が起こりました。その影響で、建材や什器などの納入が大幅に遅れることになりました。その後、私の担当する陶芸コースの授業には欠かせない、ロクロや窯の調達にも波及したことから、開校後すぐに電動ロクロを自宅の工房から学校まで運び入れ、1台の電動ロクロで学生たちに順番に指導をしながら、あとの学生には手回しロクロでの成形を指導していました。乾燥、削りの行程まで学校で行い、持ち帰って自宅の窯で焼成するなど、設備の揃わない現状を打開するため、工夫を重ねて指導したのを今でも覚えています。その後設備は充実し、数年後には陶芸を学ぶ学生が増え、新たに絵付けの授業も加わり、成形と絵付けの両方学べるのがTASKの陶芸専攻の特徴になりました。



先生がTASKで指導されることになったきっかけは何でしょうか?



TASK創立に向けての計画段階から関わられてきた、京都伝統産業青年会に私が個人会員として所属していたことと、学校から近い場所に工房を構えていたことからオファーをして頂きました。


(於:京都伝統工芸大学校)



先生はどのようにして陶芸の道へ進まれたのですか?



元々ものづくりに興味があり、中でも陶芸を学びたいと高校卒業後、京都府立高等陶工技術専門校に入校し、卒業後は京都市東山区泉涌寺地区の窯元へと就職しました。陶器の生産も盛んな時代で、一日に数百個の湯呑みや茶碗を作る毎日で、おかげで上達しました。割と早く数多く成形出来ると思っていましたが、雇主である大将の技術には叶いませんでした。とにかく、成形が早い。大将は昼間には配達や商談、窯詰めをこなしているにも関わらず、いつの間に作っているのか、なんと次の日の朝には私を上回る数を作っていました。今でもあのスピードには脱帽します。



東京での会社員経験もお持ちと聞きました。



窯元に数年勤めた後、友人の父に仕事を手伝って欲しいと請われて、東京で営業職をしていました。この時の経験は指導者としての今に生かされていると思います。10年ほど勤めた時、陶芸への思いが再熱し、京都へ戻り独立して開窯しました。そのタイミングでTASKでの講師の話が来ました。



たくさんの卒業生を送り出されて、ご活躍もお耳に入ってくるのでは?



ありがたいことに毎日のように卒業生の個展やグループ展などのDMが届いています。また、様々な工芸や美術業界の団体でも、卒業生の名前を聞くことが出来ます。先日も、中国から留学していた卒業生たちに招待頂き、景徳鎮へ行ってきました。海外でも活躍してくれている様子にうれしく思います。
前例のない教育機関で試行錯誤しながらも教えてこられた様子を伺いました。普段でも朗らかな先生ですが、卒業生の話をするとさらに目尻を下げて、心の底からうれしそうにお話しされる様子がとても印象的でした。
次回は実際の授業を見せていただいた様子を紹介させていただきます。
記事の内容について二本松学院 京都伝統工芸大学校の多大なるご協力を賜りました。