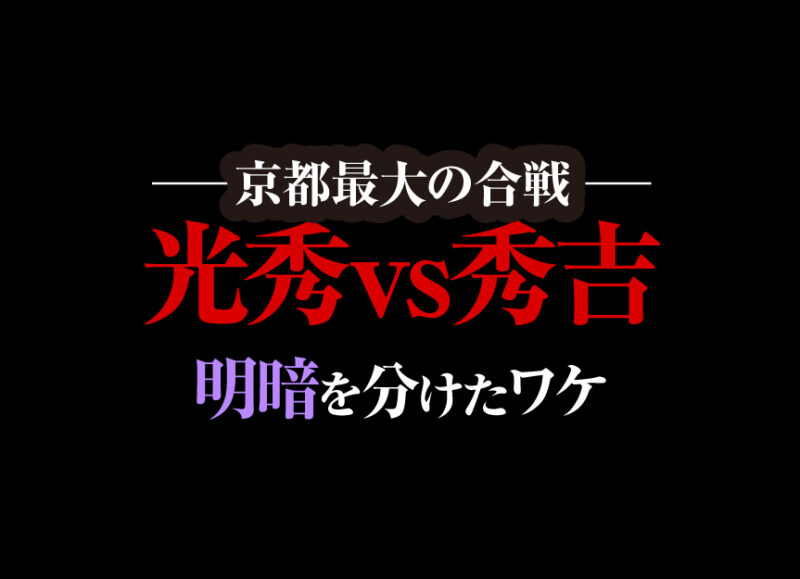後鳥羽院と大河ドラマ
毎週楽しみにしていた大河ドラマ『鎌倉殿の13人』が、令和4年の年の暮れに、ついに最終回を迎えてしまいました。後鳥羽院が隠岐に遷幸されることとなった承久の兵乱の描写は、最終回の放送の前半部分までで終わり、兵乱に破れた後鳥羽院は出家し僧形となって、進行方向とは逆を向いて座る状態での逆輿(さかごし)に乗せられ、隠岐へと護送されていきました。承久3年(1221)7月のことです。
この、承久の兵乱ですが、幕府軍とのおもな合戦のあった場所として名高いのが、宇治川です。宇治川は、京都の防衛上の重要な場所であり、寿永3(1184)年の正月、木曾義仲の軍と源義経の軍との間で行なわれた合戦のようすは、『平家物語』にも登場します。
平氏を打ち破って京に滞在していた源義仲と頼朝が対立し、頼朝に義仲追討を命ぜられた義経は、宇治川で義仲軍と対陣します。このとき、義仲軍に従軍していたのが、隠岐の島町釜にある佐々木家の遠祖といわれる、近江国の佐々木庄に地盤をもつ武将、佐々木四郎高綱でした。
高綱の兄である佐々木定綱は、のちに隠岐国の初代守護となっています。高綱の父は、『鎌倉殿の13人』で、「佐々木のじいさん」と呼ばれていた佐々木秀義です。秀義は、源頼朝の父である義朝に付き従って「平治の乱」で戦って敗れたために、本領である近江国の佐々木荘を離れ、坂東に移り住んでいました。高綱は、父・秀義の命で、兄の定綱らとともに頼朝の挙兵のさいに付き従うのですが、その功により秀義は本領である近江国佐々木荘を安堵され、近江に戻っていきました。
二頭の名馬
さて、『平家物語』の佐々木四郎高綱のお話に戻ります。高綱は、宇治川の合戦で梶原景時の嫡男である景季と、どちらがいちばんに宇治川を渡りきるかの先陣争いをし、勝っているのですが、このとき高綱が乗っていた馬が、頼朝から与えられた名馬「いけづき」でした。
佐々木高綱も、梶原景季も、ともに鎌倉で頼朝に仕えていました。頼朝は、「いけづき」「するすみ」の二頭の名馬を持っていました。梶原景季は、頼朝の名馬「いけづき」を所望するのですが、頼朝は「『いけづき』は、いざとなったら自分が戦に出る時に乗る馬だから、かわりに『するすみ』をやろう」と言って、「するすみ」を景季に与えます。
その後なぜか頼朝は、景季に与えなかった「いけづき」を佐々木高綱に与えてしまいます。戦場で、「いけづき」に乗っている高綱を見た景季はたいそう怒りながら高綱に話しかけますが、高綱は、景季が「いけづき」を欲しがっていたことを知っていたので、とっさに機転をきかせて、「これはいただいたものではなく、盗んできた馬です」と言うと、景季は納得し、一触即発の事態はまぬがれたのでした。
『平家物語』は、いろんな現代語訳が出版されていますが、古川日出男訳の『平家物語』(池澤夏樹個人編集 日本文学全集09/河出書房新社)は、ふだん古典文学作品を読み慣れていない方でも読みやすい文章なのではないかと思います。古川日出男訳の『平家物語』は、令和3年9月から令和4年3月までの間に放映されたアニメ『平家物語』の底本にもなっている本で、琵琶法師が語り伝えたものがたりの、語りのリズムと息遣いが感じられる文章です。
わたしは「いけづき」には少し思い入れがあります。実は隠岐の西ノ島には、「メド(馬道)岩」と呼ばれる大きな穴のあいた岩があるのですが、この大岩には言い伝えがあり、なぜか、宇治川合戦の名馬「池月(いけづき)」が、大岩の絶壁を蹴り飛ばしたことで穴ができたということになっているのです。興味深いですよね。
この「いけづき」という馬は、どんな馬だったのでしょう。
『平家物語』の「宇治川先陣」の一文を見てみましょう。
いけずきと思(おぼ)しい馬が、出てきた。
視界に入った。
その一頭は、金覆輪(きんぷくりん)の鞍を置いている。小総(こぶさ)の鞦(しりがい)をかけている。勇み立ち、口から白い泡を吹いている。幾人もの下人がついているのだが手綱で馭(ぎょ)することができず、躍りあがっている。躍りあがっている。まさに躍動して出てきた。
「生(いけ)ずきの沙汰 日本一の名馬」
佐々木四郎の賜ったお馬は黒栗毛で、たいそう肥えている。逞しい。そして馬であろうと人であろうと、側にいるものには見境いなく噛みついた。だから、生きているものに食いつく、生食(いけずき)と名づけられた。その背丈、四尺八寸の馬だということだった。
「宇治川先陣 先駆けの名誉」
なんという荒々しい馬でしょう。
宇治の橋姫
義経の軍が源義仲軍を破った宇治川の合戦から37年後の承久3年(1221)、今度は北条泰時の率いる幕府軍が朝廷軍を破り、翌日、入京。朝廷軍の敗北となりました。
さて、このような、激しい戦いがおこなわれた宇治川。ここには宇治橋という名高い橋があります。宇治川を挟んでの合戦のさいには、橋板を引き落として川を渡れないようにする作戦がおこなわれたそうで、『承久記』には、橋板を引き落とした橋の上で、曲芸のような戦い方をする朝廷軍の奈良法師・土護覚心と円音の活躍が描かれています。
そんな、男たちの熱い戦いのおこなわれた橋を守る神として祀られている姫がいます。彼女は「橋姫」。宇治橋西詰の大鳥居のそばにある『橋姫神社』の祭神で、境内には、おなじく水の神である住吉神社も並んでいます。
宇治の『橋姫神社』に祀られている「橋姫」は、「瀬織津姫(せおりつひめ)」という、神道の祭祀に用いられる祝詞の一つである「大祓詞(おおはらえのことば)」に登場する神様の名で呼ばれています。瀬織津姫を祀るお宮は全国に何社かあり、中でも有名なのは三重県伊勢市にある伊勢神宮です。

(イメージ図)
また、「橋姫」は、源氏物語の第四十五帖の巻名にもなっています。紫式部の著した源氏物語は、全部で五十四帖にもなる長い物語ですが、「橋姫」の巻は、その長編の中の最後の十巻、「宇治十帖」のなかの最初の巻にあたり、光源氏の死後、おもに宇治の地を舞台として展開されてゆく物語です。
『源氏物語』の現代語訳でおすすめなのが、角田光代訳です。(『源氏物語 下』池澤夏樹個人編集 日本文学全集06/河出書房新社)
「さむしろに衣かたしき今宵(こよひ)もや我を待つらむ宇治(うぢ)の橋姫(古今集/むしろに自分ひとりの衣を敷いて、今宵も私を待っているのだろうか、宇治の橋姫は)を思い出した中将は、硯を持ってこさせて、大君(おおいぎみ)に文を送る。
「橋姫の心をくみて高瀬さす棹のしづくに袖ぞ濡れぬる(宇治の橋姫の気持ちを想像し、浅瀬をゆく舟の棹の雫―涙に、袖を濡らしています)」
「橋姫」の冒頭の場面です。
後鳥羽院の時代、宇治は貴族の別荘地となっており、元久元年(1204)7月11日から16日にかけて、後鳥羽院も宇治御幸(うじごこう)を行った記録もあります。後鳥羽院が隠岐に遷幸されてから詠んだ歌の中にも、「宇治の橋姫」は登場します。
219鹿の音に片敷く袖やしをるらん今宵も更けぬ宇治の橋姫
(牡鹿が妻を求めて鳴く声を聞いて、宇治の橋姫は、衣の片方を敷いて独り寝をして、悲しみの涙で袖がぐっしょり濡れていることであろうか。待っていても人は訪ねて来ず、今夜もまた更けてしまったことだ。)
「片敷く袖」は、衣の片方の袖を敷いて独り寝をすること。男女がともに寝る時は、衣の袖を片方ずつ敷いて重ねてねむるのだが、衣を重ねる相手がいない=独り寝をしている、という意味になる。
263晴間なき袖の時雨を片敷きて幾夜寝ぬらん宇治の橋姫
(晴間なく時雨の降る頃、心晴れることなく、絶え間なく流れる涙に濡れた衣の袖の片方を敷いて宇治の橋姫は幾晩寝て待ったであろうか。)
こちらも、橋姫の「片敷く袖」について詠んでいるのだが、この歌の橋姫は、自分の衣の袖だけを敷いて独り寝をしている状態で、その上、敷かれた袖はやむことのない時雨(涙)で濡れている状態だという。そんな状態が幾晩もつづいている。
「詠御百首和歌 秋」
そんなに待たせる男性とはもう、別れてしまえばよいと思うのですが。
ところで、「橋姫」は、後世になると、また違った伝承が生れたようです。
「鉄輪井(かなわのい)」という井戸を、皆さんはご存じでしょうか?京都市下京区にある命婦稲荷神社(みょうぶいなりじんじゃ)の境内にある井戸で、「縁切井戸」と呼ばれているそうです。この井戸の水を、縁を切りたい人に飲ませると、縁が切れるのだそうです。今は、井戸の水は枯れてしまっているので、水を汲むことは出来ないのですが…。
この「鉄輪井(かなわのい)」の伝説にも、橋姫が登場します。ここでの橋姫は、自分を捨てて後妻を娶った男を憎み、貴船神社に丑の刻参りに通います。「鉄輪(かなわ)」を頭に被って。貴船神社の神の神託のとおりに鬼女となった橋姫は、夫を呪い殺そうとしますが、夫が依頼した安倍晴明の祈祷の力に負け、姿を消します。
「鉄輪井」
今回は、なんだかとりとめのない話になってしまいました。
それでは、今回は、この辺で。
短歌(有泉 作):
奔流をものともせずに馬を駆るあれは令和の宇治の橋姫