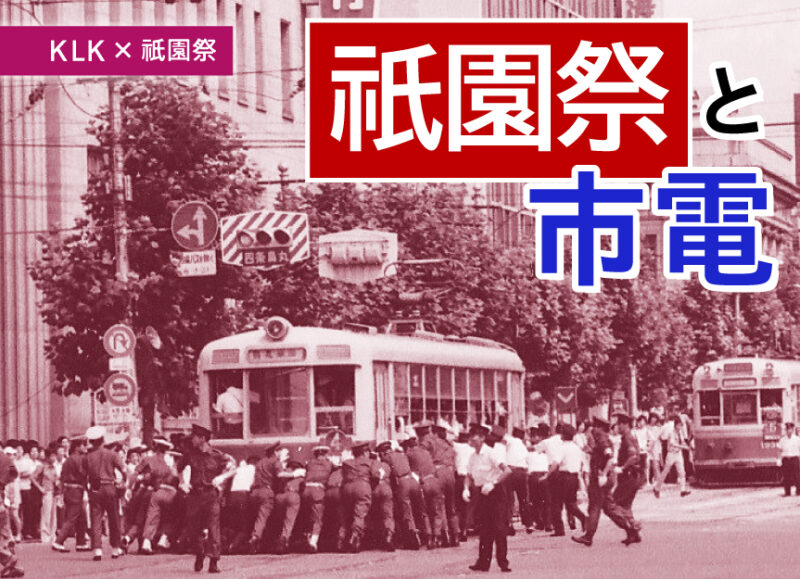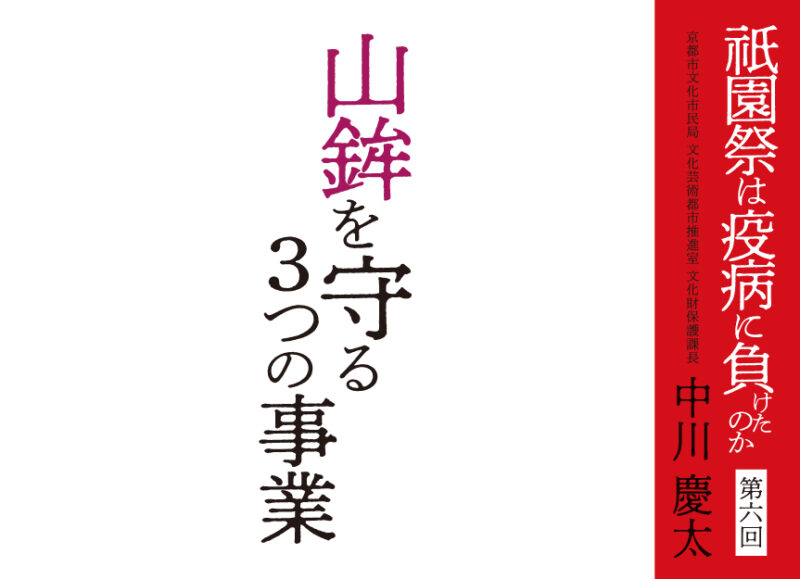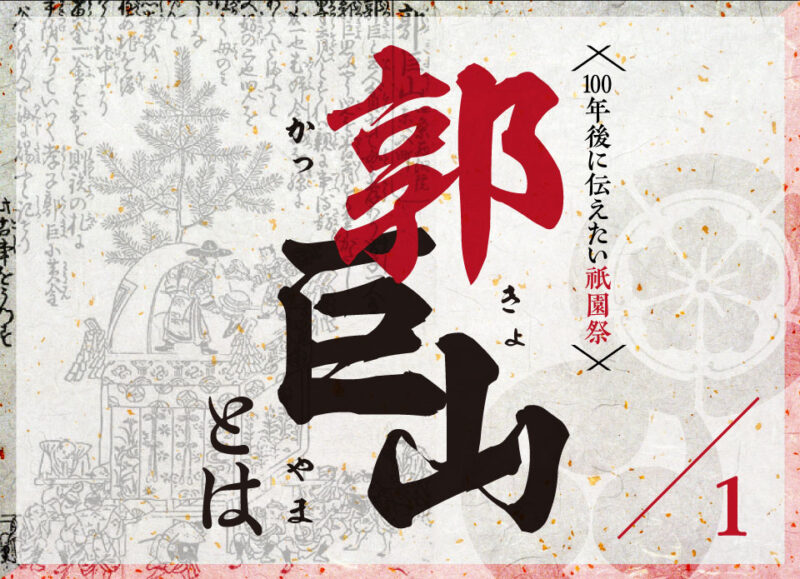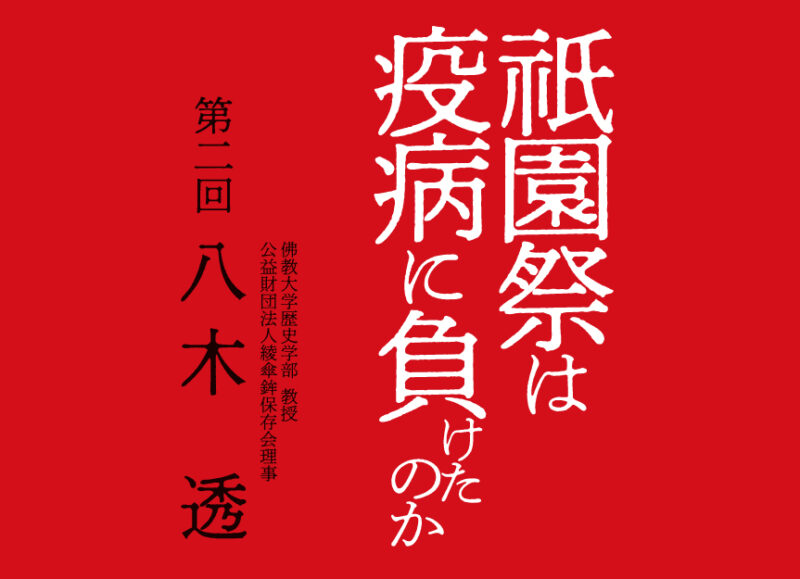2021年の祇園祭が始まっています。
私は、昨年に続いて、綾傘鉾保存会の様子を拝見、撮影しています。
6月27日に、粽づくり。

7月1日に、吉符入の神事。

ここまで、昨年と同じく、つつがなく執り行われました。

しかし、今年は、昨年にはなかった行事が加わりました。
7月3日、八坂神社舞殿にて、綾傘鉾 棒振り囃子の特別奉納が実施されたのです。



続く7月4日、中京区壬生にある元祇園梛神社でも、同じく棒振り囃子を奉納。



棒振り囃子とは、災厄を払い都大路を清めるとされる、音楽と踊りの呼び物です。
祇園祭の傘鉾 綾傘鉾独特のもので、三種の要素から成り立ちます。
「赤熊(しゃぐま)」と呼ばれるかぶり面をつけた踊り手(棒振り)が、手に棒を持ち、軽快かつ見事に振り回します。
そばには、鬼面を付けた太鼓とバチをもった「巡柱(じんちゅう)」と呼ばれる二人の男性がたち、一人が太鼓を支え、一人がバチで太鼓を叩き、踊りながら演奏します。


後ろでは、囃子方が鉦・笛で祇園囃子を奏でます。
これは山鉾巡行に伴って演じられるものですが、宵山や他の神事などで、棒振り囃子だけを独立して実施することもあります。

ふたつの神社で、連日、棒振り囃子が執り行われたのですが、じつはこの二箇所で実施されたのは、意図があってのことでした。
中京区にある元祇園梛神社に、このような話が伝わっています。
「貞観時代、京都に疫病が流行したため、牛頭天王(神仏分離令後はスサノヲノミコト)を、播磨国から祇園八坂の地に勧請、鎮疫祭を行った。この途上、梛の森にて神輿を休め、分霊をこの地に置いた。これがのちの梛神社である。またここから東へ遷御する際に、地元の住民が風流傘(ふりゅうがさ)を立て、鉾を振って楽を囃しながら神輿を八坂へ送ったとされ、これが祇園会の傘鉾の起源であると言われる。梛神社のことを元祇園と呼ぶのは、この経緯に由来する」

この話に従えば、八坂神社と梛神社は、祭神が同じだけではなく、ほぼ同じ時期に成立しており、風流傘を立て、棒(鉾)を振り、楽を囃す行為は、ふたつの神社をつなぐ仲立ち、とも言えるのです。
今年、八坂神社と、元祇園梛神社で、続けて棒振り囃子が奉納されたのは、この逸話を意識してのことでした。
綾傘鉾について、説明いたします。
祇園祭 山鉾の中に二つしか無い、「傘鉾」と呼ばれるものです。(綾傘鉾と四条傘鉾)
柄のついた綾傘を手に捧げ持って、疫病鎮圧を念じ、音楽や舞踊、棒振りの芸を行う、平安期からの流れを汲む歴史ある形態です。現在は綾傘の下に台と車輪をつけて曳行しています。

このように美しく趣向を凝らした作り物から始まり、踊りなどを加えた芸能を風流(ふりゅう)と呼びます。祭礼にともなう飾り物や傘、山、鉾も風流に含まれます。
今宮やすらい祭にも風流傘が出て、音楽と舞踊が付き従い、疫病鎮めを行いますが、これも風流です。
綾傘鉾とやすらい祭の源流は同じで、兄弟や従兄弟のような関係にあたります。
綾傘鉾は、江戸時代末期、1864年、元治の兵乱で焼失してしまいます。
途中、何度か復興しようという動きがあったのですが、完全に復帰出来たのは昭和54年(1979)のこと。
百年超が過ぎていました。
踊りやお囃子を取り戻すのは、大変なことです。
しかし、綾傘鉾の復興には、幸運なことがありました。
兵火による断絶の時まで協力していた人たちが、棒振り、太鼓、祇園囃子の伝統を継承し続けていたのです。

江戸時代の記録には、「古例、赤熊の棒振隠太鼓はやし方は壬生村より出る」とあります。(祇園御霊会細記)
壬生は元祇園梛神社のある地域。
壬生六斎念仏、という民俗芸能(芸能六斎)があります。
この人たちが、綾傘鉾に参加していたのですが、壬生六斎の演目の中にも、やはり、棒振り囃子や祇園囃子がありました。
したがって、綾傘鉾の活動が中断しても、壬生の地域には棒振り囃子が維持されていました。
ただ、両者の棒振りは関連するものの、完全に同じではないため、古来の踊りを復元した上で、宵山で披露するに至ります。
完全復興に先立つ、昭和48年(1973)のことでした。
全くの無から復興するのと、土台があって修正するのとでは、大変な違いがあったことでしょう。綾傘鉾の復活に、この貢献はいかに大きかったか。
現在でも、壬生六斎念仏の構成員は、綾傘鉾にも奉仕されています。

どうも壬生の地域は、梛神社が成立の社伝以外にも、棒振り囃子と強いつながりがあったことを示唆する「状況証拠」があるように思います。
もちろん、平安期の棒振りやお囃子が、全くそのままの形態かどうかはわかりません。
社伝には「鉾」を振り回していたとあります。
それでも、棒振りの風流を、江戸時代にもう「古例」と言われるくらい長い間、ずっとずっと伝えて来たのです。
元祇園梛神社と八坂神社は同じ神様と社伝に寄って繋がり、壬生六斎念仏と祇園祭綾傘鉾は棒振り踊りなどで繋がり、幾重もの縁が出来ています。
八坂神社で踊った次の日に、梛神社に戻ってきて棒振りをする。
千年以上のお話を一気に巻き戻したような、不思議な気持ちがしませんか。
なお、今年(2021年)は、新型コロナウィルス感染防止のため、綾傘鉾町内での棒振り囃子披露は、時間を変更、規模を縮小しながら、7/14~16の三日間、実施されています。
(本稿校了は宵山7月16日)
2021年も、山鉾巡行は中止となってしまいましたが、なんとか来年、例年通りの巡行が出来るよう、願っています。
祇園祭細見 松田元 山鉾編
京都祇園祭手帳 前祭編 河原書店
祇園祭 その魅力のすべて アリカ編 新潮社