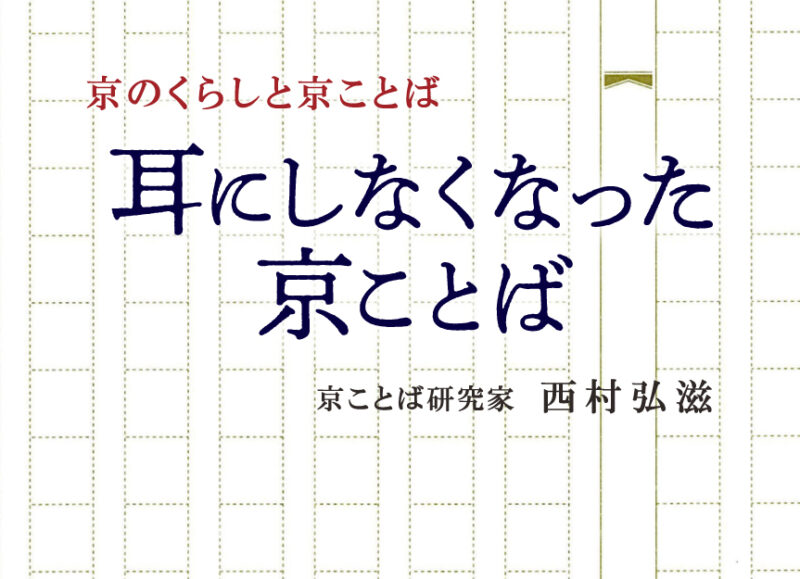今年は、司馬遼太郎生誕100年である。彼は菜の花のような黄色の花を好んでいた。記念館となった東大阪の書斎の前に、ヒューム管を鉢代わりにして菜の花が植えてあったのを思い出す。彼の命日2月12日を「菜の花忌」という。そして、『菜の花の沖』という高田屋嘉兵衛の生涯を描いた作品もある。そんなことが頭に浮かぶと、「なたね」という京ことばを思い出した。記憶の底にあったものが、蘇ってきたのである。みなさんはご存じだろうか。時々弁当にも入っているので、妻に尋ねてみたが、年の差があるものの、意外にもそれを「なたね」と呼んだ。

鮮やかな黄色の「なたね」
この「なたね」、祖父が大変好んで食べていた。簡単に一品のおかずとなり、何もないときでも、酒のあてにすぐになったからだ。どんなものかを簡単にいうと、スクランブルエッグをパサパサにしたようなものである。作り方は、割ったたまごに水少々、塩を加えて、フライパンや片手鍋などでかき回しながら熱を加えるのである。そして、何よりもたまごの鮮やかな黄色が大切なのである。この一品で食卓が華やかなものに変わる。ゆえに、醤油などで味付けをした暁には、ちょっと茶色がかったものとなり、あの鮮やかな黄色ではなくなり、もう「なたね」ではない。ただ箸でつまんでもポロポロ落ち、弁当には難儀である。しかし、この時季、一足早い「なたね」が食卓を賑わす。こんな簡単な料理ではあるが、色添えという食文化を醸し出すのである。
名は体を表すというが、ネットを見てみると、なたね玉子とか煎り卵などとある。あのつくられた「なたね」から菜の花を思い出すだろうか。一面に広がるあの菜種の花を想像できるだろうか。そう思うと、うまく京ことばとしておさまっているなとつくづく思う。
あぶって食べる「いたおみき」
ところで、まだまだ寒さは続く。ゆえに、時々粕汁などもまだ食卓に上がる。三寒四温はもう少し先である。この粕汁という命名は、おそらく酒粕からであろうと思われるが、京都は伏見という酒処があり、十分に酒を含んだ芳醇な酒粕が出回る。しかも、有名な蔵元の名の通った酒粕ゆえ、各家庭には贔屓の酒粕があるようだ。また、料理によっては使う酒粕も違うようである。そして、何より「酒粕」という命名が京都の人には気になるのか、京ことばでは、「いたおみき」という。酒のことを「おみきさん」というが、何も神さんに供える酒だけではない。その「おみきさん」の香りのする板状のものということで、「いたおみき」と呼んでいる。漢字で書けば、「板御神酒」「板神酒」となる。ゆえに酒気を含まない、みずみずしさのないカスカスの状態のものは、京都の人も酒粕なのである。「いたおみき」と聞くだけで、ワンランク違った粕汁となるように感じる。そして、この「いたおみき」、火鉢に網を乗せて、あぶって食べるのである。その酒の汁が火に落ちて、ジュジュという音がする。ぷんと酒の匂いが香る。もちろん火鉢でコトコトと炊く甘酒もいいが、手軽でアルコール度は抜けるが、この食べ方などは、やはり「いたおみき」のほうが相応しい。
「おでん」といえば豆腐田楽
もう一つ、寒さの中での楽しみは、おでんで一杯である。京ことばでは、おでんのことを「かんとに(関東煮)」という。「かんとだき(関東炊き)」という人もいるようだが、これは大阪での呼び方である。まだ勤め出した頃、50年ほど昔であるが、縄のれんの店や京都駅の屋台などには、「関東煮あり〼」などと書かれていたが、今やほとんど見ることもない。しかし、小学校の給食の献立には、「関東煮」と書かれている。公教育の場面で京ことばで献立が書かれているのである。家庭で母親が今日はおでんやといって、食卓に上がったものを見た子どもが、『これ「かんとに」やんか』と言っている姿が想像できるのが楽しい。

もともと京都では、豆腐田楽のことをおでんと呼んでいた。八坂神社にある二軒茶屋の中村楼の田楽は有名である。串刺しにした豆腐に味噌をつけて焼いている。ところが江戸時代も末になると、江戸では、具材を煮込んで食べる煮込みおでんが生まれ、上方ではそれを区別するために、焼いたおでんを田楽と呼び、関東から入ってきた煮込みおでんを「かんとに」「かんとだき」と呼んで、区別したのである。十返舎一九の『東海道中膝栗毛』では、八坂神社社頭の二軒茶屋で、店の女が「たゞ今、おでんがでけます」といって、焼いた豆腐田楽を出していることからも、串刺しにした豆腐田楽をおでんといっていたことがわかる。しかし、いつの間にか、京都の「かんとに」もおでんになってしまった。さびしい限りである。望みは、小学校給食での「かんとに」と書かれた献立だけである。
宣教師が伝えた「ひろす」
さて、そんな「かんとに」の中の具材の一つである「ひろす」についてである。今はなかなか妻も炊いてくれないので、はるかかなたの京ことばである。一般的には、「ひりょうず」「ひりょうす」といい、漢字で表すと「飛竜頭」と書く。豆腐をつぶして、ニンジンやゴボウ、ユリネ、ギンナンなどを混ぜて油で揚げたものである。ポルトガル語のfilhosからきたことばで、室町時代に宣教師が伝えたものである。それは、うるち米ともち米を水で練って、油で揚げたものであった。私は「ひろす」というが、「ひろうす」という人もいる。東京では、「がんもどき(雁擬き)」である。「かんとに」の中では、つゆがしみ込んで、噛むと器の中に、その汁がボタボタと落ちる。この「ひろす」をかんぴょうと一緒に炊いたものもまた美味い。近所の買い物では、「ひろうす」と言い、帰ってくると「ひろす」と呼ぶ。しかし、京都は有名な豆腐店もあり、そんな店に行くと、「ひりょうず」といって買う。中京区の豆腐屋では、「ひろぅす」と書いてあった。場面によって違った呼び方が、また面白い。ちょっと気を付けて耳を傾けて欲しい。
これら粕汁や「かんとに」が食卓から消えると、寒さも和らぎ、春が訪れるのである。