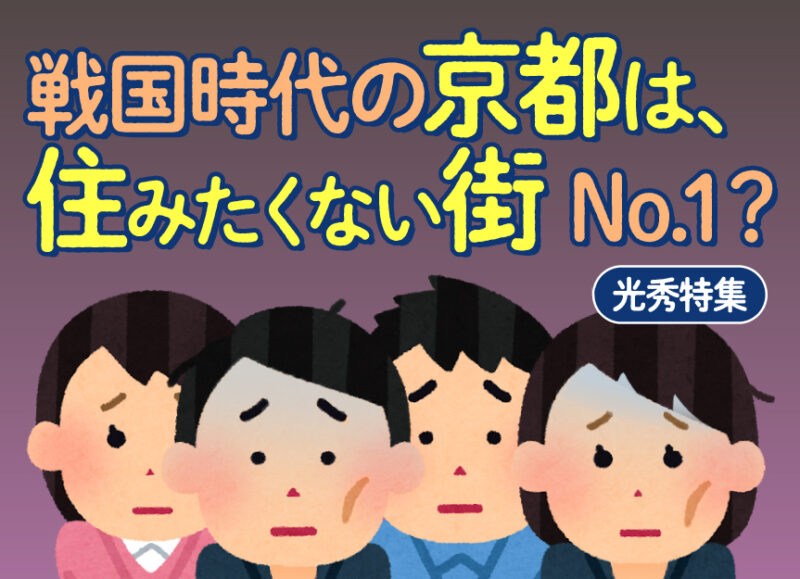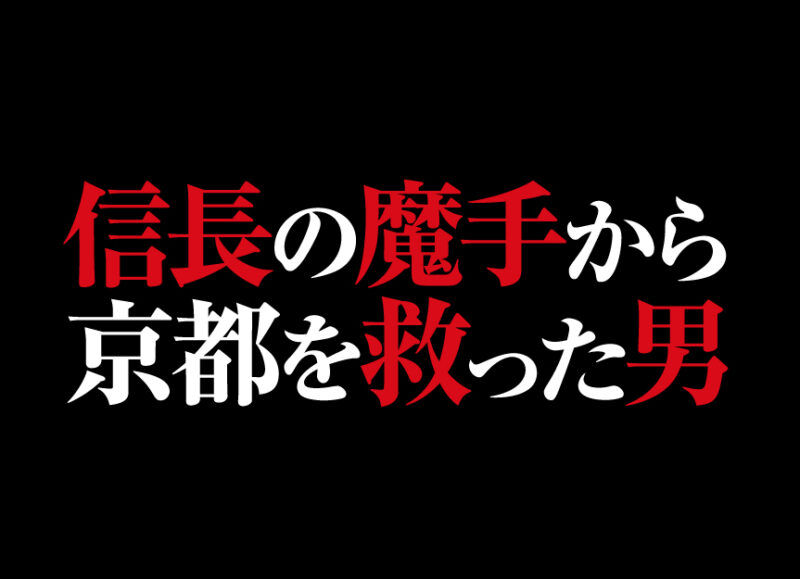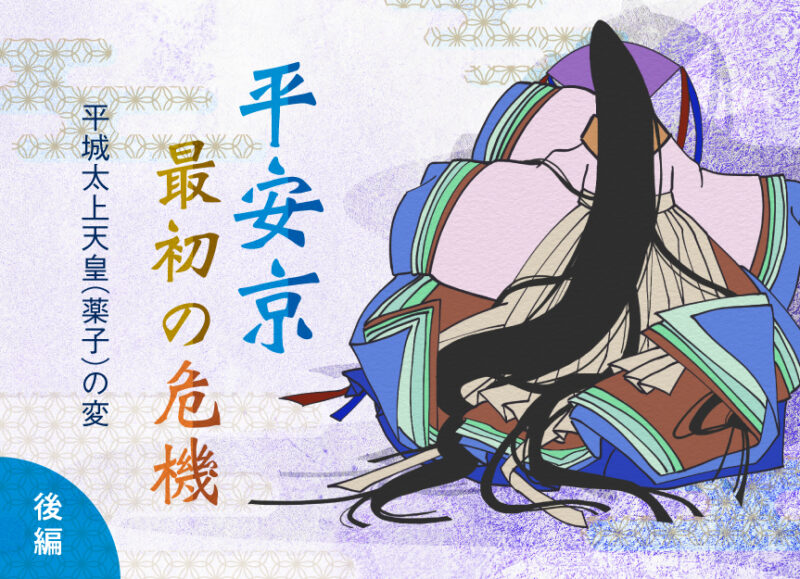時は鎌倉幕府の勃興期。
天皇家の神的権威の象徴であった、宝剣・勾玉・鏡の三種の神器。
しかし源平の戦いに巻き込まれ「剣」だけはついに戻りませんでした。
宝剣のないまま即位した後鳥羽上皇。朝廷復権を目指し、時には自ら槌を振るい剣を鍛え上げます。
菊御作の太刀。
それらを付き従うものに授け、上皇は鎌倉幕府との対決「承久の乱」に打って出るのでした。
幕府の勝利
さて、承久3年(1221)、後鳥羽上皇は京都にいた鎌倉派の武士 伊賀光季を襲い、これを殺害します。京都を中心とした畿内は、上皇の勢力範囲となりました。
同時に鎌倉幕府をまとめていた北条義時を朝敵とし、これを討ち果たすための院宣を出すのです。
前半の冒頭で、私はこの承久の乱を「きたる元寇・元帝国の襲来に向けて、日本を指導するのは『京都の朝廷か鎌倉の幕府か』を選び取る過程」としても見ることが出来る、といいました。
知られる通り、鎌倉幕府がこの戦いに勝利します。
元寇のような大きな対外戦争において、その指導者をつとめるためには…。
日本国内を掌握する統治力と、必要な規模の軍隊を組織し派遣する指揮能力がなければなりません。
指揮能力の点では、鎌倉には実績がありました。関東を統治するだけでなく、西日本にいた平家勢力や、東北地方にいた奥州藤原勢力に対して、大規模な軍勢を派遣して打ち破っています。
対して、後鳥羽天皇には実戦指導の経験がありませんでした。
美濃国から、上皇へと報せが届きます。
「関東の武士たちが軍勢を整え、官軍を破るために西上しようとしている」。
吾妻鏡によると、その数は総勢19万騎。
「むろん誇張があると思われるが(坂井孝一)」、それにしても大軍勢が三方面に分かれて京を目指して来たのです。

京方(官軍)は尾張・美濃で敗退し、近江の瀬田川周辺や山城の宇治などの都周辺まで追い詰められます。
後鳥羽上皇は比叡山延暦寺の僧兵に期待をかけましたが、延暦寺からの返答は「衆徒の微力」では「東士の強威」を防ぎ得ないというものでした。
京方2万数千は、瀬田でも宇治でも激戦を繰り広げました。

各方面で幕府方の突破を許し、追い詰められる京方。
このとき、後鳥羽上皇にとって極めて不名誉な記録が残されています。
敗れ去った京方の武士たちが、上皇の御所へとやってきました。
「君は早くも合戦に負けておしまいになりました。門をお開けください。御所に籠もって力のかぎり戦って討ち死にいたす所存です」
そう奏上したのは、三浦胤義だったとか。
院は、答えます。
「男共が御所に立て籠もれば、ここは包囲されて自分(上皇)が攻められる。それは不本意であるから、早々にどこへなりと立ち去れ」
胤義はこの無情に驚き、呆れ、この上皇の誘いに乗って謀反を起こしたことを後悔するのでした。
さらに院は幕府方の北条泰時に勅使を遣わします。
「この度の合戦は上皇の意思(叡慮)ではない。謀臣が申し行ったところである」。
この申し様を受けた時、鎌倉方はどのような顔をしたことか。
ときに承久3年 旧暦の6月15日。平時であれば、祇園会のころでした。
後鳥羽上皇のこの時の行動は責任回避的で、もっとも惨めな有り様として描かれています。
私はこれを読んで「鎌倉方が上皇を貶めるために話を盛ったのか」とさえ思いました。
朝幕のねじれを憂い、あるべき治世を求めた上皇。ときに鍛冶場に立ったほどの熱意ある人物像が、まったく跡形もないのです。
『稀代の帝王、必ずしも賢王ではないのである』(坂井孝一)
概説書を何冊か読んでみましたが、私のような疑問を持つ人はいないようでした。
上皇はどうも、巻き込んだ人たちに対する意識が薄いように思います。
「貴人、情を知らず」という言葉があります。
彼もまたそうだったのか。
あるいは朝廷が敗北するということを全く考えておらず、初めて向き合う恐怖に人格が萎縮したのか…。
戦のあと
鎌倉幕府による後鳥羽一党への処分が始まりました。
後鳥羽上皇が隠岐の島へ流されたことは、比較的知られているかと思います。
幕府による追求は皇族全般に及びました。後鳥羽の直系子孫は皇位から遠ざけられ、あるものは遠島に処されます。
新たに皇位についた後堀河天皇は、後鳥羽の血を引かないからこそ白羽の矢がたった人です。承久の乱がなければ、おそらく芽はなかったでしょう。
幕府はこうして朝廷を影響下に置き、後鳥羽上皇が所有していた三千箇所という荘園を没収します。有事の際には「必ず武家に返却する」という誓約をさせたうえで朝廷に渡しはしたのですが、これら土地への影響力が飛躍的に高まったことは間違いありません。
上皇方に与した貴族・武士たちにはさらに厳しい処分が待っていました。
数多くの人々が追手を差し向けられ、捕らえられ処刑されました。
それを見越して自害するものも居ました。先述の三浦胤義なども、そうでした。
多くの血を流し、鎌倉幕府が朝廷を抑え込みました。
それから約50年後の元弘11年(1274)、元帝国の皇帝フビライが軍勢を九州北部へ向けて送り込むことになります。
当時の鎌倉幕府は、事前の経緯から蒙古襲来を察していました。戦いに先立つ文永8年(1271)、あらかじめ九州に御家人を派遣しています。
鎮西(九州)に所領を持つ御家人は、たとえ本拠地が他の地域であっても防衛に赴くよう指示したのです。
「異国の防御をいたし、領内の悪党を鎮めなさい」という司令文が残っているそうです。
また、「異国警固番役」を任命して指揮系統も整えていました。
私は想像します。承久の乱なしに、これらの体制が出来ただろうか。
あるいは朝廷が勝った時、幕府同様に速やかに国内を掌握できたか。元寇に際して、幕府に匹敵する処置を行えただろうか。
後鳥羽上皇ならあのカリスマと実行力で成し遂げたかもしれない…。
逆に、武士の離反を招いたかもしれない。後の世の後醍醐帝のように。
これもまた、結果論です。
歴史の正解はひとつではなく、試行錯誤の結果が次に繋がったに過ぎない。
鎌倉幕府が国防戦争を成し遂げた、という結末へと。
何が最善だったかはともかく、許容内の結果は残すことが出来たのです。
後鳥羽上皇の役割
50年は人生と比べれば長い時間ですが、国家の歴史にとってはまたたく間です。
ひとつの政権が確立し機能するまで30~50年かかることも珍しくありません。
後鳥羽上皇の時代、だらだらと国を割っている場合ではなかったのです。
鎌倉幕府が内部対立で汲々としていたとき、両者対決の引き金を引けるのは上皇だけでした。
後鳥羽上皇は、歴史を一歩進めるために敢えて敗北する、まるでトリックスターのような役割を果たしたように見えるのです。
一言だけ、上皇を弁護するならば。
統治権を持つ者が、整備された権力体を目指すのはごく自然なことです。むしろ機構を整えることが彼らに求められる責任と言ってもいいでしょう。
先述しましたが、「国を割っている場合」ではありませんでした。
国家体制の問題を認め、行動できたという点でやはり上皇の全てを否定し切ることは出来ないと考えます。
とはいえ、死んでいった人たちがいます。
まさに刑場に引き出され命を散らそうとする人に向けて、この戦いの歴史的意義を話したところで慰めになるとは思えない。
「私は歴史の駒ではない」
と叫ぶかもしれません。
興味深い話があります。
平安時代前期の10世紀、やはり大陸から九州へと外敵勢力の襲来がありました。
刀伊の入寇といいます。
九州の人々の抗戦によって、防衛に成功します。
この時、機械式の弓、弩(いしゆみ)が活躍したといいます。
弩は歩兵の道具で、騎兵には適しません。
この時の戦訓を受けて、三善清行という臣が醍醐天皇に向けて国防指針というべき意見書を提出しました。
彼は述べます。
「弩こそ国防の要です」と。
国防構想において、まだ武士の影も形もありはしませんでした。
それから300年弱。
東日本に武士という軍人階層が現れ、戦い方の常識を変え、日本の国家体制を革めていきます。
やがて彼らが西へ赴き、元帝国の矢面に立つ日がくると想像できた人が居たでしょうか。
一例を挙げましょう。
九州 肥前国に千葉氏という一族が居ました。彼らは名前の通り現在の千葉県 下総国などに根を張っていたものが、元寇の際に一部が幕府の命で九州に移り住んだのです。
彼らは桓武平氏で、つまり平安京を作り上げた桓武天皇の末裔でした。
東国のどこかで起こった武士という波が、列島の西の果てまで届いていくのです。
さて後鳥羽上皇ですが、島流しとなった隠岐の島で歌を詠んでいます。
「我こそは新じま守(もり)よ沖の海のあらき浪かぜ心してふけ」
歌人 丸谷才一は、この歌をこのように解釈しています。
この歌は、惨めな流人として「優しく吹け」と海に哀願するのではなく、自分が島守として守るべき他者のために「心して吹け」と命令しているのだ、と。
この一首、敗残者の惨めな心情として紹介されがちなのですが。
元寇を意識しながら調べている私には、別の「風」が心をよぎるのです。
島守である彼が、海原に命じた風。
軍船を砕き、敵勢を押し流す海風。
いや…いかに異能の上皇とはいえ、この時点で未来が見えているはずがないのですが。
そんなはずは、ないのですが。

参考文献
承久の乱 真の「武者の世」を告げる大乱 坂井孝一 中央公論新社
承久の乱と後鳥羽院 敗者の日本史6 関幸彦 吉川弘文館
後鳥羽院政の展開と儀礼 谷昇 思文閣出版
後鳥羽院 第二版 丸谷才一 ちくま学芸文庫
愚管抄 慈円 愚管抄 全現代語訳 大隅 和雄 講談社学術文庫
よみがえる承久の乱 後鳥羽上皇VS鎌倉北条氏 京都文化博物館2021
蒙古襲来 戦争の日本史7 新井孝重 吉川弘文館
モンゴル帝国の戦い ロバート・マーシャル著 遠藤利国訳 東洋書林
三種の神器に関する研究:「剣の観念」の中世的展開 酒井利信 武道学研究36