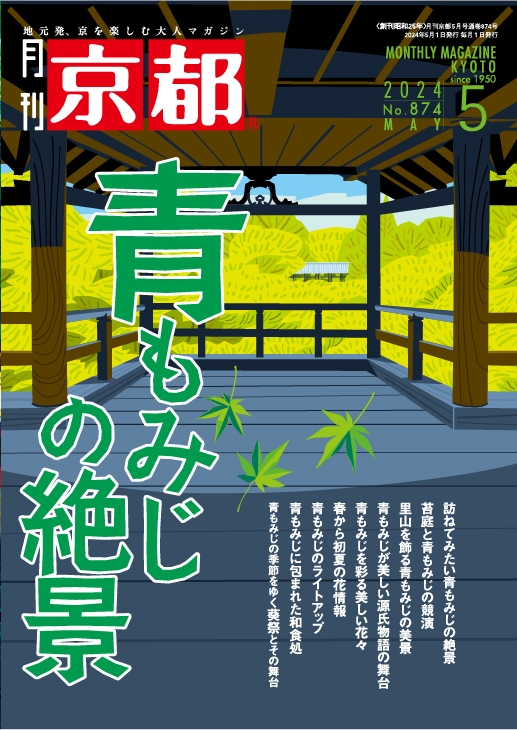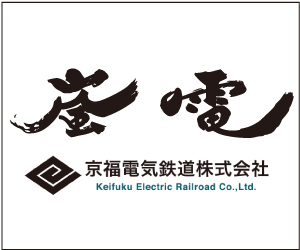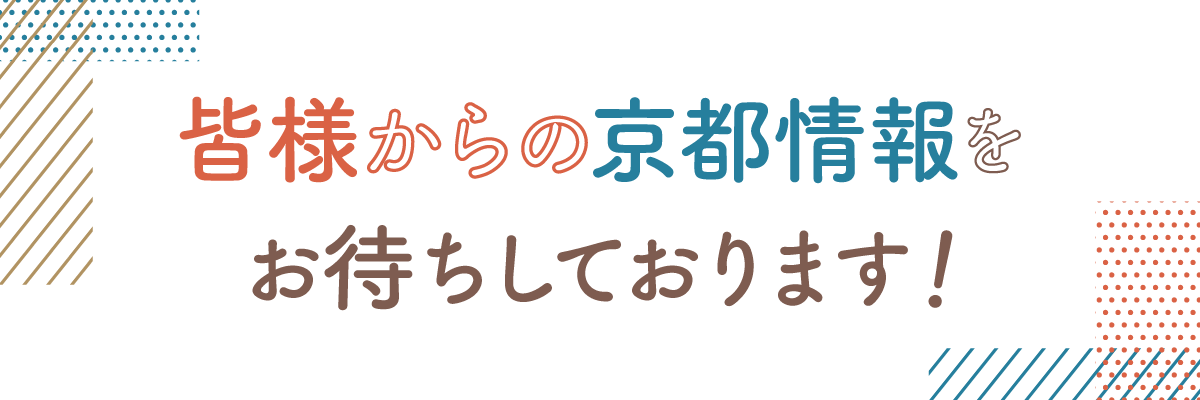見どころがいっぱい!北野天満宮
【歴史愛好家シリーズ】この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます
▶︎[船岡山の光と影]清少納言も愛でた市内北部のランドマーク▶︎[城郭寺院ー金戒光明寺ー]アフロな地蔵?
▶︎[京見峠と氷室ー堂ノ庭城ー]昔の氷の保管場所、氷のかわりに食べていた○○
▶︎[豊臣秀次と瑞泉寺]処刑場は、今やカップルの憩いの場
5.右近馬場
一の鳥居の東を走る南北一筋の馬場を言う。ここは、日本最初の競馬場である。古代から遊猟で知られ、平安時代には大宮人の遊宴の地であった。
出雲阿国が慶長8年(1603年)、はじめて歌舞伎踊りを披露したとも言われている。
北野さんの南東の警察敷地は北野右近馬場城跡と言われている。
6.伴氏社 道真公の母君
道真公の母君が大伴氏の出身であり、伴氏社と言う。暖かい愛情と厳しさで菅公を優秀な青年官吏に育て上げた母君を祀る。神前の石鳥居の台座には珍しい連弁が見られる。
大伴氏を供養する石造りの五輪塔が、南隣の東向観音寺にある。
明治維新の神仏分離政策により、ここに移された。
忌明塔ともいい、むかし父母をなくした人が49日喪に服し、忌明けの50日目にこの塔に詣る習慣があった。
7.楼門の扁額
楼門には「文道大祖・風月本主」の扁額が掲げられている。
菅公は「文道の大祖・風月の本主」と言われ、学問や芸能の神様であり、自然界の主であると讃えられている。牛は多くの信仰を集める菅原道真公のお使いである。
8.二の鳥居
新門辰五郎が寄進した石鳥居。
新門辰五郎は、江戸時代後期の町火消、とび職、香具師、浅草寺門番、侠客の元締め的存在であった。
石灯籠と松並木が並ぶ参道は、厳かな神道の雰囲気が漂う。
9.撫で牛
牛が菅原道真公のお使いとされるのは「菅原道真の墓所の位置は牛が決めた」「菅原道真が生まれたのは丑年」「菅原道真は牛車に乗って太宰府に行った」「牛が刺客から菅原道真を守った」などに由来している。
撫牛さんには、自分の悪い部分と牛の同じ部分を交互に撫でることによって、回復するという信仰がある。神牛像は20体ある。
母と子の像もあり、探すのも一興である。


関連する記事
 橋本 楯夫
橋本 楯夫
昭和19年京都市北区生まれ。
理科の中学校教諭として勤めながら、まちの歴史を研究し続ける。
得意分野は「怖い話」。
全国連合退職校長会近畿地区協議会会長。
|自称まちの歴史愛好家|北野天満宮/今宮神社/千本通/明智光秀/怖い話
アクセスランキング
人気のある記事ランキング