
京都がもっとも輝いていた時代。桃山文化の神髄を堪能する。
安土時代ってそんな感じだったんじゃないでしょうか?つまり「自由と恐怖」がセットの時代、それが安土という時代だったように思います。本能寺の変は、いろいろな意味で「恐怖から逃れるため」に起こった事件だといえます。さて、その後に政権を取ったのが、ご存じ豊臣秀吉です。彼の特徴をひとことでいえば「人たらし」に尽きると思います。天性のキャラと人心を読みとり、くすぐる術に長けていた秀吉は、かつての上司や同僚、難敵・徳川家康をも臣従させます。さらには天皇や朝廷まで「たらし」こみ、関白の座を手に入れたわけです。その人たらしっぷりは民衆にまでおよびます。その象徴といえるのが「北野大茶会」です。格式を重んじる茶会を一般大衆に開放し、関白自らが茶を点てもてなすという前代未聞の催しでした。現代でいえば昭和末期のバブル期のような華やかな雰囲気があったのだと思います。そのバブルは秀吉の死とともにあっけなく弾けました。その後にやってきた徳川江戸時代は、成長を否定した今でいうデフレの時代、また抑圧の時代でもありました。
桃山文化とは「信長の恐怖」と「家康の抑圧」という2つの時代の谷間に咲いた一輪の花、ひと時の栄華であったように思います。同時に京都にとっても特異な時代であったといえます。そんな視点をもって「京の冬の旅」で公開される各所を見て回るのも、もう一つの京都の楽しみ方ではないでしょうか。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます
▶︎宇治の「おとぎ電車」▶︎京の地形と京都人が育て利用してきた京野菜
▶︎「ぶっ飛んでいる仏師」京の変人烈伝vol.1
▶︎プロの配達員が語る京都の宅配事情 part1
▶︎「京の冬の旅」公式HP
なお、コロナウイルス感染拡大の状況、社会情勢等により「京の冬の旅」が中止または内容変更となる場合がございます。
非公開文化財特別公開
今回の「京の冬の旅」で特別公開される文化財は下記の通りです。


関連する記事
 吉川 哲史
吉川 哲史
祇園祭と西陣の街をこよなく愛する生粋の京都人。
日本語検定一級、漢検(日本漢字能力検定)準一級を
取得した目的は、難解な都市・京都を
わかりやすく伝えるためだとか。
地元広告代理店での勤務経験を活かし、
JR東海ツアーの観光ガイドや同志社大学イベント講座、
企業向けの広告講座や「ひみつの京都案内」
などのゲスト講師に招かれることも。
得意ジャンルは歴史(特に戦国時代)と西陣エリア。
自称・元敏腕宅配ドライバーとして、
上京区の大路小路を知り尽くす。
夏になると祇園祭に想いを馳せるとともに、
祭の深奥さに迷宮をさまようのが恒例。
著書
「西陣がわかれば日本がわかる」
「戦国時代がわかれば京都がわかる」
サンケイデザイン㈱専務取締役
|八坂神社中御座 三若神輿会 幹事 / (一社)日本ペンクラブ会員|戦国/西陣/祇園祭/紅葉/パン/スタバ
アクセスランキング
人気のある記事ランキング




























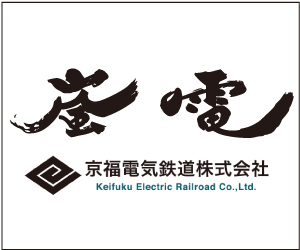





~没後400年記念 大名茶人・織田有楽斎ゆかりの寺~