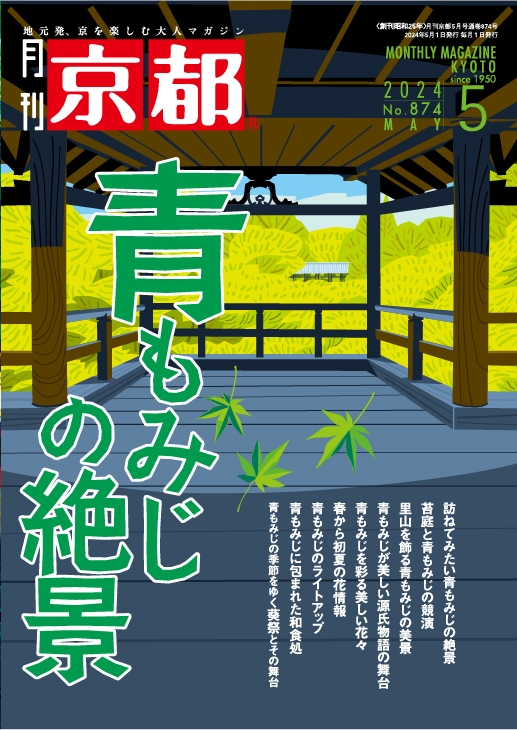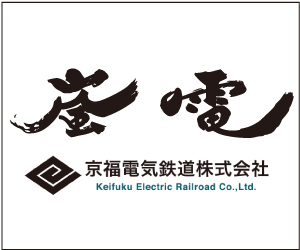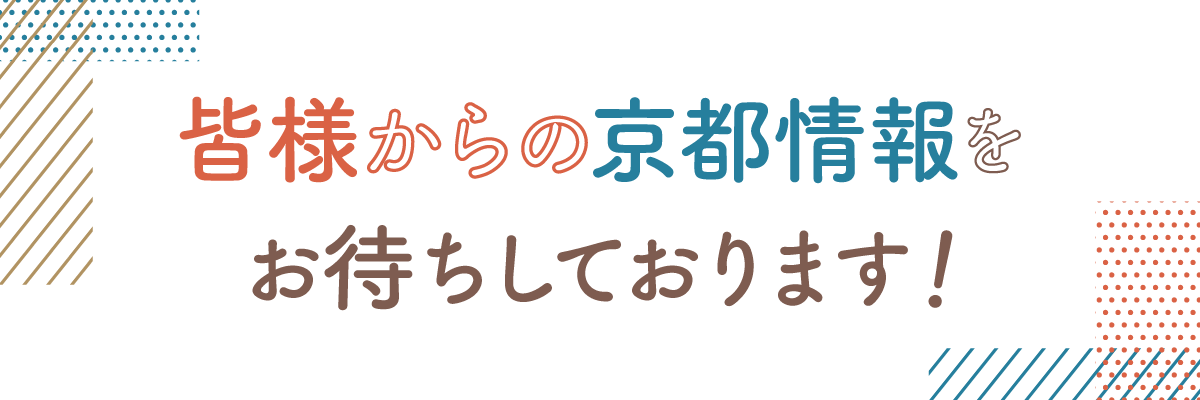茶道とは。何モノか。 その5「大坂 堺 織田信長と茶の湯政道。」
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます
▶︎由緒正しき京菓子店▶︎お盆に始まる行事の数々
▶︎神輿をかつぐ人だけのお弁当
▶︎漱石も惑わされた「おおきに」の意味
▶︎京都の春の味といえば竹の子
▶︎京野菜で作る昔ながらのお雑煮
翌 天正6年(1574年)3月24日 織田信長は、相国寺で茶会を開いた。茶頭は信長の右筆(秘書役)武将 松井友閑であった。友閑は、祖父の代から足利氏の幕臣として仕え、永禄の変で足利義輝が三好三人衆らによって暗殺されると、後に織田信長の家臣となった人物である。「兼見卿記」、「宗及記」によると、津田宗及とも親交を深め、目利きで知られ、鳥丸家、松江宗訥と共に、天下三墨蹟の一つ「無準」の墨蹟を所持していた。無準師範は中国 南宋の臨済宗の僧で、鎌倉時代中期の僧 円爾をはじめ日本から無準に参じた僧は多く、日本に最も強い影響を与えた宋代禅林中の巨人である。
松井友閑は、武野紹鴎より「相阿弥茶湯書」を伝えられ、戦国武将としてだけではなく、茶人、文化人で、茶道に対する造詣が深かった。後にも信長が開く茶会には、度々茶頭として呼ばれ、織田信長の相国寺茶会には、天下三宗匠のうちの二人、堺の豪商 天王寺屋 津田宗及、千宗易(千利休)が出席し、床には水墨山水画を描いて牧谿(もっけい)と並称される、玉㵎筆の「万里江山」の絵 (玉㵎:中国 南宋末の画僧)、京都の豪商 大文字屋から召し上げた「初花」肩衡(茶入)、「安井茶碗」「朱徳作茶杓」がズラリと並んだ。
「香炉両人所持」と呼ばれた、「不破香炉」所持の津田宗及、「珠光香炉」所持の千利休に、織田信長は扇子に乗せた蘭奢待(らんじゃたい)を、扇子と共にこの二人に下賜した。蘭奢待とは、奈良 東大寺 正倉院 中倉薬物棚に、正式名称「黄熟香(おうじゅくこう)」別名「蘭奢待(らんじゃたい)」と呼ばれる、現在も実在する香木がある。蘭奢待の「蘭」文字の中には、「東」。奢の中には、「大」。待の中には、「寺」が、含まれているので、別名、「蘭奢待(らんじゃたい)」と呼ばれ、成分からは伽羅に分類される香木で、平城京の仏教文化を創った聖武天皇の崩御のあと、光明皇后により、東大寺に奉献された聖武天皇遺愛の品の一つである。日本には聖武天皇の代(724年‒749年)に中国から渡来したと伝わり、一説には「日本書紀」や聖徳太子伝暦の推古天皇3 年(595年)記述という説もある、天皇家伝来天下の香木である。
歴代の天皇や将軍たちは、手柄のあった者に対し、この香木を切り取って与え、蘭奢待を持つ者が、天下人である。という象徴となった。現代においても、正倉院展で公開される蘭奢待には、足利義満、足利義教、足利義政、土岐頼武、織田信長、明治天皇らが切り取った跡が示されている。
「御会過テ、蘭奢侍一包拝領申候、御扇子すへさせられ、御あふきとともに被下候、宗易・宗及両人ニ迄被下候、香炉両人所持仕候とて、易・及ニ東大寺拝領いたし候、其外堺衆ニハ何へも不被下候」織田信長は扇子に乗せた蘭奢待(らんじゃたい)を、扇子とともに津田宗及、千宗易(千利休)、この二人に下賜したのである。
織田信長の「茶の湯政道」である。
天正3年(1575年)十月二十八日、織田信長と徳川家康が武田勝頼の軍勢を破った長篠の戦いの三ヶ月後、織田信長は京都や堺の茶人17人を招き京都妙覚寺で茶会を催した。本願寺との和睦が成立し顕如上人へ一文字呉器茶碗を贈った一週間後である。浄土真宗本願寺派 第11世宗主である顕如が信長に献上した茶壷「三日月」、「白天目茶碗」、「九十九髪」の茶入、「松島」の茶壷など、天下の大名物を披露した。この時、茶頭を務めたのが千宗易(千利休)で、「信長公記」に宗易の名が登場するのはこの時が初めてである。
「千利休由緒書」には、この頃「御茶頭を仰せ付けられ三千石を給された。」と記されている。
天正5年(1577年)松永久秀が、信長の命に背き、上杉謙信、毛利輝元側に寝返った。信貴山城に立て籠もり再び対決姿勢を明確に表した。信長は松井友閑を派遣し、理由を問い質そうとしたが、使者には会おうともしなかった。
同年、織田信長が紀州征伐へ出陣すると、播磨国の別所長治もこれに加勢し、同盟関係から裏切った中国地方の毛利輝元を信長が制圧しようとすると、長治は先鋒役を務めに申し出た。しかし、織田勢による上月城の虐殺、中国方面総司令官が足軽出身の新参者 羽柴秀吉であることに不満を抱き、妻の実家である丹波国 波多野秀治と共に信長に反逆した。
1578(天正6)年正月一日、安土城 織田信長のもとへ五畿内の諸将が新年挨拶のため出仕する事となった。信長は諸大名の挨拶を受ける前、一部のだけの諸将を招き、朝の茶事を催した。出席者は織田信忠、武井爾伝、林秀貞、滝川一益、細川藤孝、明智光秀、荒木村重、長谷川与次、羽柴秀吉、丹羽長秀、市橋長利、長谷川宗仁である。6畳の茶室に於いて十二名、この茶会で何が話されたのか。十二名から外された武将達は、その事実をどのように受け止めたのか。茶の湯の第一は客組で、主客とも拝見する第一は道具でなく「人間」なのである。茶頭は松井友閑が務め、一同は茶席にて雑煮と舶来の菓子を信長から賜った。
以降4年間、播磨国攻略、織田家京屋敷を二条新御所として、皇太子 誠仁親王に進上、大坂本願寺との講和、東国 北条氏政を織田政権 支配下に従属させ、徳川家康と同盟関係にあった信長は、徳川領の遠江・三河へ侵攻した甲斐武田氏一族を攻め滅ぼし、名実共に天下人へとたった数年で駆け上がっていく事になる。
天正10年(1582年)一月元旦、織田信長は出仕してきた者たちに安土城の天皇を迎えるための部屋「御幸の間」を見せた。という記録が「信長公記」に残されている。信長を太政大臣、関白、征夷大将軍のいずれかに任ずる事が話し合われ、5月に朝廷が安土城の信長に推任のための勅使を差し向けた。
本能寺の変
本能寺の変 天正10年(1582年)五月二十九日、信長は未だ抵抗を続ける毛利輝元攻略の中国遠征 出兵準備のため、「戦陣の用意をして待機。命令あり次第出陣せよ。」と、安土城の留守居衆と御番衆に指示を出し、供廻りも連れず本能寺に逗留した。六月一日 信長は、安土より38点の茶道具を京に運ばせ、前久、晴豊、甘露寺経元などの公卿・僧侶ら40名を招き、本能寺に於いて道具開きの茶会を茶開き、名器を披露した。この茶会の目的は博多の豪商島井宗室が所持する楢柴肩衝を何とか譲らせようと思っていたとも、多数存在する暦の統一を朝廷と交渉するための上洛だったとも云われている。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます
▶︎由緒正しき京菓子店▶︎お盆に始まる行事の数々
▶︎神輿をかつぐ人だけのお弁当
▶︎漱石も惑わされた「おおきに」の意味
▶︎京都の春の味といえば竹の子
▶︎京野菜で作る昔ながらのお雑煮


関連する記事
 松尾 大地
松尾 大地
昭和44年(1969年) 京都 三条油小路宗林町に生まれる。
伏見桃山在住
松尾株式会社 代表取締役
松尾大地建築事務所 主催 建築家
東洋思想と禅、茶道を学ぶ。
|禅者 茶人 建築家|茶道/茶の湯/侘び寂び/織田信長/村田珠光
アクセスランキング
人気のある記事ランキング