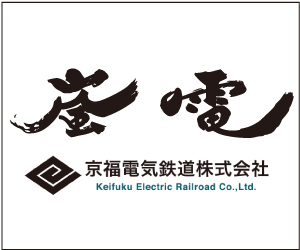七草がゆの歌~お正月の習わし〜【京都人度チェック】
この歌は京都以外の地方にもさまざまな形で残り、長く歌われてきたようです。「京都」は「日本人の文化のルーツ」、この習わしも京都から日本各地に広まったのでしょうか。
たとえば茨城では
「七草なずな、唐土(とうど)の鳥が、日本の国に、渡らぬ先に、ストトントントン」(注4)
という歌が。リズミカルな包丁の音が聞こえてきそうですね!
鳥取では
「唐土の鳥が 日本の土地に渡らぬさきにせりやなずなや 七草そろえて繁盛 ホーイホイ」(注5)
となります。「追っ払う」うちに「ゲン担ぎ」のほうに行ってめでたい歌に。
山梨では
「唐土の鳥と日本の鳥と渡らぬ先に、あわせてこわせてバッタバッタ」(注6)
歌の後半では大きな鳥と戦っている様子が浮かんできそうです!
囃し歌を調べて行くと、伝わっていくうちに各地にたくさんのバージョンが生まれ、それぞれの地域に合ったものに変化して行ったのやなぁというのが見て取れました。でも思いは1つ、「疫病を防ぎ、無事に過ごしたい」ということです。
そして少なくとも、すでに700年前には七草の上でトントンしてた日本人が、今ほど感染症に勝ちたい気持ちが強い時はありません。鬼車鳥を退散させるべく、私も今年は心を込めて、より強くたたいて歌いましたよ!
「とんとの鳥が 日本の土地へ 渡らぬ先に 七草なずなを 祝いましょう!!」
疫病退散!!
注2:「年中故事要言」元禄10年(1697年)刊に見える
注3:天球を分けた二十八宿の区分のうちの4つ
注4:茨城県鹿島郡鉾田町の歌。 WEB本の雑誌「私の好きなわらべ歌」
注5:鳥取県西伯郡大山町国信の歌。
鳥取県立博物館サイト 注6:山梨県立図書館レファレンス回答


関連する記事
 鳴橋 明美
鳴橋 明美
上京の、形になりにくい文化(お祭・京都のおかず・伝統工芸・京ことば)の継承のお手伝いをする「京都上京KOTO-継の会」会長。
「鳴橋庵」店主。
「能舞台フェスタ in 今宮御旅所」実行委員会会長。
組紐とお抹茶体験を鳴橋庵店舗にて行っております。
合間合間に京都のお話を挟みつつ、楽しく体験していただけます。
お申込みは「鳴橋庵」HPまで。
|鳴橋庵 店主・京都上京KOTO-継の会 会長|お盆/織田稲荷/京都人度チェック/パン/氏子/十三参り
アクセスランキング
人気のある記事ランキング