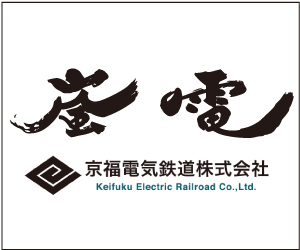京都転車台物語
堀川を斜めに渡る鉄橋は人家の買収が必要であったために実現されずに苦肉の策の転車台だったようですが、電車の向きを回転させて変えるという非常に珍しい光景でした。
2軸の電車の車輪間は約2.1mですから、それより少し大きい目の回転盤があればよかったので、貨車用の転車台を転用したようです。
そこに乗った電車はいったんポール(集電装置)を下げ、乗客が乗ったまま人力で回して向きを変え、またポールを上げて出発していきました。
人々は「車回し」とよんだようで、後に複線化されたときに堀川を斜めに渡る鉄橋が架けられ、転車台も廃止されました。
この電車の転車台の姿は、先般閉館になった子ども文化会館(エンゼルハウス)の壁面レリーフによく表現されていました。
ちなみにそこには「先走りの少年」も表現されています。
4 バスの転車台
「バスの転車台」って何のことと思われるかもしれませんが、バスも結構車体が大きく、狭いところではバスの転車台がありました。市バスでは経路上の次の3か所にありました。
市電伏見線が廃止になった後、市バスに代替されますが、市電時代と同じように市バスが中書島駅のすぐ横まで乗り入れました。しかし、電車時代のようにホームでそのまま折り返すことはできませんから、さらに奥に転車台が設けられ、系統によっては乗客を乗せたままそこでバスを転向させて発車していきました。
現在のような西口のバスターミナルが整備される前に、洛西ニュータウン方面からやってきた市バスが乗客を降ろした後、転車台に乗って向きを変えていました。ターミナルが整備され、今のようにUターンして出ていくようになり廃止されました。
葛野大路と太子道がT字型に交差するところに、ここで折り返していた27系統が向きを変えるために昭和48(1973)年に設置されましたが、馬塚町を通り過ぎるように経路が変更され、ターンテーブルも廃止されました。
このほか、かつては市バスの錦林車庫の中や国道24号線と丹波橋通が交差する北東角に京都文教大学の送迎バス用のターンテーブルがありました。
少し離れていますが、阪急東向日駅に隣接している阪急バスの車庫にも設置されていましたが今はありません。
ちなみにバスのターンテーブルには2つの駆動方法がありました。
1つは電気のモーターで回すタイプで、ターンテーブルにバスが乗った時、ちょうど運転台の窓から手を出せば操作できるスイッチがぶら下がっていました。
もう1つはバスの後輪が乗る位置にローラーがあり、ゆっくりと後輪を回転させると、ローラーが回ってその回転がギヤを介してターンテーブルを回すというものです。
見た目だけで言ってますが、とりわけ後者のものは回転盤の下はメカニックなのでしょうね。
よく考えますと、街中にはパーキングやマンションの駐車場などに自動車用のターンテーブルはいっぱいあります。しかしやはり大きな機関車がグルっと回転するのは迫力があります。一度、鉄道博物館の転車台を見に行ってみてください。
(2020.9)
日本鉄道旅行地図帳 新潮社
鉄道史料17号 鉄道史資料保存会
さよなら京都市電 京都市交通局
梅小路100年史 西日本旅客鉄道株式会社
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます
▶︎地下鉄烏丸線開業前史▶︎お嫁に行った京都市電
▶︎大きく変わった「保津峡」の線路
▶︎東海道線は西から東に延びました
▶︎「三条京阪」地上に駅があったころのお話


関連する記事
 島本 由紀
島本 由紀
昭和30年京都市生まれ
京都市総合教育センター研究課参与
鉄道友の会京都支部副支部長・事務局長
子どもの頃から鉄道が大好き。
もともと中学校社会科教員ということもあり鉄道を切り口にした地域史や鉄道文化を広めたいと思い、市民向けの講演などにも取り組んでいる。
|鉄道友の会京都支部副支部長・事務局長|京都市電/嵐電/京阪電車/鉄道/祇園祭
アクセスランキング
人気のある記事ランキング