
【第四回】「相生結び」は、「相生の松」を意匠化したもの
と説いていました。
許真の説に従えば、「一とは、物事の始まり。今風に言えば、この宇宙を作ったビッグバンのようなもの。そこから、人を含む、すべての生き物が生まれた。更に説明すると、ビッグバンから生まれたのが天と地であり、すべての生き物は天と地によって育まれる。故に、天と地の教えである、〝まこと〟に従い生きていくときは、松や桧のように、天空に向かって真っすぐに伸びて行くことが出来るのだ」と説明していました。
同書は【朱】の文字を、
【朱】赤心の木。松や桧の仲間は、その中心が赤く染められている。故に天空に向かって真っすぐに伸びて行くことが出来る。大切なことは、松や桧のように、人の心に、まことの心が具わること。
と解いていました。
『説文解字』が我が国に伝えられると、我が国の先人は、松や桧の仲間が天空に向かって真っすぐに伸びることが出来るのは、幹の中に【一】を含むことで、朱色に染まっているのだと理解し、松の幹を割ってみたのです。すると、幹の中心部は「朱色」に染まっていました。そこで「松や桧の仲間は、幹の中心が朱に染まっている故に、天に向かって真っすぐに伸びて行くことが出来るのだ」との説明に納得し、引いては「人が、守らなければならない道理を、松や桧はその姿を通して、私たち人に示して見せているのだ」として、結婚式が執り行われる床の間に、真っすぐに伸びた若松を生け飾ってきたのです。
「松栢赤心」の【赤心】とは、「うそ偽りのない心」。更に中国ではその言葉をもとに「赤心を推して人の腹中に置く」と言い伝えてきました。その言葉には、「人と接するときには、真心を以て接し、すこしもへだてないことを意味する」と『広辞苑』は説明しています。つまり、すべての人が幸せに生きていくための決まり事とは、【一】の文字が含み持つ意味を理解することだと説かれてきました。花の道は、そのことを受けて、目で見て理解するために、我が国の先人たちは結婚式に生ける生け花は、天を指して真っすぐに伸びた若松を花材として生けることを習いとすると定めたのです。詰まるところ、ここに載せた生け花には、「松栢赤心」の熟語を目で見て理解させるため、生けられてきたと云ってよいのですが、それ以外にも無言で大切なことがらを私たちに語りかけてきました。
絵図を観ると、松の左側に「男」、右側には「女」の文字が書き入れてあります。ですからこの生け花は、恋して結ばれた男女の二人に、このように生きて行くことができれば、幸せに生きていくことができますよと、人としての究極の願いを込め生けられていたのです。ここには、二本の若松が同じ高さに生けられていました。その姿を通して、男性と女性、両性は互いに性が異なっていても、お互いを尊敬し助け合って生きていくことが大切である。つまり『共棲』することの大切さを、生け表されていたのです。このことは、江戸時代の庶民たちの間では「男尊女卑」の思想が無かったことを今に伝えていると云ってよいでしょう。
更によく観ると、松の下の枝は左右の枝が交差して生けられていました。また、左下には「このしんにある葉を、ミのげという」との文字が書き添えられていました。この生け花のように、左右の枝が交差するように生けることを、「連理の松」に仕立てると云い習わしてきました。とともに、このように生けられた姿には、「比翼の鳥」が生け表されていました。「ミのげ」とは「蓑毛」とも書き、鷺の首の部分に生えている乱れた毛を指すことから、この生け花が「比翼の鳥」として生け表されていたことが分かります。では、「比翼の鳥」とは、どのような鳥を指してきたのでしょうか。
「比翼の鳥」の言葉をもっとも早く伝えていたのは、中国が周と呼ばれた二千年以上も前に著された『爾雅(じが)』という辞書です。同書は早くに我が国へ伝えられていました。その書物をもとに、儒学者の貝原益軒は、元禄七年(一六四九)に『和爾雅』と改名し、その本を出版しました。
同書には「比翼の鳥」を、
南方に比翼の鳥あり。比べれば飛べず。
と記していましたが、その説明文だけでは、比翼の鳥とはどのような鳥かを明確に知ることはできません。そこでさらに『広辞苑』等をもって説明すると、
南の国の楽園には、比翼の鳥と云う鳥が住んでいる。この鳥は、雄は頭に右目だけ、胴体には右翼、右足だけ。また、雌鳥の頭は左目だけ、胴体には左翼、左足だけで、この鳥が空を飛ぶことが出来るのは、雌雄の二羽が一緒になったときだけである。だが、互いを比較しあうときは、空を飛ぶことはできない。
という想像上の鳥で、実は誰も見たことがないとされてきました。ですから「比翼の鳥」がどのような鳥だか良くイメージできない方もいられることでしょう。幸いなことに江戸時代前期、京都には儒学者の中村惕斎(てきさい 1629-1702)が居ました。惕斎は、ほとんど独学で朱子学を収め、伊藤仁斎と並び称されている人です。その惕斎が著した絵解き百科事典が『頭書 訓蒙図彙(きんもうずい)』です。同書には比翼の鳥を画いた絵図を載せていました。ここに、その絵図を載せておきます。詰まるところ、「比翼の鳥」とは、異なる松の枝が接ぎ木したかのように、男女の契りの強いたとえをもとに、想像上の鳥を描いていましたが、その鳥は東南アジアに生息する「極楽鳥」、またの名を「風鳥」という鳥の剝製をもとに「比翼の鳥」を描いたと伝えていました。
『生花秘伝集』が載せている「相生の松」に話を戻します。一般的には、この絵図のように枝葉が交差するように生けることを、花の道の師匠は「禁忌」だとして、注意してきました。ところが結婚式に生ける松に限っては、このように枝葉を交差して生けることを許してきました。その姿が「比翼の鳥」を生け表していることを理由に許し、さらに花の道の奥義(おくぎ)を伝えている生け花、「秘伝の花」として伝えてきたのです。そこに、花の道に添って生けられた、生け花を生けることの難しさが潜んでいると云ってよいでしょう。
私は、これから花の道の教授になることを目指す若い人に、
「結婚式が執り行われる会場に、『比翼の鳥』を生け表した生け花を生けられるようにお稽古をしておきましょう」
と話します。すると若い弟子さんたちからは、
「そのような生け花を生けても、現代の若い人には理解できません。ですから、受け入れられないように思います。そのような生け花を生けてやるよりも、美しく咲いている赤いバラの花を沢山生けてやった方が、友達は喜ぶに決まっていると云えますが・・・」
との答えが返ってきました。
我が国の先人たちが大切に守り伝えてきた「相生」や「比翼・連理」の言葉が含み持つ「共棲」の言葉の意味を、多くの若者たちにも知っていただきたいです。
「共棲」の言葉は、マメ科の植物の根を観れば、その意味を簡単に理解することができます。たとえば、蓮華の根を掘り起こしてみると、その根には小さなコブが沢山付いています。その小さなコブは、根粒バクテリアという菌が棲み付いているためにできたコブです。根粒バクテリアは空気中の窒素を使って養分を作り、棲みかを与えてくれるレンゲ草にも養分を与えます。このような助け合いの関係を「共棲」と呼んできました。しかしながら、何時しか、そのことを忘れてしまっているのです。
「比翼の鳥」は、中国で生まれ、我が国では『高砂』の物語をとおして語られ、京都の将軍のあいだで究極の願いとされました。その想像上の鳥の姿を、職人や商人といった庶民たちにも理解できるようにと、書物を通してやさしく説いたのは、一条兼良、藤原惺窩、貝原益軒、中村惕斎たちでした。彼らが活躍した時代は異なっていましたが、京都の町を中心に学問を深めた学者たちです。その学者たちが語り聞かせた言葉をもとに、花の道の先人は、床の間に、生け花を生け示してみせたのです。その姿は絵師によって描かれ、さらに木版刷りの「花書」として出版されることで、我が国の隅々へと伝えられて行きました。
江戸時代初期に著された「花書」には、先の学者たちが語り聞かせた言葉を目で見える姿として生けあらわした抛入れ花が、数多く今に伝えられています。その抛入れ花は京都の町を中心に醸され深められた、我が国固有の文化である「花の道」の意にそって生けられていました。つまり、花の道の先人が生け示した抛入れ花の姿とは、京都の町で深められた学問をもとに生け表された姿を、絵師が写し取り、今に伝えられているといえます。その抛入れ花の姿が、我が国の人々の心をどれほど豊かにしてきたかは、あらためて言うには及ばないことです。このすばらしい我が国固有の文化である生け花の文化を、もっと多くの人の知っていただきたいと思います。
『生花秘伝集』 元禄十五年 著者不詳 刊
『抛入花伝書』 貞享元年 初代池坊専好 刊
『説文韻府』 元文十年 夏川氏元編 刊
『和爾雅』 元禄七年 貝原益軒編 刊
『頭書訓蒙図彙』 寛政元年 中村惕斎 刊


関連する記事
 米村 孝一
米村 孝一
出身地
熊本県 熊本市
生年月日
昭和22年生
職業
自営業 いけはな研究家 花道・洗心流教授
テーマ
はなの道は、何時興ったのか。また、一輪の花に、どのような意味が込められていたのか?
過去の出筆
『はなをいる 花に聴く』 マインド社刊 2018年
『石州流生花三百ケ條』監修・解説 マインド社刊 2021年
『いなほのしづく』(A3用紙に約三千字の文章、関連した絵図) 月一回発行。令和三年六月で三六三号 県立図書館等にて公開。
|いけはな研究家 花道・洗心流教授|花道/生け花
アクセスランキング
人気のある記事ランキング















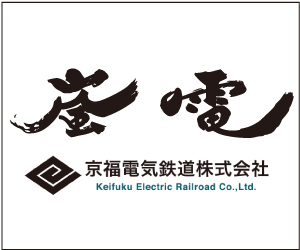





貝原益軒(1652-1713)は、儒学の先駆者である藤原惺窩の教えを受けた、松永尺五(せきご 1592-1657)の門下生。尺五は、惺窩の教えを広めるため、京都に私塾を開き、門弟が数千人いたと伝えられている。その中にあって最も俊秀であったと伝えられているのが益軒。彼は中国で著された『爾雅』を手本に『和爾雅』を著す。その内題をコピーしたもの。