
【第六回】茶の湯の祖、村田珠光が生けた抛入れ花
義政は、正月の節会を祝うため宮中へ参内したのち、洛東の銀閣寺に帰ってきた。銀閣寺へ帰り着いた義政は、冷えた体を温めるため、相阿彌に一服の茶を所望した。そこで相阿彌は、茶の湯の支度をするしばしの間、側にいた珠光に、床の間に花を生けるように申しつけた。その申しつけを拝受した珠光は、絵図のような抛入れ花を生け飾った。
説明文によると、この抛入れ花は〝わび茶の湯〟の祖と称されている、村田珠光が生けたものでした。床の間の壁には雪を頂いた竹の葉を描いた掛け軸をかけ、その前に獣面を象った唐金製の水盤を置いて雪を盛り、福寿草が生けられていました。この抛入れ花が生けられた日は正月元旦であったことが分かります。
絵図を観ると、寒中だというのに、掛け軸には雪を頂いた竹が描かれていました。その前に、雪を盛った水盤を置き、黄色の花を開いた福寿草が生けられていました。寒中に、このような飾り方をすることは、見ただけで更に寒くなるとして、一般的には「禁忌」、タブーだとされてきました。ですから、師匠は、弟子たちに、「そのような飾りつけをしてはいけません」と注意を促してきました。では、何故、珠光は、禁忌を犯した抛入れ花を生けたのでしょうか。
正月元旦は、庶民(当時の農民)たちにとっては農事初めの日でもありました。そこで農民たちは正装をして田圃へ行き、取水口の前に幣を立て、その前にゴザを敷き、三宝に昨年収穫した米を盛り、
「今年の秋は、黄金色の実をたわわに稔らせた、稲の穂が頭を垂れますように」
と豊作祈願をしてきました。
そのことを知っていた珠光は、正月に雪が降り積もることは、山や溜池などに多くの水が蓄えられることを意味している。そのことを踏まえて、珠光は床の間に雪を盛った水盤を置き、黄色い花を咲かせた福寿草の花を生けることで、
「義政さん、今年も豊作であることを、農民と一緒に願いましょう」
との思いを込め、この抛入れ花を生けたに違いありません。この抛入れ花には、庶民たちの願いを込め生けられていたのです。ですから、その思いは茶の道だけでなく、花の道にも通じるものがあり、珠光が花の道にも大きな影響を与えてきたことを、この抛入れ花にて知ることが出来るのです。
『君台観左右帖記』 文明八年 能阿彌筆 (江戸時代初期写)
『和泉草』 寛文の頃 藤林宗源編纂 (私蔵はコピー本)
『抛入花之園』 明和三年 禿帚子著 刊
『温故年中行事』 江戸時代後期 著者不詳 刊
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます
“パン食”と“昔の朝食”から見た京都人の本性京都独特の住所がもたらす「誤配のメカニズム」
十三参りでやったらあかんことは?【京都人度チェック】
「お千度」ってどんな行事?


関連する記事
 米村 孝一
米村 孝一
出身地
熊本県 熊本市
生年月日
昭和22年生
職業
自営業 いけはな研究家 花道・洗心流教授
テーマ
はなの道は、何時興ったのか。また、一輪の花に、どのような意味が込められていたのか?
過去の出筆
『はなをいる 花に聴く』 マインド社刊 2018年
『石州流生花三百ケ條』監修・解説 マインド社刊 2021年
『いなほのしづく』(A3用紙に約三千字の文章、関連した絵図) 月一回発行。令和三年六月で三六三号 県立図書館等にて公開。
|いけはな研究家 花道・洗心流教授|花道/生け花
アクセスランキング
人気のある記事ランキング














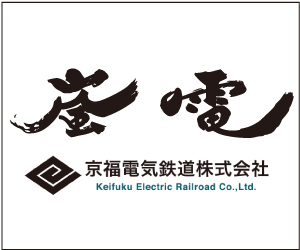





同書は江戸時代後期に著されたもの。庶民たちが執り行っていた行事の様子を、絵図にして今に伝えている。ここには、寒風の中で「水口祭」を執り行う農民たちの様子が描かれている。