
天皇陵・皇后陵・親王陵 -北区周辺を訪れる-
7.第102代後花園天皇火葬塚
堀川通り鞍馬口下ル東に面している。
後花園天皇は、伏見宮第3代貞成親王の第一皇子として生まれる。
この時代幕府足利将軍が目まぐるしく変わり、8代将軍義政は遊興に走り、これには天皇さえ戒められている。
応仁の乱の最中、文明2年(1470年)室町殿にて52歳で崩御されたが、ご遺骸は悲田院のあるこの地に火葬された。
塚は堀川通りに面しているが、うっそうとした樹木が生い茂っている。
8.天皇塚
北大路通堀川西入北側にあった小円墳であった。
堀川天皇中宮篤子雲林院陵とも言い、圓融天皇火葬地とも言われる。
その小円墳は開発で破壊され、今の北図書館が立つ地かその東側の地であったかと思われる。
9.般舟(はんじゅ)院陵 伝式子内親王塚
千本今出川東にある嘉楽中学校の間、今出川に面して北側にある。
後土御門天皇典侍源朝子陵、後花園天皇典侍嘉楽門院藤原信子陵など、一陵三分骨所十墓からなり、皇妃の多くは当院に葬られた。
嘉楽中学校の校名は後花園天皇典侍嘉楽門院藤原信子の嘉楽から名付けられた。
これらの陵は般舟三昧院が伏見より移建された際に、移されたものである。
伝式子(しょくし)内親王塚は般舟院陵の域内西方にある。
樹木のうっそうと茂る小墳の上に小五輪石塔が置かれている。
周辺には数個の石仏が並んでいる。
樹木に覆われた小高い墳の中央にある小さい五輪石塔が親王塚である。
嘉楽中学校の今出川に面して正門があるが、その横に「禁裏道場跡」の大きい石碑がある。
秀吉は文禄3年(1594年)伏見城を構えるにあたり、現在地に般舟院を移建された。
寺は引き続き天台・真言・律・浄土四宗兼学の禁裏道場として栄えた。
その後歴代の尊牌を泉涌寺に移されたので、寺地を分割上地して嘉楽中学校とした。
10.第78代二条天皇陵 香隆寺陵
平野神社の西、等持院の東にある。
二条天皇は第77代後白河天皇の第一皇子であったが、父子との仲はうまくいかなかったと言う。
永万元年(1165年)御年23歳で崩御された。
龍安寺裏山の小高い山を朱山といい、その南方山麓には七つの天皇陵などが点在する。
山全体が天皇陵で占められ、開発が及んでいない。
設置された当時のままの自然環境に恵まれ、京都盆地を見渡せる絶好のビューポイントである。
11.第69代後朱雀天皇 圓条寺陵・第70代後冷泉天皇 圓教寺陵
龍安寺境内の北に圓条寺陵がある。
後朱雀天皇は、第66代一条天皇の第三皇子である。
長元9年(1036年)兄である第68代後一条天皇の崩御に従い、28歳で即位した。
この頃、比叡山では争いが激しくなり、京にもそれが飛び火していた。
天皇は「自分の徳がないせいだ」と強く自責の念を抱いていたという。
また、治世の末期には天然痘が大流行し、天皇も感染した。
様々な治療を試みるも容態は好転せず、寛徳2年(1045年)に37歳で崩御。
後冷泉天皇と後三条天皇については「4」と「1・2」参照して下さい。
【歴史愛好家シリーズ】この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます
▶︎千本頭周辺のトピックス▶︎「有名人が織りなす、祇園祭事件簿」前編
▶︎千本通 -冥界への路- パパっと分かる平安遷都
▶︎夏越の大祓に行って厄をかぶる話
▶︎[エッセイ]雨の貴船を楽しむ


関連する記事
 橋本 楯夫
橋本 楯夫
昭和19年京都市北区生まれ。
理科の中学校教諭として勤めながら、まちの歴史を研究し続ける。
得意分野は「怖い話」。
全国連合退職校長会近畿地区協議会会長。
|自称まちの歴史愛好家|北野天満宮/今宮神社/千本通/明智光秀/怖い話
アクセスランキング
人気のある記事ランキング



















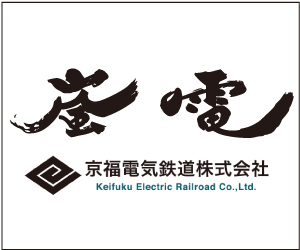





嘉楽中学校の校名はこの藤原信子から名付けられた。