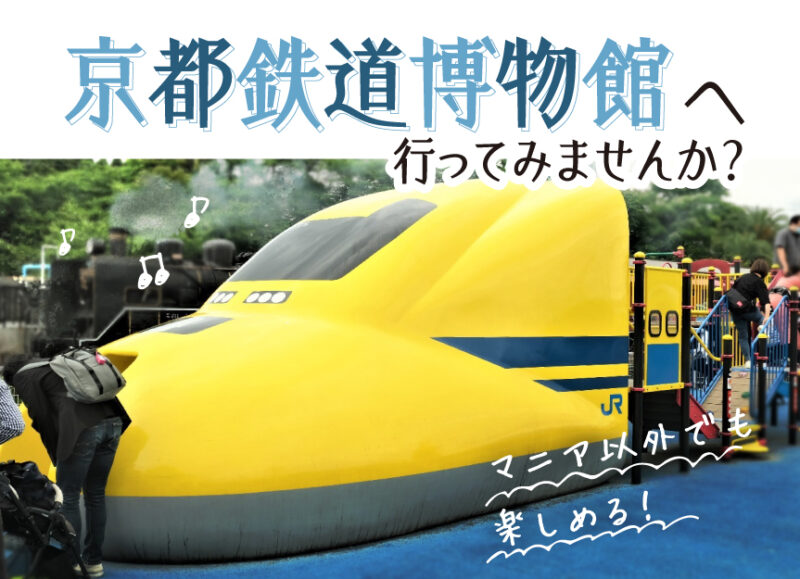京都の初冬の行事を代表するのは御火焚である。
御火焚は宮中の「庭火」の系譜を引きながら、種々の信仰と習合しつつ今日まで続いている、京都特有の行事である。
これは江戸時代から京都を中心として行われてきた行事で、もともと旧暦11月に社前で火を焚いて祝詞や神楽を奏し、新穀とお神酒を供えて神を祀る行事であり、民間の新嘗祭の一種であるとも考えられている。
御火焚は神社や寺院だけでなく、各町内でも行われ、みかんや御火焚饅頭などを供えて、それらを子どもたちにも分け与えるのが古くからの慣習とされている。
伏見稲荷大社の御火焚祭
京都で毎年最初に御火焚祭が行われるのは伏見稲荷大社である。
新暦11月8日、境内には3カ所の火床が作られる。
まず本殿で火鑚神事が行われ、そこで鑚り出された神火を火床へ移して数十万本の火焚串が焚き上げられる。
伏見稲荷大社の御火焚祭は京都一のスケールだといえるだろう。
他にも、花山稲荷神社、八坂神社、今宮神社、車折神社など、多くの神社で行われるほか、太秦広隆寺や東山区正覚庵などの寺院でも行われている。
中でも正覚庵の御火焚祭は、「筆供養」を目的として行われている点が特徴だといえる。さらに町内で行われる御火焚もある。
たとえば、祇園祭の山鉾の一つである「太子山」を出す下京区太子山町では、山と町の名である聖徳太子に因んで、広隆寺に合わせて毎年11月22日に、一年最後の町内の集会として御火焚が行われている。

巻物や俳諧から見る御火焚
ところで、佛教大学図書館が所蔵する、17世紀末から18世紀初頭頃の京都の祭事を描いた『十二月あそひ』と称される絵巻には、町家の前に小さな神輿を据え、その前で火を焚きながらさまざまな供物を供え、町内の老若男女が楽しげにひと時を過ごす様が描かれている。
またその詞書に「うちより民の家々まて、庭火をたきて神をいさむ事もゆへなきにハあらす」と記されている。
また17世紀中頃に成立したとされる俳諧『山之井』には、
「祇園は午の日、かの神社は申すにおよばず、下京の氏子ども、小さな神輿を町々にかきすえつつ、大道に薪を積みて御火焚きし、また時の菓物ども、神酒など奉りはべる」
と記され、近世における京都市中における御火焚の様子を窺うことができる。
さらに貞享2(1685)年の成立とされる『日次紀事』の「十一月の項」には、
「この月毎神社の縁日、柴薪を神前に積み、神酒を備へ、しかる後に火を投じてこれを焼く。
(中略)氏子の家もまた、その産土神の縁日をもって火焼を修す」と記されている。
さらに正徳3(1713)年成立の『滑稽雑談』には、「十一月諸社御火焼の神事あり。
これ当年の新穀を初めて共進の神事なり。
官符ありてこれを勤むるは新嘗祭といひ、官符なき社、その神官これを供へ奉る。
神事夜分に行ふゆえに、庭燎を設く。
俗、御火焚きといふ」
とあることから、近世には、大社で行われる御火焚は「新嘗祭」としての意味を有していたことがわかる。
民間の新嘗祭、霜月祭
御火焚祭が元は旧暦11月、つまり霜月に行われるのは、この月には最後の収穫祭である「新嘗祭」が行われることと、さらにこの月が「冬至」の月であることと深い関わりがあると考えられる。
新嘗祭は皇室が中心となって行われる収穫祭であるが、民間で行われる新嘗祭は、一般に「霜月祭」とよばれる。
このまつりにはさまざまな姿が見られるが、基本的には先祖に新穀を供えて収穫を感謝し、来る年の豊饒を祈願する祭りである。
そして霜月下旬には冬至を迎える。
冬至は一年でもっとも昼が短くなる日であることから、昔の人々はこの時期に太陽の力がもっとも衰えるものと考えていた。
衰弱した太陽のエネルギーを復活させ、太陽を生まれ変わらせるためのまつりが霜月祭であったといえる。
このような信仰的基盤が御火焚や霜月神楽などの、民間の新嘗祭としての霜月祭として残ったものと考えられよう。

大師講
冬至の月である霜月に行われるもっとも象徴的な行事は「大師講」である。
大師講は、元は霜月23日から24日にかけて行われた行事で、この日はオダイシサマが姿を変えてこっそりと訪れる日であるから、大師粥とよばれる小豆粥を作って接待するなどという伝承が、全国の広い地域から聞くことができる。
オダイシサマとは、古くはタイシ(太子)、すなわち尊い客人神を意味した語であったものが、後に仏教思想の影響によって弘法大師を代表とする高僧を指すようになったと考えられる。
中には元三大師や達磨大師だという例もあり、必ずしも弘法大師と決まっているわけではない。
いずれにしても、庶民にとってはめったに謁見することがないような高僧であることは間違いない。
また大師さまは、この日には乞食のようなみすぼらしい姿をしてやって来るともいわれている。
また大師さまは一本足であるとか、足がスリコギのようになっている等という、不具者としての伝承も聞かれる。
いずれにしても古い大師講の伝承には、太陽がもっとも衰える季節、すなわち冬至に、遠いところから神がやってきて人々に幸をもたらすという、日本人の原初的な信仰としての来訪神信仰を垣間見ることができるのである。
降雪と不具者の関係
たとえば丹後半島の丹後町間人(現京丹後市)では、霜月23日をダイシコサンとも、またスリコギカクシともいい、達磨大師を祀るという。
大師さまは修行によって足の先が腐ってスリコギのようになっているので、これを隠すために雪が積もるのだといわれている。
また京都府船井郡和知町(現京丹波町)では、11月23日をオダイシサンの日といい、オダイシサンは一本足だから必ず雪が降って足跡を隠すのだという。
さらに兵庫県朝来郡和田山町では、12月23日から24日にかけて、スリコギカクシの雪が降るという。
昔、オダイシサンが村へやってきて稲の穂で作った団子を所望したが、貧しい村のお婆さんは足がスリコギのようになっていたために、田の稲を盗むとその足跡からすぐにわかってしまうので仕方なく断った。
するとオダイシサンは稲を盗んでもわからないように、雪を降らせたと伝えられている。

このような、お大師さんが不具者の姿で村々を訪問するという伝承は広い地域で聞くことができる。
また和田山町の伝承は、一般に「あと隠しの雪」と称されるが、これらは基本的に霜月23日の夜には尊い神がやって来るという伝承が元にあり、神の来臨を象徴的に暗示する伝承として「不具者」や「降雪」の話が付随したものと考えられる。
しかし、貧しい老婆がお大師さんをもてなすために盗みをはたらこうとするが、それを憐れんだお大師様が、盗みがわからないように雪を降らせるという伝承は、仏教的な色彩を帯びたものとも考えられることから、少し後になって語られるようになったものかもしれない。
仏教の影響を受けた「施し」
一方で、京都とその周辺地域の大師講は早くから仏教の影響を強く受けたものと思われる。
御火焚の影響を受けた火の行事として伝えられ、また仏教の「施し」を目的とした大師講の例が京都府長岡京市で聞くことができる。
長岡京市今里・井ノ内・馬場などでは、近年まで大師講が行われていた。
この地域では「大師さんのお湯」ともいわれ、お風呂を沸かして人々に施し湯をすることが主な目的であった。
たとえば井ノ内では、かつては一月晦日にトウヤの家で鉄砲風呂を沸かし、周りを莚で囲んで人々に入ってもらった。
この風呂を「弘法さんのお湯」とよぶ。
トウヤでは風呂に入りに来た人たちに、ぼた餅を振舞ったという。
また馬場では、かつては毎年一月二十一日を中心とした一週間の間、村内の軒のある家に頼んで前庭を貸してもらい、薬湯を沸かした。
この風呂には村人はもちろん、他所の者でもだれでも入ることができたといわれている(7)。
このように、長岡京市の大師講は一月の行事として伝えられているが、古くは秋から冬の行事であったという伝承も聞かれることから、やはり本来は霜月の行事であったことが想像できる。
そこには風呂を沸かして「施し湯」をして、さらにぼた餅などの食物も提供したというところに特徴が認められる。
そのことからも、これ地域の大師講は、仏教でいういわゆる功徳を積むための「施し」を目的として行われていたことがうかがえる。
大根焚
ところで、12月になると、京都ではいくつかの寺院で「大根焚」が行われる。
鳴滝了徳寺や千本釈迦堂の大根焚が有名であるが、これも一面では「御火焚」の系譜を引く行事であると考えられる。
右京区鳴滝にある真宗大谷派の了徳寺では、毎年12月9日と10日に大根焚が行われる。
伝承によると、鎌倉時代の建長4(1252)年の霜月のある日、親鸞聖人が嵯峨清凉寺と愛宕月輪寺参詣の途中に当寺に立ち寄られた際、村人たちが大根を炊いてもてなしたことに由来するといわれている。

その年は稲が不作で、村人たちは上人に差し上げる食物がないことを嘆き悲しんだが、幸いに大根だけは豊作で、収穫したての新鮮な大根を塩だけで炊いて差し上げたところ、親鸞聖人は村人たちが丹精込めて炊いた大根をたいそう喜ばれ、そのお礼として、薄の穂を束にして筆代わりとし、「歸命盡十方無礙光如來」の十字名号を書いて寺に納められたと伝えられている。
この故事に因んで、今日では報恩講行事の一環として行われているのが大根焚である。
いつしかこの大根には中風除けの効験があるとの伝承が生まれ、近年では京都内外から大勢の参拝者があり、毎年3000本の大根を準備しているという。
なお、親鸞聖人が書かれたという名号の掛け軸は今も大切に伝えられ、大根焚当日には本堂に掛けられる。
また本堂の裏には、親鸞聖人が筆にしたという薄に因んで、「薄塚」が祀られている。

了徳寺に伝わる親鸞聖人のような高僧が地域へ来訪したとする伝承には、先に紹介した「大師講」の行事と共通するものがあり、大根焚にも、冬至が近いこの時期に遠いところから神々がやってきて人々に何らかのメッセージを残してゆくという、古い来訪神の信仰を垣間見ることができる。
この時に訪れ来る神仏は、弘法大師や親鸞聖人などすべて普通では滅多に謁見することができないような偉大な存在であり、このような高僧がまさに来訪神と同様の存在としてとらえられているのである。
そしてこのような偉人、すなわち異界からやってくる神的存在への施し物、供物として、京都ではこの季節を代表する野菜としての大根がクローズアップされたのではないだろうか。
その意味では、「大根焚」は火を焚くという点からすれば、御火焚の系譜を直接に引く行事であり、また内容からすれば、広義の意味での大師講の一類型であるといえるかもしれない。