
神輿をかつぐ人だけのお弁当
祇園祭といえば山鉾巡行だけがクローズアップされがちやけど、本来は神様の御霊を神輿に乗せてお迎えとお見送りをする、神幸祭と還幸祭がお祭の中心。そこで配布される「みこし弁当」は、お弁当の原点といえる素朴で力強いものなのだ。
弁当作りではなく弁当打ちなのは、炊き立てのご飯を長方形の型によそい、広げた竹の皮へ打ち付けて型から外すので。両日とも朝から、「バコッバコッ」という音が聞こえてくると、「あぁお弁当作ってはるなぁ」と思う。
男衆は流れ作業でゴマをふり、梅干しをのせて脇に黄色いおこうこを添え、竹の皮をたたんで、赤い札を置いて、中央を藁で結わえて…見事な流れ作業で次々と弁当をこしらえていかはる。余談であるが、町内の女性も下働きは手伝うけど、弁当打ちの工程には触れてはならん決まりになっているそう。弁当打ちは男の世界、なのである。
17日は約2000食、24日は約2600食ほど作り、地元の氏子さんや御神酒を献じた人にも配られる。輿丁さんには力の源、一般人には疫病除けや安産の御利益があるそうだ。安産は私らもう関係ないけど(^^ゞ 毎年ありがたくいただくのである。
神様も輿丁さんも三条通で休憩
還幸祭には、上久世の綾戸國中神社から駒形稚児さんが来はる。駒形稚児さんは、三若会所のやや南に鎮座する武信稲荷神社で休憩される。乗ってきたお馬さんも境内で休憩する。そして神輿に先駆け、パッカパッカと八坂神社を目指すのだ。近所に住む人はまず駒形稚児さんを見送り、そして中御座の神輿が商店街を通るのを待つ。
午後8時ごろ、西の方から「ホイットホイット」のかけ声が聞こえてくる。そして三若会所と武信稲荷神社のある通りでいったん止まり、神輿を高く掲げて鳴閂(なりかん)を威勢良く鳴らすのだ。
そして神輿が又旅社前に留まっている間、輿丁さんたちは周辺の公園や駐車場などで休憩しはる。その時に広げるのが、みこし弁当だ。「たいへんな重労働やし脂っこいもんなんか喉を通らん。白飯が何よりのご馳走」と、輿丁さんたちは言う。それとビールやねww
日本人の原点ともいえる日の丸弁当は、しみじみとおいしいんやろう。私ら、神輿を担いでなくてもほんまにおいしいし。特にあの、梅干しとおこうこが接したご飯の赤いとこ黄色いとこが、たまらんのよね。
25日には千団子の授与がある
還幸祭から明けて25日には、又旅社で千団子授与がある。還幸祭の際に神輿へお団子が供えられる御供社奉饌祭というのがあり、翌日にお下がりを頂戴するのだ。又旅社へお参りすると、八坂神社の袋に入ったお団子がいただける。これは無料やけど数量限定ね。
シンプルな甘いお団子で、よばれたら無病息災のご利益があるそう。これもまた、地域の人だけが知る祇園祭の一コマなのだ。
※2019年夏の記事です。
[祇園祭特集]記事一覧
長刀鉾稚児家 祇園祭への想い
神輿をかつぐ人だけのお弁当
祇園祭と市電
納涼床の起源 神輿洗い
神輿の先陣をきる榊台
3分で読める「祇園祭ゆるゆる入門書」
僕は京都の銘竹問屋 Episode-6『祇園祭と竹』
祇園祭の頃だけ、開かれる井戸
久世駒形稚児の素顔
風流「祝い提灯」について
京都ハレトケ学会『祇園祭と御大礼』
三条通の祇園祭
三若、四若、錦って?
大船鉾復興裏話〜お囃子からはじまった鉾復興〜
嵐電 四条大宮駅前 ー 御神輿と丹波八坂太鼓 ー
【KLK×祇園祭】一番搾り 祇園祭デザイン誕生秘話
祇園祭「鷹山」について
錦の神輿 ー担ぎ手の熱い夜ー
神と人と街が交わる祭り「祇園祭」


関連する記事
 川添 智未
川添 智未
京都市北区生まれ、中京区在住。
たまねぎ工房の屋号でライター・フードコーディネーターをしている。
酒好きが高じ唎酒師・日本酒学講師となって酒セミナーを開くほか、京の食文化ミュージアムあじわい館「食と酒のかたりべ」でもある。
飲み食い以外の趣味は犬で著書に「洛中いぬ道楽」「いろこよみ-風景に見る日本人の心-」、相方は犬用介護ハーネスの玉葱工房)、ブログ【京都・町家ぐらし】
|ライター・フードコーディネーター|みこし弁当/パン/ひなまつり/水無月/食べ物
アクセスランキング
人気のある記事ランキング



















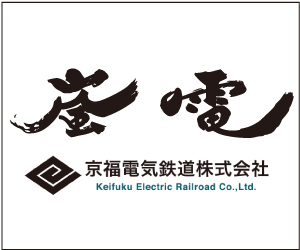





写真提供:三若・吉川忠男氏